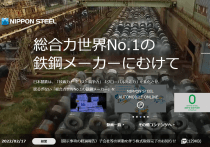日本製鉄、利益6千億円を達成、10年間の構造改革が結実…高炉廃止も断行
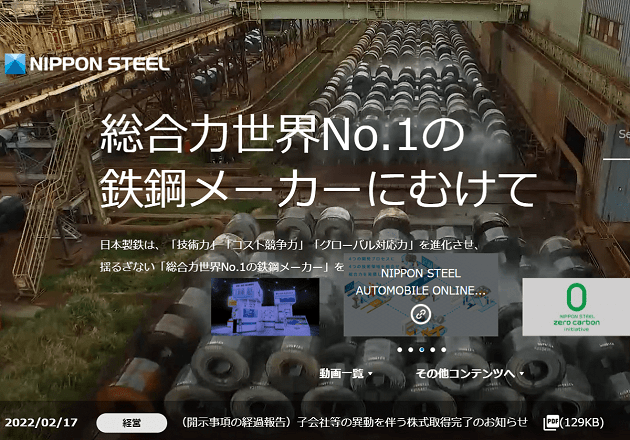
最近、日本製鉄は事業運営体制の変革を加速度的に進めている。その一つとして注目されるのは、新しい車載用のバッテリーなどとして利用が期待される全固体電池関連の事業だ。特に、日本製鉄は全固体電池分野での分業体制の加速を念頭に置いているとみられる。製造コストの高さや世界標準の技術規格の確立など、全固体電池の普及には解決されなければならない課題が多い。その状況下、日本製鉄は全固体電池の製造や利用に関するデータを蓄積して新しいサプライチェーンを確立し、高い成長につなげようとしている。
現在、世界経済の後退懸念は高まっている。最大の鉄鋼製品消費国である中国では、経済成長率の低下傾向は一段と鮮明だ。中国の過剰鉄鋼生産能力も加わり、世界的に鉄鋼、非鉄関連製品の価格にはさらに強い下押し圧力が加わる展開が懸念される。それに加えて、日本製鉄は脱炭素に対応するために水素製鉄など新しい製鉄技術の確立も急がなければならない。日本製鉄にとって収益源多角化は急務といえる。そのための一つの取り組みとして、どのように日本製鉄が国内外の企業と連携して全固体電池のサプライチェーンを確立して付加価値の創出に取り組むかが注目される。
日本製鉄が徹底して取り組む固定費圧縮
過去10年程度の間、日本製鉄は徹底して事業運営の効率性の向上に取り組んだ。2016年度ごろからその成果は徐々に発現し始めた。2016年度に1,309億円だった同社(当時の社名は新日鐵住金)の純利益は徐々に増加した。新型コロナウイルスの感染発生によって世界経済が一時大混乱に陥った2019、20年度は最終赤字に陥ったものの、2021年度の純利益は6,373億円と大きく増加した。昨年度の収益増加は一過性のものというよりも、同社が不退転の決意で徹底して固定費圧縮に取り組んだ成果といえる。固定費を削減するために、日本製鉄は国内で運営してきた高炉の休止などを加速した。
日本製鉄のように高炉を持つ一貫製鉄会社にとって、高炉の運営は生産能力の維持と強化に欠かせない。ただし、高炉の維持と管理には付随施設を含め数千億~1兆円程度の設備投資が必要であるといわれている。2021年度、日本製鉄は4,074億円の設備投資と3,306億円の減価償却費を負担した。主要産業の中でも高炉を持つ一貫製鉄会社が負担する固定費は大きい。そうした特性から、過去、世界の鉄鋼需要が減少すると日本製鉄の最終利益は大きく減少し、状況によっては赤字に陥った。それに加えて、いったん高炉に火を入れると、操業が休止するまで高炉の保守を続けなければならない。
固定費負担の高さという課題を克服するために、日本製鉄は高炉休止という抜本的な構造改革を強化した。固定費は圧縮された。それに加えて、日本製鉄は選択と集中を進めた。それによって、わが国の自動車メーカーなどが必要とする高張力鋼板(ハイテン)など高付加価値製品の生産に集中した。顧客企業には値上げを通達して売上高の増加とコスト吸収力の向上が目指された。その結果として、事業環境が変化しても、事業利益(売上収益-売上原価・販売費及び⼀般管理費・その他費用+持分法による投資利益・その他収益)が獲得されやすい収益構造が実現した。8月4日に日本製鉄は2023年3月期の最終利益が6,000億円に達するとの予想を公表した。その水準は前年度実績を下回るものの、過去の平均的な利益水準より高い。
全固体電池で新しい収益源確立狙う日本製鉄
生き残りをかけ、さらにはより高い成長を目指すために、日本製鉄は新しい取り組みを急速に強化している。その一つが全固体電池関連の事業だ。全固体電池とは、電解質が固体である二次電池のことだ。国内の研究機関や企業は、世界各国に先駆けて全固体電池の研究開発を重ねてきた。現状、関連する特許件数ランキングの世界トップ3は、トヨタ自動車、パナソニック、出光興産だ。今日の車載用バッテリーなどに使用されているリチウムイオン電池の電解質は液体だ。
一般的に、全固体電池はリチウムイオン電池よりも安全性が高く、電気自動車(EV)などの航続距離延長に貢献すると期待されている。そのため、自動車の電動化の切り札として全固体電池の実用化を目指す日本企業は多い。全固体電池は国内産業界全体が脱炭素の取り組みを加速し、高い成長を目指す数少ない先端分野の一つといっても過言ではない。
その状況下、日本製鉄はかなり長期の展開を視野に入れて、事業運営体制を整備しはじめた。同社は、他の企業が設計、開発した全固体電池の試作や性能評価を行う体制を整備している。一つの見方として、日本製鉄は全固体電池分野での国際分業の加速を念頭に、事業運営体制の整備を急いでいるようだ。国内産業全体で考えると、最も重要なことは世界各国に先駆けて全固体電池の大量生産と実用化を実現し、必要な国際規格やルールの策定を主導することだ。
そのために試作と実証実験を重ねて全個体電池の出力、安全性などに関するデータをより多く収集しなければならない。データをもとに改良を重ねて実証実験をさらに増やす。それによって、全固体電池のライフサイクルアセスメント(素材生産、使用、廃棄やリサイクルなどの過程で排出される温室効果ガスの量などを評価し、持続可能な資源利用を目指す取り組み)に関するルール策定も進むだろう。その際、個々の企業がすべてのプロセスを自己完結するよりも、得意な分野に集中したほうが効率性は高まる。そうした展開を見据えて日本製鉄は全固体電池の試作品の受託製造と性能評価体制の確立を急いでいると考えられる。
成長期待高まる日本製鉄の全固体電池事業
今後の展開として注目されるのは、日本製鉄がどの程度の時間軸で全固体電池の受託生産体制を確立するかだ。受託製造体制の整備によって、日本企業や研究機関が持つ全固体電池関連の研究や基礎的な製造技術は収益を生みやすくなるだろう。それによって、全固体電池の供給に不可欠なサプライチェーン整備も加速するはずだ。
新しい供給網構築などにかかるコストを抑えるためには、規模の経済効果を高めることが求められる。そのために日本製鉄は既存分野で固定費圧縮を強化して先端分野に資金を再配分しつつ、複数の企業などとの連携を強化して事業規模の拡大を目指すだろう。全固体電池の分野で研究開発や試験の体制を強化する日本企業は増えている。日本製鉄はそうした企業と協力して、共同での研究開発、資材調達、生産設備の運営、さらには国内外の企業を巻き込んだ実証実験体制を整備し、ビジネスモデルの確立に取り組むと予想される。その結果として、日本が全固体電池に関する世界のルール策定をより有利に進める可能性は高まる。
過去、日本が素材開発などの分野で世界に先行した事例は多い。しかし、ビジネスモデルを確立して収益を得るという点では、中国や韓国企業の後塵を拝した。日本製鉄に期待したいことは、その教訓を活かすことだ。自社ですべての工程を完結するのではなく、全固体電池の設計、開発、大量生産、素材供給、リサイクルなど、それぞれのプロセスにおいて強みを持つ企業との協働体制を強化する。それは先端技術の普及を支え、全個体電池分野における国内産業界の競争力向上に決定的なインパクトを与えるだろう。
ただし、全固体電池には克服しなければならない課題も多い。例えば、EV搭載が目指されている硫化物系全固体電池の場合、硫化水素が発生するリスクをどう抑えるかなどの課題がある。リチウムイオン電池と比較したコスト優位性の確保も課題だ。しかし、そうであるからこそ民間企業はチャレンジし、先行者利得を目指すべきだ。口で言うほど容易なことではないが、日本製鉄が国内産業界のもつ全固体電池関連の最先端知識や製造技術を結合し、世界各国の先を行くサプライチェーン構築に取り組むことを期待したい。
(文=真壁昭夫/多摩大学特別招聘教授)