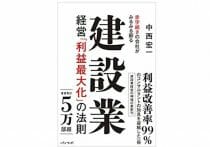商社から建設業界に転職→残業減+やりがい増で大満足…建設業=低賃金の嘘

少し前にインターネット上に投稿された、商社から建設業界に転職したところ年収はやや減ったものの、勤務時間は減り、休日は増え、やりがいがあって満足しているという投稿が一部で話題となっていた。いまだに「3K」「低賃金」というイメージが根強い建設業界の待遇・労働環境の実態はどうなっているのか。また、魅力の高い業界といえるのか。専門家の見解を交えて追ってみたい。
この投稿者は建設関連会社に計測工として勤務し、年収は商社時代の4分の3となり、勤務時間は基本的には9~17時で給料には「みなし残業」分が60時間相当含まれ、年間の休日数は約120日だというが、このような待遇・労働時間は建設業界では一般的なのか。土木・建設会社のコンサルティングや建設業界に関する情報発信を行っているクラフトバンク総研所長の高木健次氏に聞いた。
「現在、建設業界は、積極的に働き方改革やデジタル化に取り組み業績が伸びている会社とそうではない会社に二極化しており、比率としては前者が約2~3割、後者が約7~8割です。この投稿者の方は前者に在籍していると思われます。建設業界全体でみると、年間の総労働時間は全産業平均と比べて68時間長く、年間の出勤日数は12日多く(国土交通省/23年8月発表『建設業における働き方改革』より)、週休2日を確保できていない人が多いのが実情です。また、日本建設業連合会(日建連)が23年秋に実施したアンケートによると、約67%の現場で月45時間・年360時間までという時間外労働の原則ルールを守ることが困難と各社回答しています。
こうした長時間労働の問題を解決しながら、工事に3Dプリンタを活用したりベンチャー企業と連携したりといったデジタル化に取り組んでいる企業が業績を伸ばしており、遅れている会社からの転職組も含めて人材が流入しています」
「若者の就業者が減っている」という誤解
日建連の調査によれば、加盟社の23年度の国内建設受注額は22年度比9%増の17兆6646億円で、過去20年で最高額となった。こうした建設需要の高まりと「建設業の2024年問題」といわれる時間外労働の上限規制(時間外労働時間が原則「月45時間・年360時間」に制限され、違反は罰則の対象となる)、高齢化などにより、建設業界の人手不足は深刻だと指摘されている。
「2010年に504万人だった建設業就業者は22年には479万人に減っており(前出・国交省資料より)、その一方で建設需要は伸びています。加えて、建設現場での土木・建築作業に関する人材派遣は労働者派遣法で禁止されています。また、有料職業紹介事業者が建設現場業務の職業に求職者を紹介することも職業安定法により制限されており、工事会社は人材エージェントなどを使って職人を採用することができません。つまり、大工や電気工などの職人を獲得する手段が事実上、ハローワークか縁故、新卒採用に限られており、経営者は非常に不利な条件下で採用活動を強いられているわけです。
『キツイ仕事というイメージが原因で若者の就業者が減っている』と誤解されがちですが、新規学卒者の建設業への入職者数は少子化にも関わらず、近年では4万人台を維持しており、減っていません。入職者が変わらない一方で、建設業就業者の6人に1人は65歳以上と高齢化が進み、引退による離職者が増加しているため、業界全体の就業者が減っているのです。ちなみに減っているのは4名以下の事業者勤務者と一人親方であり、5名以上の事業所の就業者はあまり減っていません。
地方と都市間の二極化も進んでいます。大手の工事会社が積極的に地方の工業高校、高専に募集をかけており、地方の高校を卒業後に東京・大阪・名古屋の大手企業に就職する人の割合も高いです。加えて業界内で転職を機に地方から都市部の大企業に入る人も多く、その結果、過去10年間で100名以上の工事会社の就業者は13万人増えた一方、29人以下の中小企業は19万人減っています」(高木氏)
優良企業では管理職年収700万円レベルは一般的
「建設業界は低賃金」というイメージも世間の誤解だと高木氏はいう。
「上下のレンジが広いとはいえ、国税庁『民間給与実態統計調査結果』によれば、建設業の平均給与は全産業平均より高くなっており、大手企業や、先ほど申し上げた2割の優良企業では管理職年収700万円レベルは一般的になってきます。そのため、現在では地銀や地方公務員、介護職からの転職も増えています。また、今では工業高校の求人倍率は10倍以上、高専は20倍以上と高い水準になっていますが、建設業界は技術と専門性が求められる世界なので、多くの工業高校・高専卒業者が大手の工事会社や優良企業に就職して、大卒者並みの給与を得ています。他方で、製造業では大手企業の正社員が半数を超えるのに対し、建設業は資本金1,000万円以下の小規模企業(家族経営の会社など)で勤務する人が就業者の4割もいます。この4割の人の給与水準が上がっていないことが課題です。また、業界努力で死傷労災件数もピーク時から9割近く減っています」(高木氏)
もっとも、転職を考える上では建設業に向いている人とそうではない人がいる点には留意したほうがよいという。
「理系社会・資格社会なので工業高校・高専・大学でエンジニアリングを勉強していたような人は歓迎される一方、普通科、文系大学卒の人はかなり勉強する必要があるでしょう。また、夏は暑く冬は寒い屋外での力作業が主になるのでハードな仕事であることは事実であり、体育会系文化が根強く、荒っぽいタイプの人も少なくないので、そうした人々と仲良くなれるメンタリティーも必要になってくるでしょう。そういう負けん気が強く、かつ専門性を持っていれば頑張るほど稼げる世界なので、夢がある業界だといえるでしょう」(高木氏)
(文=Business Journal編集部、協力=高木健次/クラフトバンク総研所長)