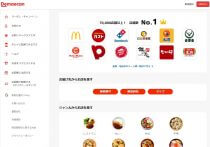「帝人」の高度なケミカルリサイクル事業、世界経済全体の環境対策で重要度高まる

現在、環境や半導体生産など世界経済の先端分野で、日本企業が生産する高機能、高純度の素材への需要が一段と高まっている。その基礎になっているのは、日本企業が磨いてきた“モノづくりの力”の強さだ。その一つの例として、繊維分野における帝人のケミカルリサイクル事業の展開がある。
同社は世界市場のニーズに呼応して、ケミカルリサイクル分野での取り組みを強化している。その目的は、世界的に問題が深刻化しているマイクロプラスチック汚染対策などの需要を取り込むことにある。そのために、帝人は異業種との連携を進め、自社のモノづくりの力がより良く発揮される体制を目指している。
見方を変えれば、帝人は、自社の祖業である繊維分野のモノづくりの力にさらなる磨きをかけることによって、長期の視点での成長を実現したい。世界経済全体で環境対策への取り組みが進む中、同社のケミカルリサイクル事業がどのように競争力を発揮するか、より多くの注目が集まるだろう。
日本繊維・素材産業の競争力を支える帝人
帝人は、東レなどと並び、繊維分野における日本のモノづくりの強さを象徴する企業だ。その強さは、手触り、着心地、耐久性、軽量化、微細さ、環境負荷の軽減など、人々、企業、社会の多様なニーズを満たす繊維製品を生み出すことにある。
それは、日本繊維産業だけでなく、第2次世界大戦後の日本経済の復興などに大きな影響を与えた。第2次世界大戦後の日本経済の復興にとって、繊維産業が果たした役割は大きかった。なぜなら、当時の世界経済、特にアジア経済では、工業化の初期段階が進んだ繊維産業を有する国は、日本が唯一の状況だったからだ。1950年頃、日本の輸出の約半分が繊維製品だった。その後、韓国、中国、台湾などの工業化が進展し、繊維製品の生産は日本からアジア新興国地域にシフトした。
そうした変化に伴って、日本では繊維製品の輸出によって得られた資源が重工業分野に再配分された。経済環境が変化するなかで、もともとレーヨンなどの生産を行っていた帝人は、代表的な化学繊維であるポリエステルの生産技術を海外から導入し、成長を実現した。さらに、高度経済成長期に帝人は積極的に海外進出を強化して、化学繊維メーカーとしてのさらなる成長を追求した。それは、第2次世界大戦後の日本経済が、軽工業から徐々に石油化学など重工業へとシフトしたことと符合する。
しかし、1973年の第1次石油ショックの発生によって事業拡大を重視した事業戦略は行き詰まり、同社の成長のペースは鈍化した。その後、帝人は、化学繊維の生産で培った技術を生かして航空機向けの炭素繊維など産業用素材や医療分野での事業運営に取り組み、今日に至る。
現在、多くの株式投資家は、帝人を産業用の高機能素材と医療分野に注力する企業とみなしているようだ。そのため、直近の決算説明会では、コロナショックの発生による航空機需要の減少が炭素繊維事業の収益に与える影響や、医療分野での成長戦略に関する質問が多くなされた。
新しい成長分野として注目されるケミカルリサイクル事業
それに加えて、帝人はケミカルリサイクル事業にも取り組んできた。長めの目線で考えると、ケミカルリサイクル事業は帝人にとっての新しい成長事業になる可能性がある。
ケミカルリサイクルとは、化学繊維などを再生し、新しい原料として利用することをいう。2002年に帝人は、世界に先駆けてケミカルリサイクル事業をスタートさせ、廃棄された繊維製品からポリエステル繊維を再生してきた。それは、プラスチック製品が海洋など自然環境に与える影響を軽減し、より循環的かつ持続的な事業の運営を目指す取組みだ。日本からアジア新興国に繊維製品の生産地がシフトした後も、同社は繊維分野でのモノづくりの力をひたむきに磨いてきたといえる。
注目したいのが、2021年4月に帝人が、繊維分野に強みを持つ総合商社の伊藤忠商事とプラント大手の日揮ホールディングス(日揮)とポリエステルのリサイクル技術のライセンス事業に向けた協議書を締結したことだ。帝人にとってその意義は、今後の事業運営の効率性を高めることにある。
まず、帝人のケミカルリサイクル事業を取り巻く世界経済の環境は追い風の状況にある。現在の世界経済では、自然環境や人々の健康のためにマイクロプラスチックの排出対策が強化されている。一例として、伊グッチなど世界的な高級ブランドがリサイクルプラスチックを素材として重視している。そうした企業の増加は、帝人のケミカルリサイクル事業の成長機会の増加を意味する。
その一方で、米中の対立やコロナショックの発生によって、世界経済の環境変化のスピードが一段と増している。そうした激動の時代に対応するためには、個社の取り組みだけでなく、他社の強みを取り込むことが欠かせない。そのために、帝人は、世界のヒト、モノ、カネの動きをいち早くとらえ、それを結合することによって成長してきた総合商社、世界のエネルギー利用などを支えてきた日本のプラント技術と自社のモノづくりの力を結びつけることによって、ケミカルリサイクル事業の成長力を高めようとしている。
帝人が目指す繊維分野でのイノベーション
現時点で、帝人、伊藤忠商事、および日揮の共同事業に関して、具体的な内容は公開されていない。一つのシナリオとして考えられるのは中国など環境分野での取り組みを進めている国や地域において、3社が現地の企業とも連携することによって、合弁事業を運営する展開だ。
そのために帝人が取り組むべきことは、国内の生産の現場で培われてきた繊維生産の技術にさらなる磨きをかけることだ。そう考える理由は、第2次世界大戦後の帝人の成長が示す通り、同社の繊維生産技術は海外の企業に容易に模倣できないからである。
それは、現在の日本産業全体の収益獲得の状況からも確認できる。半導体の部材をはじめとする素材分野、製造装置、精密機械、自動車などの分野で日本の企業は世界の需要を取り込んでいる。原材料の生産やその調合、さらには部品と部品の精緻なすり合わせに関して、日本企業が比較優位性を持っているからに他ならない。そうしたモノづくりを支える現場の力を伸ばし、さらなる磨きをかけることが、帝人をはじめ日本の繊維や素材関連の企業の成長には欠かせない。
そう考えると、帝人が今回の協議書締結に込めた真意がわかる気がする。帝人の経営陣は、自社の技術をより積極的に世界に発信し、需要を取り込みたい。ただし、情報の獲得や事業機会の模索、政策当局との交渉などに関しては、総合商社に強みがある。また、プラントの設計、建設、運営は、自社で取り組むよりも専門家に任せたほうがよい。
そうした他社の強みを活用することは、帝人が、国内の生産拠点や研究所において、より集中して繊維関連の生産技術の開発に取り組み、イノベーションの発揮を目指すために欠かせない。そう考えると、帝人の成長戦略の基礎は、国内の生産拠点や研究所にて新しい繊維の創出により集中して取り組む組織体制を整えることだといえる。それは、同社だけでなく、マイクロプラスチックの排出削減など先端分野での日本企業の競争力発揮にも無視できない影響を与えるだろう。
(文=真壁昭夫/法政大学大学院教授)