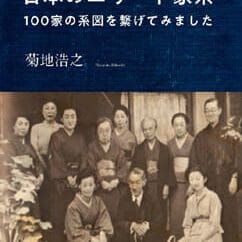『青天を衝け』幕閣たちの異例人事と実力主義…農民・渋沢栄一が大出世した幕末の大混乱

老中は外様小藩と旗本からの大抜擢
NHK大河ドラマ『青天を衝け』には、しばしば江戸幕府老中(or大老)が出てくる。阿部正弘、井伊直弼あたりは有名だが、第19回(6月20日放送)に出てきた松前崇広(まつまえ・たかひろ)や阿部正外(まさとう)となると、よほどのマニアでもなければ知らないだろう。
松前崇広は蝦夷(えぞ/北海道)福山藩(俗称・松前藩)3万石の外様大名である。外様大名が老中に任ぜられるのは珍しく、父親が譜代大名だった例(松平定信の子・真田幸貫:ゆきつら)などがあるくらいで、純粋な外様大名の子が老中になったのは、崇広が初めてだろう。
福山藩は北海道の最南端(現:北海道松前郡松前町)に位置し、外国船が行き交う土地柄だったので、崇広は国防の危機を感じて城を改築し、洋式砲術を奨励。そんなところが幕閣に評価されて、文久3(1863)年に寺社奉行、翌元治元年7月に海陸軍総奉行兼老中格、同年11月に老中に登用された。西洋かぶれで、江戸城登城の際にも太刀は持たず、短刀とピストルを身につけていたという。
もうひとりの阿部正外は、その名が示す通り、阿部正弘の遠縁にあたる。阿部家は正弘の家が本家筋で、分家の大名が2つあり、そのうちのひとつに正弘の甥っ子が養子に行き、正外はその養子に当たるのだ。正外はもともと3000石の旗本に生まれ、文久元(1861)年に神奈川奉行、翌文久2年に外国奉行、文久3年に町奉行と昇進を重ねた。
神奈川奉行在任時は、生麦事件を起こした島津久光を箱根で止めようとして老中らを慌てさせ、町奉行在任時には攘夷に反対して将軍に辞職を勧告した無骨者。その手腕が認められて元治元(1864)年3月に陸奥白河藩10万石の家督を継ぎ、その3カ月後に老中に任ぜられた。幕末には有能な旗本を大名の養子にして、幕閣に登用する事例が散見されたのである。
松前崇広は外様小藩、阿部正外は実質的な旗本抜擢。いずれも平時ではあり得なかった老中人事であり、そこまで幕府は切羽詰まっていたのだろう。なお、『青天を衝け』第21回(7月4日放送)にちらっと登場した老中・小笠原長行(ながみち)は藩主世子(家督相続せずに老中)、若年寄の立花種恭(たねゆき)は外様小藩の出身である。


勘定奉行は名門出身だが、外国奉行は医師あがり
『青天を衝け』第22回(7月11日放送)、渋沢篤太夫(渋沢栄一/演:吉沢亮)は幕府使節団の一員としてついにパリに旅立つ。それもあって、老中・若年寄以下の勘定奉行や外国奉行などの面々、さらに使節団に赴く幕臣が描かれる。
まずは勘定奉行や外国奉行など、使節団を見送る側だ。
小栗上野介忠順(おぐり・こうずけのすけ・ただまさ/演:武田真治)は、家康以前から徳川(旧姓・松平)家に仕える三河武士の子孫で、2500石の名門旗本に生まれた。
安政6(1859)年に目付(外国掛)として遣米使節に加わった(乗った船は咸臨丸。勝海舟・福沢諭吉・中浜万次郎等が同乗した)。帰国後、外国奉行に就任。文久元(1861)年4月にロシアが対馬を侵略し、その対外交渉のために対馬に派遣されたが、不首尾に終わり、外国奉行を罷免される。
ちなみにこの時に同行したのが溝口勝如(みぞぐち・かつゆき)である……誰それ? 第20回(6月27日放送)に篤太夫が新撰組の土方歳三(演:町田啓太)と大沢源次郎を捕縛に行ったのを覚えておられるだろうか。では、それを命じた人物は? それが陸軍奉行の溝口なのである。溝口は明治維新後の徳川宗家の家令(執事)になっている。おそらく、帰国した篤太夫が静岡の徳川家を訪れ「あー。あの時の!」という伏線として、わざわざ登場させているのだろう。
その後、小栗は勘定奉行に任ぜられ、町奉行・歩兵奉行を兼務。勘定奉行を免職され、陸軍奉行並。勘定奉行に再任。免職して軍艦奉行並。さらに勘定奉行に再任され、海軍奉行並・陸軍奉行並を兼務という。わずか5年の間に3回勘定奉行に就任している。よほど余人をもって代えがたい人材だったのだろう。
小栗とセットで登場する、外国奉行・栗本鋤雲(じょうん/演:池内万作)。普通、幕閣の人物って「✕✕守(~のかみ)」とか訓読みの名前で出てくるものだが、この人物だけなぜか音読みで坊さんみたいだ。実はこの御仁、純粋な武士ではなく、医者あがりなのだ。
栗本鋤雲は幕医の家に生まれたのだが、蘭学に興味を持ったため、上役の医師に嫌われ、安政5(1858)年に箱館(函館)に飛ばされた。箱館は安政元(1854)年に開港したばかりで、まだまだ未開の地だったらしい。栗本は山野の開拓、薬草園の経営、鉱物資源の調査、牧畜・養蚕実験、医学所の開設に尽力。文久2(1862)年にその功績によって医籍から士分に取り立てられ、江戸に戻って学問所頭取、目付、軍艦奉行並とスルスルと昇進。慶応元(1865)年11月に外国奉行に登用された。この時の名前は栗本安芸守鯤(あきのかみ・こん)。鋤雲はのちの名前である。やっぱり「✕✕守」って名前だったんだね。
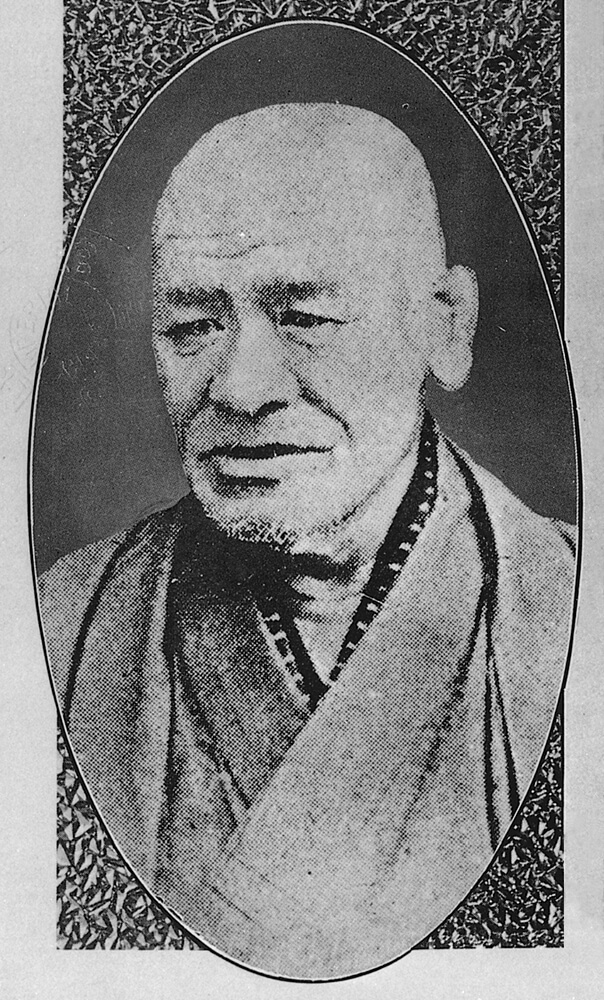

ここにも外国奉行とその親族
そして、使節団に赴く幕臣である。
向山英五郎一履(むこうやま・えいごろう・かずふみ/演:岡森諦)は旗本300俵・一色(いっしき)家に生まれ、旗本100俵・向山家の養子となった。満23歳で昌平坂(しょうへいざか)学問所教授方出役(いまでいう東京大学非常勤講師)を務めたほど成績優秀だった。
安政2(1855)年に養父が箱館奉行支配組頭に就任したため、付き随って箱館に渡り、翌年に養父が死去したため、箱館奉行支配調役に着任。安政5(1858)年12月に箱館奉行支配組頭となった。この年に栗本鋤雲が箱館に飛ばされたので、おそらく両者は顔馴染みだっただろう。
向山は栗本より先に江戸に戻り、奥右筆、外国奉行支配組頭に就任。栗本と同時期に目付に就任。やっとここで両者が邂逅し、次いで、慶応2(1866)年10月に外国奉行に就任、栗本と再び肩を並べた(すみません。書いておりませんでしたが、外国奉行は複数名着任です。また、この時2000石に大幅加増されている)。
翌慶応3年1月、フランス派遣にともない勘定奉行格、同年8月に在フランスのまま若年寄格に昇進。帰国後(慶応4年3月)に若年寄に登用されている。若年寄は譜代大名が務めるポストなので破格の昇進で、これも幕末人事だといえよう。
なお、向山の婿養子・向山慎吉は明治維新後に海軍中将に昇進、日露戦争の功績で男爵となったが、後妻に山高信離の長女を迎えている。
その山高石見守信離(やまたか・いわみのかみ・のぶあきら/演:山本浩司)は旗本2500石・堀家に生まれ、1800石の旗本・山高家の養子となった。信離自身は中奥番、小納戸、目付といった従来型の旗本人事を歩んでいったが、実兄の堀利煕(ほり・としひろ)は外国奉行・神奈川奉行・箱館奉行を歴任、甥の堀利孟(としたけ)も神奈川奉行・軍艦奉行を歴任。毛並みとしては申し分ないということで、幕府使節団の団長を務めた清水徳川家第6代・徳川昭武(演:板垣李光人)の傅役(もりやく)を任されたのだろう。使節団にあっては残念な役回りだったようだが、有能な人物だったらしく、子の林曄(はやし・はじめ)が林家(儒学者・林羅山の子孫)の養子になっている。
幕府の人事といえば、前例踏襲・家柄重視みたいに思われるかもしれないが、幕末になるとそんなことにこだわってはいられなくなっていく。だから、渋沢篤太夫(栄一)みたいな農民出身者でも受けいれられたのだろう。
(文=菊地浩之)