在宅勤務が定着、食品消費への意識はどう変化?メーカー側はオンラインで“接点”増やす
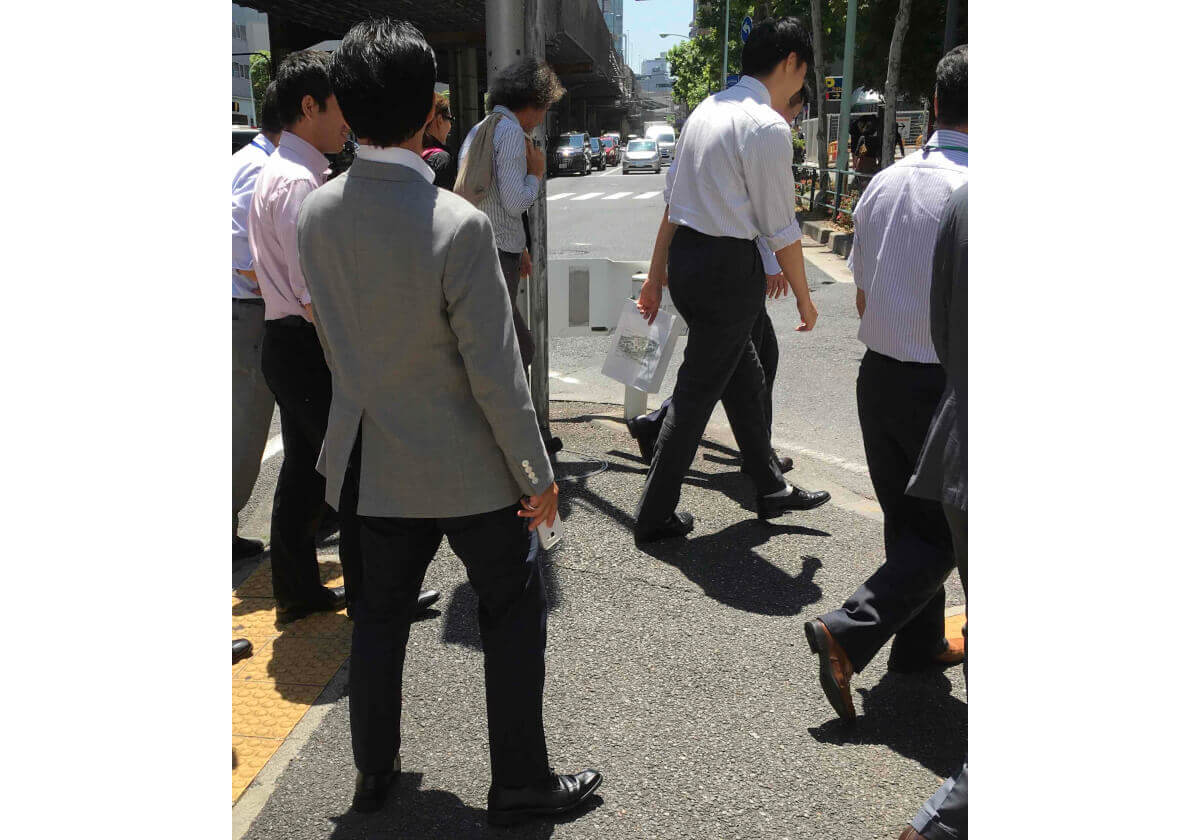
依然として、コロナ禍での仕事が続く。業種や職種によって違うが、総じて在宅勤務が進み、業務の状況次第で「出社するのは週(または月)に〇日」という人が多いだろう。
消費活動も大きく変わった。当時も現在もメディアでは「コロナで売れた商品・売れなくなった商品」を紹介している。外出用の衣服や装身具の購入減、(マスクで口を覆う機会が増え)口紅や化粧品の需要減などが知られるが、家庭内の消費活動も様変わりした。
今回は、そのなかで「在宅勤務時の食品」に焦点を当てたい。何を買うかではなく、各方面の取材を基に、コロナ前の通勤時代とは異なる在宅時間増加での消費者心理を考えてみた。ここまで長く在宅勤務が続くと、単なる「巣ごもり」では見えてこない消費者の行動が目立ってきたからだ。
合わせて、メーカー側の訴求も事例で紹介したい。厳しいご時世の消費者コミュニケーションの参考になれば幸いだ。
この2年で進んだ、食品消費の3つの意識
まずは2020年からの在宅勤務で目立つようになった食品消費への意識を紹介しよう。
(1)調理機会が増えて「時短」を重視
(2)通勤減で「健康志向」がより高まる
(3)これまでとは違う「ストレス」を感じる
それぞれ簡単に説明したい。
(1)は、自宅近くの飲食店にも行きにくいご時世で、社会人も在宅での食事機会が増加した。そうなると、自炊では誕生日や記念日など特別な日でない限り、通常の食事はパパッと簡単な調理を目指すようになる。
食材ではパスタ類も売れたが、これは調味ソースを変えれば週に複数回出しても飽きない一面もある。さらに目立ってきたのが市販の食品を調理に応用する例だ。
たとえば、カレーをつくる際、ルーに「野菜飲料」を加える。野菜を洗う・剥く・切ることに比べると調理時間を短縮できるからだ。市販の飲料は容器に原材料名が明記されているので、栄養成分もイメージできる。
「在宅勤務が中心となって消費者の健康意識が高まり、野菜飲料を野菜摂取だけでなく“栄養摂取”や“保存性”、それに“衛生面”の観点で選ばれる方が増えています」
野菜飲料の大手メーカーであるカゴメは、こう話す。ここでいう衛生面とは、生の野菜を洗って使うことに比べて管理された工場で生産された商品への安心感もあるようだ。
「料理レシピ」で訴求するメーカーも増加
同社を含めて、メーカーが自社商品を使ったレシピを打ち出す例が増えた。コロナ以前から行う活動もあるが、在宅を意識してより進化している。
たとえば「カゴメのレシピ」として同社が行うのは、以下の訴求だ。
これには原材料の野菜系を使ったメニューもあれば、季節を意識した冷製トマトスパゲティなどもあり、「調理時間が短い順」「カロリーが低い順」などの検索もできる。
菓子メーカーのカンロは、「カンロ飴食堂」というオンライン“食堂”で訴求する。世話好きで料理上手な女将がやっているという設定にもこだわった。
看板商品の「カンロ飴」は、原材料が「砂糖・水飴・しょうゆ・食塩」でできている。「飴にする過程において高温で加熱するため、特有の香りやおいしさが生まれていること。水飴により料理にテリが生まれやすいという特徴があります」(同社)。その特徴を調理でも生かすという訴求だ。外出自粛で行楽需要が減った飴菓子の、別の魅力も打ち出した。
カンロ飴を使った「炊き込みご飯」「じゃがいものカンロバター煮」などのレシピのほか、アウトドア人気を反映したキャンプ飯のメニューも紹介されている。
カゴメもカンロも「調理時間」つきで、“時短”を意識した訴求も目立つ。

清涼飲料は避糖化、ノンアルも人気
(2)は、通勤が減り運動不足が気になる人も増えた。運動代謝ができない分、栄養代謝を意識し、バランスの取れた飲食を心がける人も目立つ。
清涼飲料市場では数年前から「無糖飲料の構成比が5割弱(2018年は約49%)」(全国清涼飲料連合会調べ)と半数が無糖になった。「消費者は有糖の飲料も楽しみますが、全体的な傾向としては“避糖化”の傾向が強まっています」と、サントリー食品の担当者は話す。
「ウチの夫は、風呂上がりに(無糖の)炭酸水を飲む機会が増えました。炭酸飲料でスッキリしたいけれど、糖分摂取が気になるようです」(30代の女性会社員)
通勤で歩く機会も減った現在、こんな声に象徴されるのだろう。
在宅時間が長くなり、清涼飲料では2リットルや1リットルという大容量が売れている。盛夏の時季は、さらにその傾向が強まりそうだ。
また、ビール類ではなくノンアルコールを好む人も増えた。これも健康意識の高まりと関係する。
アサヒビールの調査(2021年2月)でも顕著だ。「特に20代、30代の若年層は、度数の低いアルコールを求める声が他の世代よりも高く、少し酔いたい時はローアルコール・ノンアルコールを求めている」と解説する。同社はアルコール度数0%のノンアル「アサヒ ドライゼロ」や同0.5%の微アルコール「アサヒ ビアリー」などで積極訴求を行う。

空きペットボトルの「ラベル剥がし」がストレス
(3)の「ストレス」には、いろんな意識がある。
最近よく聞くのが、ペットボトル飲料の空きボトルを捨てる際、「ラベルを剥がすのが面倒」という声だ。
コロナ以前、平日に通勤する時代は社内や自販機横のゴミ箱に捨てていて気にならなったが、在宅勤務が中心となりペットボトル飲料の自宅消費も増えた。容器によって剥がし方が違い、うまく剥がれない時もある。
マーケティングや商品開発の現場では、「消費者の障壁を取り除く」という共通認識がある。この場合の「障壁」は物理的や心理的な抵抗感を指す。「その程度はガマンしろ」と思うか、その障壁を「取り除こう」と考えるかは、感性や意識の問題だ。
これに目をつけたメーカーはラベル面積を減らしたり、ラベルレスの容器を発売したりした結果、消費者に支持された。
観光に行けない思いを「気分」の商品で訴求
2021年7月12日から東京都では4度目の緊急事態宣言が発令され、2年続けて夏休み中の観光旅行需要にブレーキがかかった。そうなると消費者が行う行為のひとつに「観光気分の食品購入」がある。その需要も取り込んだ事例がある。
北海道のコンビニとして、独自の取り組みで注目される「セイコーマート」。同社グループが近年、力を入れるのが、自社PB(プライベートブランド)商品「セコマ(Secoma)」だ。2016年に社名を変え、PBも順次この名前に変えた。セイコーマートでは約3500種類の商品を扱い、約1000種類がセコマオリジナル商品だという。
セコマのアイスは、早くから「北海道」にこだわってきた。店舗は北海道中心だが、本州のスーパーには幅広く供給し、ドラッグストアは「ウエルシア」に供給している。
「たとえば『北海道メロンソフト』は、道産の赤肉メロンを使い、2006年に発売。当初はメロン果汁1トンからのスタートでしたが、現在は100トン以上に拡大しています」(同社)
こだわるのは、メロンのおいしさに加えてミルクのおいしさだ。「北海道クリーミーソフト」なども人気で、喫食者は「道内旅行で食べたソフトクリームのよう」と話していた。
2020年からは、セコマの牛乳やヨーグルトも伸びた。「リモートワークの親御さんも、学校に通えなかったお子さんも、しっかりと栄養を摂るため、乳製品の優れた栄養バランスが再注目されたのではないか」と、同社は分析する。


通常の販促ができなければ「接点」を増やす
日常消費する食品は、小売店での購入が一般的だ。送り手側も実店舗での販促に力を入れるが、コロナ禍では小売り店頭で販売員を立てるような試飲・試食はやりにくい。
メーカーの現場では「消費者との接点(タッチポイント)を増やす」という言い方をする。これまでの接点=店頭訴求が制限されれば、別の接点をつくり訴求する。在宅勤務が多い消費者はスマホ画面を見る機会も多くなり、オンラインでの訴求は有効な手法だ。
今回紹介した事例は「生活者インサイト」(洞察や本質を見抜く)という活動だ。昔から「不満あるところにビジネスあり」とも言われる。
在宅生活が長引くほど、調理回数増や旅行自粛などさまざまな不満が顕在化する。それをどう「心地よい思い」に変えて消費につなげるか。各社の腕の見せ所だろう。
(文=高井尚之/経済ジャーナリスト・経営コンサルタント)












