偽装カルテルまでしてディーゼル車を延命の裏に自動車の「不都合な真実」
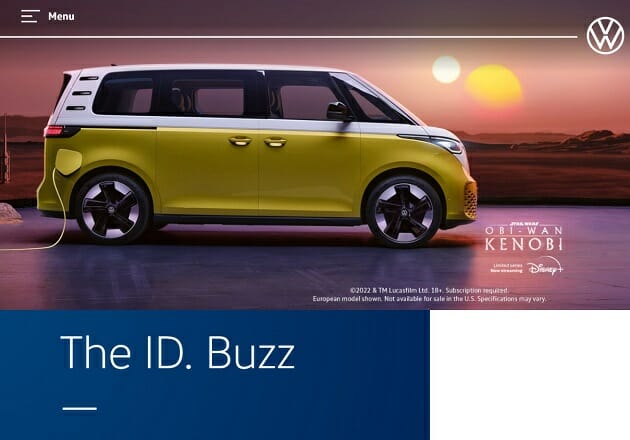
2015年に米国から始まったディーゼルエンジンの排ガスをめぐるトラブルは米国、欧州をめぐり、とうとう日本にも上陸。日野自動車は3モデルのトラックの型式認定を取り消され、生産できない状態に追い込まれた。一方、主要な欧州メーカーはすでに対策を打ち、問題を解決しつつある。何をどう解決したのか。それともEVシフトの大潮流のなかでディーゼル車は絶滅するのだろうか。真相を追ってみたい。
排ガス偽装カルテル事件
排ガス偽装事件の闇は深く、排ガス浄化技術に関するカルテルへと及んだ。フォルクスワーゲン(VW)と傘下のポルシェ、アウディに加えてBMW、ダイムラー・ベンツ(当時)と、ほとんどのドイツのメーカーが排ガス浄化システムについてカルテルを結び、談合をしていたことが当局の調査で明らかになったのである。
カルテルは、上記のメーカーで結託して排ガス浄化技術の利用を控えようというものだった。彼らはエンジンと排ガスの浄化装置の改良でEUのディーゼル排ガスの規定値をクリアしていたが、それ以上の浄化技術の使用を控え、過剰な技術開発を止めようと談合していたのだった。とんでもない話である。
排ガス偽装が米国で明らかになった2015年頃のパリの大気汚染はひどかった。数キロメートルも離れると、あの大きなエッフェル塔がかすむほどであった。自動車の排ガスによる健康被害は拡大していた。
こうした状況のなかで上記のカルテルに対して、EUの委員会は計8億7500万ユーロ(1146億円)の罰金を科した。ただし、ダイムラー・ベンツはカルテルの存在をEU委員会に明かしたということで制裁を免れた。
なぜ、そこまでして偽装したのか
簡約すれば、ディーゼル車はよく売れる商品で手放せなかったということに尽きる。欧州のメーカーにとっては主力商品であり、ドル箱であった。しかし、環境規制が彼らの背中に忍び寄っていた。
クリアしたとはいえ、新たな二酸化炭素(CO2)排ガス規制であるユーロ6は厳しく、尿素SCRと呼ばれるシステムを使う必要があった。これはコスト面でも、装置を取り付けるスペース面でも、負荷が大きかった。後述するように、たとえば小型のディーゼル車ではコストがかかり販売価格が高まり、また大きな装置の搭載は困難であった。可能であれば、こうした装置は取り付けたくなかったというのが自動車メーカーの本音だろう。
二律背反の排ガス対策
ディーゼルは燃費の良さと低速で力が強いことが大きなメリットであった。燃費が良いとは少ない燃料でよく走るということだから、排出されるCO2も少なく、地球温暖化・気候変動には好ましいエンジンであった。だが、それは排ガスによる大気汚染が明らかになるまでの話だった。
実際は自動車排ガスによる大気汚染はモータリゼーションの進展していた米国で戦前から問題になっており、CO2による地球温暖化は1985年の世界会議(フィラハ会議)で問題になり、90年代に入るとこれらは同時に解決すべき問題となった。
ところが、この2つは二律背反する問題だった。少し複雑だが、ディーゼルエンジンもガソリンエンジンも、燃費を良くしてCO2を減らすと排ガスが増えてしまうのである。
PMを減らすとNOxが増える
燃費を良くするには、燃料をなるべく高温で素早く燃やす必要があるが、こうすると空気中の窒素が反応し窒素酸化物のNOxが増えてしまう。窒素は非常に反応しにくい物質だが、エンジンの中では窒素でさえも反応させてしまう高温となり、燃焼温度が高いほど効率が良く、燃費も良くなる。しかし、それだけNOxも増える。そして、このことが顕著なのがディーゼルエンジンなのである。
一方、もうひとつの大気汚染物質である粒子状物質のPMは高温で燃やすほどに少なくなる。NOxを減らそうと低い温度で燃やすと、逆に燃え残りのガスが増え、PMも増加する。NOxを減らせばPMが増え、PMを減らせばNOxが増えるのだ。
ディーゼルを手放せなかった燃費規制
ディーゼル車を手放せなかったもうひとつの理由がある。地球温暖化・気候変動をもたらすCO2の排出規制だ。いわゆる燃費規制である。EUは世界に先駆けて自動車のCO2排出規制を強めた。すでに実施されている2021年規制値は、95グラム/1キロメートルだ。1キロメートル走った時のCO2排出量を95グラム以下にしなさいというもので、実燃費に換算するとリッター24.4キロメートルとなる。
しかもメーカーが販売した自動車の平均値だから、達成するにはすべてのモデルの原動機はもちろん、車体も含めた大幅な見直しが必要だ。
4500億円の罰金
さらに罰金額がすごい。1グラムオーバーしただけで1台当たり95ユーロ(1万2700円)の罰金だ。VWのようにEUで350万台近く販売するメーカーだと、年間の罰金は450億円となる。10グラムもオーバーしてしまうと4500億円だ。そして1台当たりの罰金による販売価格の上乗せ額は12万7000円となる。そうなれば競争力はゼロで、ブランドイメージはマイナスである。1グラムでも減らせという命令が開発部門に下ったとしてもおかしくない。
規制をクリアするには、ガソリン車よりも燃費の良いディーゼル車のほうが都合がよかった。ディーゼル車はガソリン車にくらべて燃費が良く、CO2排出量は3%ほど少ない。だが、たかが3%少ないだけでメーカー全体のCO2排出量を減らすには、ディーゼル車を大量に販売する必要があった。しかし、排ガスのうちNOxとPMに関しては、とてもガソリン車のクリーン度には及ばず、排ガス規制をクリアするのは困難だった。ここに排ガス偽装の種がまかれた。
日本車にはハイブリッド技術があった
ディーゼルに替わる解決策はガソリンハイブリッドであった。21世紀直前にこの技術を完成させていたトヨタ自動車とホンダは、ハイブリッドで欧州マーケットに打って出た。迎え撃つ欧州勢は、ディーゼルで応えるしかなかった。欧州メーカーには、「悔しいハイブリッド」だったに違いなかった。
ハイブリッドは、特にトヨタのそれは日本のお家芸である組み合わせ調整型の技術の最たるものである。デジタル技術をアナログ的に使うので阿吽の呼吸を必要とする。欧米が苦手とする技術だ。
欧州勢はディーゼルを諦めると、ハイブリッドも諦めて、一気にEVにシフトした。そして返す刀で、自動車のゼロ・エミッション化を掲げ、ハイブリッドでもクリアできない排ガスとCO2の厳しい規制に打って出た。自動車の大革命の始まりである。
結論は
排ガス偽装の背景を追うと、欧州の自動車メーカーの苦しい台所事情が見えてくる。しかし、排ガスだけではなくCO2もゼロにして地球温暖・気候変動を止められる自動車でなければ21世紀に生き残れない。
だからといって水素燃料車やバイオ燃料車に勝ち目があるかというと、EVは30年には21年の7.6倍の3544万台になるというから(英LMCオートモーティブ)、とても勝ち目はない。ついてこられないメーカーを置き去りにして、流れは一気にEVにシフトしたのである。ディーゼルにこだわる時代は終わった。
売れるからとディーゼルにこだわったことで、欧州のメーカーは手痛い目にあった。一方、一瞬は欧州勢に勝ったかに見えた日本のハイブリッドも、売れるからとこだわったがゆえにEVシフトに乗り遅れている。資本主義時代の技術には日々の革新が求められる。昨日の技術にこだわると「イノベーションのジレンマ」(クレイトン・クリステンセン)に陥り、それまでの成功を捨てることになる。排ガスもCO2もゼロでなければ自動車は生き残れないのだ。








