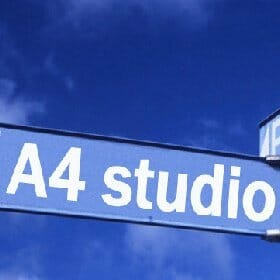JASRAC徴収額が過去2番目の高さ、「儲けすぎ」批判は的外れ?

日本の音楽著作物の利用を管理する一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)。イベントやビジネスで音楽著作物を利用する際には大半の場合、JASRACに著作権使用料を支払う必要があるが、その強硬的な徴収の態度に批判の声が上がることもたびたびあった。特に2017年に、JASRACが音楽教室からも著作物使用料を徴収する方針を示したことは議論を呼んだ。
そんなJASRAC、今年5月18日に21年度の音楽著作物使用料徴収額が1167億3000万円、分配額が1159億7000万円を突破したと発表。新型コロナウイルスの影響でイベントの開催やカラオケボックスの利用が激減したのにもかかわらず、過去2番目の徴収額であったという。
この発表を受けてネット上では、「徴収額が増えて音楽業界が盛り上がっているのは嬉しいけどJASRACにお金が入るのはもやもやする」「人の著作物で儲けすぎではないか?」と内心複雑に思う人々の声が見受けられた。
いったい、今回の徴収額増加をどのように評価するべきなのか。そこで著作権・エンタメ法務に詳しい弁護士であり、自らも音楽家として活動する高木啓成氏に、JASRACの徴収額増加の背景について詳しく伺った。
インタラクティブ配信の徴収額増加、サブスク浸透の影響か
まず、徴収額が増えた要因としてインタラクティブ配信(インターネットによる利用)の増加があげられるという。
「19年度から21年度のインタラクティブ配信の分配実績額を確認すると、19年度の201.9億円から21年度には356.2億円まで上がっています。たしかにライブやコンサート、フェスといった大規模演奏会などによる分配額は下がってはいるものの、インタラクティブ配信の徴収額に比べれば微々たる差なのです。
特にSpotifyやApple Musicなどのサブスクリプションサービスや、NetflixやYouTubeなどの動画サービス市場の拡大が今回の徴収額増加につながったのはいうまでもないでしょう。コロナ禍によりミュージシャンやアイドルがライブ配信をすることも多くなりましたし、徴収額増加は当然かと思いますね。
実際に作家(作曲家・作詞家)や音楽出版社は、インタラクティブ配信による収益が増えなければ事業が成り立たなくなりつつあります。インタラクティブ配信の隆盛に比べると、CDの徴収額はここ5年において売上が横ばいであるものの、90年代をピークに減少しているのが現状です。貸レコードに至っては10年前に比べて3分の1以下の売上となってしまっています。
半面、インターネット上での音楽利用が増加の一途を辿っているのは先ほど申し上げたとおりです。インタラクティブ配信は従来の貸レコード、貸ビデオに代わる役割を持っているので、権利者側(作家、音楽出版社)がインタラクティブ配信で多くの徴収を望んでいるのは自然といえるでしょう」(高木氏)
作家や音楽出版社は、むしろJASRACによる著作権使用料の徴収を望んでいるというわけか。
「作家や音楽出版社は、著作権使用料を正確に徴収・分配してもらうためにJASRACに著作権の管理を委託しています。音楽を使った事業を始めるスタートアップ企業なども、JASRACに対して著作権使用料の支払いを前提に事業計画を作っています。著作権使用料を支払うことは、企業人からすると通常の感覚なんです」(同)
余談だが、過去に騒動になった音楽教室からの徴収騒動についても、音楽教室は営利目的で運営しているため、特段保護する必要はないかもしれないだろう。
JASRAC一強の理由、しかし競合も現れ現状は変わりつつある
JASRACが音楽業界において、ここまで強い立ち位置につくことができたのは、制度的な理由とその歩んできた歴史によるものが大きいのだという。
「もともとJASRACは仲介業務法によって定められた音楽著作権管理事業者でした。01年に著作権等管理事業法が施行されてからは、複数の著作権管理事業者が認められ、イーライセンス、ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)などの事業者が登場したものの、JASRACの座を脅かすほどには至っていませんでした。
要因はいくつかあるのですが、ひとつはJASRACが地道な徴収活動を続けてきたという歴史が大きく影響しています。テレビやカラオケ、インタラクティブ配信などについては、各事業者との間で契約を結んで徴収するのは比較的容易なのですが、全国にあるパブやスナックなどの小規模なお店で流れる曲から徴収するのはなかなか困難ですよね。ですが、JASRACは調査員を派遣して各店の音楽利用の実情を調査し、場合によっては訴訟を起こしてまで徴収をしてきました。これは、JASRACが作家・音楽出版社側から著作権の信託譲渡を受け、法律上の著作権者となっているからできることなんです。
このように徹底して著作権使用料を徴収してきた歴史があるからこそ、作家、音楽出版社が安心して権利を預けることができるというのがJASRACの強みでしょうね」(同)
とはいえ、近年JASRACの徴収の態度が強くなってきたという指摘も、あながち間違いではないと高木氏は指摘する。
「一番の要因は競合であるNexToneの存在かと思います。NexToneは前出のイーライセンス、JRCが合併してできた株式会社であり、主に音楽著作権管理事業を行っています。
JASRACとは違って著作権の管理の委託だけを任されているので、訴訟を起こすような業務は取り扱っていません。ですが、NexToneのほうが管理手数料率を下げており、曲の使用目的によっては使用料免除も一部認めるなど事業者側への柔軟な対応が見られます。特に近年は海外の著作権管理事業者と徴収代行契約を締結し、海外での利用についても一定の分配が可能となっています。
JASRAC自身も管理手数料を下げたり、柔軟な対応を行ったりしている動きもあるので、NexToneは無視できない存在になっているのでしょう」(同)
では今後のJASRACの徴収額はどうなっていくのか。
「コロナ禍の悪影響が落ち着けば、短期的には徴収額は上がるでしょう。軒並み低調であったライブやCDリリースのイベントが行えるようになるので、若干上がりそうですね。しかし、長期的に考えると上がるかどうかは判断が難しいです。個人的にはインターネット上の音楽利用料をどれだけ徴収できるかにかかっていると考えています。
またJASRACと作家の関係性も変わってきそうです。従来は作家が音楽出版社に著作権を譲渡し、音楽出版社がJASRACに著作権を預けるという仕組みでしたが、今後はクリエイターが直接JASRACに著作権を預けるケースも増えてくるかもしれません。特にYouTubeなどのインターネット上で活動するクリエイターの方は、著作権使用料をより多く得るためにそういう形式の契約を望むことが多くなるでしょうね」(同)
インターネット上での音楽利用のニーズ増大に合わせて、JASRACに著作権使用料を支払う事業者が増えつつある現在。競合NexToneの存在も大きいだろうが、JASRACと音楽業界の関わり方は少しずつ変わっていくのかもしれない。
(取材・文=文月/A4studio)