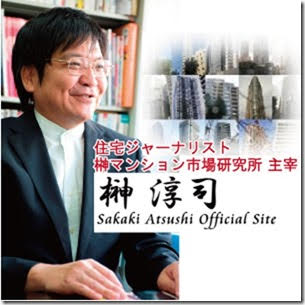「Gettyimages」より
「Gettyimages」より東京都心で土地の値上がりが止まらない。
買っているのはホテル事業者、そしてマンションデベロッパー。高くなっても、躊躇せずに買っていく業者がいるので、どんどん値上がりしているのだ。ホテルの場合、今から土地を仕込んでもオリンピック前の開業には間に合わない。東京五輪の閉幕後もインバウンドは増えるだろう、という見込みのもとに買っている。マンションデベロッパーはどうなのか。彼らの最近の事業展開はやや歪だ。
首都圏の新築マンション市場は、かなり停滞気味だ。2013年から始まった価格の高騰は、今や局地バブルエリアから都心近郊まで広がりつつある。しかし、売れ行きがそれに伴っているかというと、かなり怪しい。都心の港区や千代田区、あるいは新宿区や渋谷区といったところは新築マンションの販売価格が多少高くなっても特殊な需要が存在した。タワーマンションには相続税対策の高層階需要。あるいは2015年頃にピークだった外国人の爆買い。それに、日本国内の富裕層による値上がり期待の投資。
こういう特殊な需要に支えられて2016年いっぱいは高くなっても売れていた。ところが、国税庁の方針や、中国政府による外貨持ち出し制限などがあって2017年には相続税対策や外国人による購入はほぼ見られなくなってしまった。
2016年頃には、そういった特殊需要がほとんどなかった城南エリアでも局地バブルによる値上がりが広がった。そもそも世田谷区や品川区、大田区といったところで供給される新築マンションは「買って住む」という実需による購入がほとんどである。それも、富裕層よりも一般の中堅所得者が購入層の中心だ。
彼らの所得が都心の局地バブルによって上昇したわけではない。むしろ消費税の増税や公共料金の値上がりなどで可処分所得は減少気味。マンションの価格だけが上がっても、そこに収入は追いついていない。だから、高くなったマンションを買えない。その結果、城南エリアの新築マンションは軒並み売れ行き不振。市場を見ると、建物が完成したのに販売が続いているマンションが販売中物件の半数以上を占めるまでになった。
ところが、マンションデベロッパーたちは高くなった土地を購入せざるを得ない。なぜなら、彼らは常に開発事業を行っていないと会社としての売上は立たないし、利益も上げられない。社員の給料が払えないから会社が維持できないのだ。だから「この値段で買ったら今の相場より15%高く売り出さなければいけない」と予測できる土地でも買ってしまう。その結果、完成在庫となって値引き販売に至る。会社としてはどんどん体力が削られる。
リーマンショック後の2009年頃も同じような状態であった。だからマンションデベロッパーがバタバタと倒産した。特にマンション開発が事業のメインで、どこの企業系列にも属さない「専業独立系」と呼ばれたマンションデベロッパーは軒並み倒産に追い込まれた。社名をあげるとゼファーや日本綜合地所、ニチモ、アゼルなどだ。大京やリクルートコスモスは大手の傘下に入ることで経営を継続することができた。
現在も、新築マンションの開発事業は同様に困難な状況に追い込まれている。しかし、10年前ほど無茶な土地の仕入は行われていないし、規模も小さい。また、マンションデベロッパーは財閥や金融系列などの大手が主役になっている。あの倒産劇を生き延びた「専業独立系」のデベロッパーも混じるが、ここ数年の好景気でそれなりの体力を蓄えている様子。近いうちに倒産ということもなさそうだ。
郊外でのマンション開発、ほとんど不可能に
しかし、新築マンション市場の様相は大きく変わろうとしている。
まず、新築マンションは高くなりすぎて売れていない。それは山手線の内側である都心でも、世田谷などの城南エリアでも同様。
ところが、足元の中古マンション市場では微妙な変化が起きている。一例をあげると、2015年から2016年頃までの価格上昇期に売買契約が結ばれ、2017年以降に建物が完成した新築マンションが中古市場で大量に売り出されている。それらは新築販売時の価格から概ね2割から3割高い売り出し価格で市場に出ている。値上がり期待で買った個人投資家が売り出しているのだ。ところが、あまり売れていない。
2018年の春以降、そういった物件のなかで値引きしてでも成約を急ぐケースが見られるようになった。あるいは、値上がり益を1割程度に抑えた売り出し価格の物件も散見できる。つまり、中古マンション市場は緩やかな値下がりが始まったと推測できる。
マンション市場における中古と新築の価格差は、従来「都心では小さく、郊外に行けば行くほど広がる」というのがセオリーだった。現在、首都圏における新築マンション1戸当たりの建築費は2300万円前後である。広さは20坪前後が基準。これに土地代や販売経費、デベロッパーの利益を乗せると、販売価格は安くても4000万円前後になってしまう。
ところが、千葉市より東、旧大宮市より北のエリアでは築10年の中古マンションが2000万円程度で購入できる。そういう場所で新築だからといって4000万円でマンションを売り出しても、すんなり売れるはずもない。だから、今や郊外でのマンション開発はほとんど不可能になってきている。
供給量は数分の一に
一方、都心においても従来は小さかった新築と中古の価格差が広がっている。たとえば、港区の表参道近辺では新築マンションの相場観が坪単価にして1000万円に迫っている。それだけ土地の価格が上昇しているのだ。ところが、築10年くらいまでの中古マンションの相場観は坪単価500万円から600万円。まるで郊外のような乖離が発生してしまっている。これは表参道のような一等地だけでなく、山手線の内側全般に見られる傾向である。
今後、新築マンションの価格が下落することは考えにくい。その理由は、土地の値段と建築費に下がる見通しがほとんどないからだ。土地は増えゆくインバウンドをにらんだホテル業者が、これからも高値で買っていくはずだ。彼らの高値買いにブレーキをかけるかと思われた民泊は、政府が不要な規制を設けたおかげですっかり萎んでしまった。
建築費は15年前の2.5倍くらいに高騰しているが、その原因は人件費。その背景にあるのは人手不足。鉄筋コンクリートの建物をつくるための職人がここ10年で激減したといわれている。その結果、人件費が2倍以上に高騰。それにつられてマンションの建築費も上がってしまった。少子高齢化により、人手不足は当面解消しそうにない。
そのうち都心でも「新築を購入したら2億円だが近くの築10年は1億円」という時代がやってくる。そうなると、新築マンションは売れなくなるから、今の郊外のように供給がなくなってしまうのだろうか。
実は、そういうことは考えにくい。新築マンションは一定数供給されるはずだ。ただ現在の供給量の数分の一程度には減るはずだ。それでも中古の倍近い値段の新築マンションを購入する富裕層が存在するからだ。同じような機能のマイカーでも、価格が国産に比べて2倍程度のメルセデスやBMWを喜んで購入する層がいるのと同じ理由だ。なかには数倍以上になるポルシェやフェラーリを買う人だっている。
マンションも同じように、贅をつくした新築に中古の倍以上のお金をかける富裕層が必ずや一定数はいるはずだ。新築マンションという商品は、そういった趣味で新築を買う富裕層のための特殊な商品になるのだ。
(文=榊淳司/榊マンション市場研究所主宰、住宅ジャーナリスト)