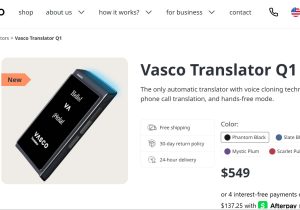大量供給なのに値崩れしない東京オフィス市場…空室率2%台が示す企業行動の変化

●この記事のポイント
・東京のオフィス市場では大量供給が続くにもかかわらず、空室率は2%台まで低下し賃料も上昇中。「供給過剰説」が成り立たない背景には、企業のオフィス戦略の根本的変化がある。
・企業はコスト削減ではなく、人材獲得と生産性向上を目的に最新・高立地オフィスへ移転。港区や渋谷、丸の内では“満室状態”が常態化し、都心5区で激しい争奪戦が起きている。
・今後の焦点は新築移転後に生じる「二次空室」の行方。市場全体が崩れるのではなく、老朽ビルが淘汰される“選別の時代”が始まり、東京一極集中はなお続く可能性が高い。
いま、東京のオフィス市場で「常識」では説明のつかない現象が起きている。建設資材価格の高騰、人手不足、リモートワークの定着――。本来であれば、オフィス需要を冷やすはずの逆風が吹き荒れるなか、東京都心では今後5年間にわたり、かつてない規模の「超・大量供給」が予定されている。
通常であれば「供給過剰によるオフィス暴落」、いわゆる「2025年問題」が声高に叫ばれても不思議ではない。しかし、現実は真逆だ。空室率は下がり続け、賃料は2年近く上昇を続けている。
なぜ東京だけが、これほどまでに強いのか。その背景には、日本企業の「生き残り」をかけたオフィス戦略の劇的な変化がある。
●目次
- 過去5年を大幅に上回る「年16万坪超」という異次元供給
- 「空室率2%台」が示す、驚異的な需要吸収力
- 都心5区「争奪戦」のリアル…港区一極集中と“空室ゼロ”地獄
- 2026年へのカウントダウン…二次空室は“崩壊”か“選別”か
過去5年を大幅に上回る「年16万坪超」という異次元供給
商業用不動産大手コリアーズ・インターナショナル・ジャパンが公表した予測は、業界関係者に大きな衝撃を与えた。東京中心部(千代田・中央・港・新宿・渋谷・豊島・品川の一部)における、今後5年間の年間平均供給面積は16万6,800坪。過去5年間の平均(約12万3,700坪)と比べ、実に35%超の増加となる。
注目すべきは、その多くが大規模再開発によるハイグレードビルである点だ。大阪、名古屋、福岡といった地方中枢都市では、建設費の高騰を受け、新規プロジェクトの凍結や延期が相次ぐ。一方、東京ではデベロッパーがコスト増を織り込んだうえで、開発の手を緩めていない。
不動産ジャーナリストの秋田智樹氏はこう分析する。
「東京は賃料水準そのものが高く、長期で見れば建設費高騰を吸収できる前提が成り立つ。地方都市と同じ物差しで“供給過剰”を語ること自体が、すでに現実とズレています」
「空室率2%台」が示す、驚異的な需要吸収力
供給が増えれば空室が増える――。この市場原理が、現在の東京ではほとんど機能していない。
三鬼商事が発表した2025年11月時点の東京都心5区の平均空室率は2.44%。9カ月連続で低下し、事実上「満室」に近い水準だ。さらに平均賃料も22カ月連続で上昇しており、大量供給をものともせず、市場がそれ以上のスピードでオフィスを“飲み込んでいる”状況が続く。
この異常とも言える需要の正体を解くヒントが、森ビルが実施した「2025年 東京23区オフィスニーズに関する調査」にある。
同調査によれば、新規賃借の予定がある企業は全体の27%。注目すべきは、その移転理由だ。
・立地の良いビルに移りたい(33%)
・新部署設置・業容拡大(26%)
・設備グレードの高いビルに移りたい(25%)
かつて主流だった「賃料削減のための移転」は影を潜め、オフィスは今や人材獲得と生産性向上のための戦略投資へと位置づけが変わった。
都内でオフィスを構えるスタートアップ企業の経営者は、こう打ち明ける。
「リモートワークで十分だと思っていた時期もありましたが、優秀な人材ほど“集まる価値のある場所”を求める。最新ビルの立地や環境は、どんな求人広告よりも効くんです」
秋田氏も、「オフィスの役割そのものが変わった」と指摘する。
「企業が欲しいのは“机を並べる箱”ではない。社員を呼び戻し、外部からも選ばれる“舞台装置”です。その機能を満たせるビルは、実は限られています」
この結果、最新スペックの大型ビルへ需要が集中し、玉突き移転が加速している。
都心5区「争奪戦」のリアル…港区一極集中と“空室ゼロ”地獄
最新データからは、都心5区のなかでも明確な「勝ち組」と「調整局面」が浮かび上がる。
港区:東京で最も“街が生まれ変わっている”爆心地
2025年度上半期、都心での移転先の過半数が港区に集中。浜松町ビルディングなどの再開発に伴う退去企業が、そのまま麻布台ヒルズや虎ノ門ヒルズへ移る「港区内循環」が常態化している。
渋谷・千代田:空室を探すこと自体が困難
渋谷区はIT・クリエイティブ企業の集積が続き、空室率は2%を下回る水準。千代田区(丸の内・大手町)では外資系金融・コンサルの拡張意欲が根強く、坪単価3万円超を維持している。
エリア格差が示す「選ばれる条件」
一方、中央区や新宿区では、築年数の古い中小ビルを中心に空室が目立ち始めている。
「立地」「設備」「環境」の3拍子が揃わないビルは、同じ都心でも競争力を失いつつある。
2026年へのカウントダウン…二次空室は“崩壊”か“選別”か
今後、市場の最大の焦点となるのが、新築ビルへの移転後に残る二次空室(既存ビルの空き)だ。これまでは別の企業が埋めることで需給が保たれてきたが、供給がさらに増えれば、Bクラス以下のビルは賃料を下げても埋まらないリスクを抱える。
秋田氏はこう警鐘を鳴らす。
「今後起きるのは“オフィス不況”ではなく、“オフィスの選別”です。市場全体が崩れるのではなく、価値のないビルだけが静かに淘汰されていく」
現在の東京オフィス市場は、単なるバブルではない。企業が生き残りをかけ、最高の環境を奪い合う戦略的な椅子取りゲームだ。
賃料上昇はどこまで続くのか。2026年に向けた超大量供給は、市場を冷やすのか、それとも東京一極集中をさらに加速させるのか。
都心の空を埋め尽くすクレーンの群れは、日本経済の「再生」の象徴か、それとも「過熱」の前兆か――。その答えは、これから竣工を迎える数々のメガプロジェクトの稼働率が、静かに示すことになるだろう。
(文=BUSINESS JOURNAL編集部)