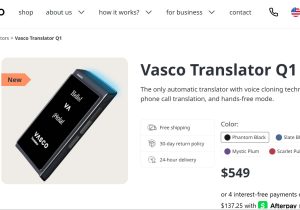年内に賃貸マンション家賃「平均25万円」が確実…買えない層にもしわ寄せの現実

●この記事のポイント
・東京23区の賃貸家賃は平均25万円目前。新築・中古価格の高騰が波及し、家主は強気の値上げ。
・郊外も万能策ではなく、埼玉・千葉などコスパ重視エリアへのシフトが進む。
・行政支援や二拠点居住など多様な選択が登場、柔軟な「住まい経営」が鍵に。
東京23区の賃貸マンション家賃が、ついに平均25万円に迫っている。不動産情報サービス「アットホーム」の最新データ(2025年9月時点)によると、23区内の賃貸マンション平均家賃は3カ月連続で過去最高を更新。単身者向けでも10万円を突破し、ファミリー向け(70平米前後)の平均家賃は24万円台後半に達した。
この勢いなら、年内にも25万円台突入は確実――。いま、東京で「借りる」ことすら難しくなりつつある。
背景には、新築・中古マンションの販売価格高騰による“購入断念層”の増加がある。都内新築マンションの平均価格は今年、初めて「9000万円台」に乗せた。手が届かない購入層が賃貸市場に流れ込み、供給が追いつかない。結果として、家賃はじりじりと上昇し、入居者争奪戦が常態化している。
●目次
- 「強気の大家」が支配する市場、上昇圧力は止まらない
- 「郊外移住」も万能策ではない――現実的な選択肢とは?
- “二都居住”や社宅・シェアハウス再評価の動きも
- 「買えない・借りられない」時代、どう備えるべきか
「強気の大家」が支配する市場、上昇圧力は止まらない
現在の賃貸市場では、「家主側の強気姿勢」が目立つ。物件の供給が極端に少ないため、「いくら引き上げても入居者が見つかる」状況が続いているのだ。
「たとえば、港区・目黒区・文京区などの人気エリアでは、新規募集の際に前入居者の家賃より月3~5万円高く設定することも珍しくない。特に子育て世代に人気の70~80平米クラスは供給が限られ、内見前に申込が入るケースすらある。
家賃上昇は今後もしばらく続く見通しだ。その理由は、賃貸市場の動きが「分譲価格を1~2年遅れて追随する」という構造にある。新築・中古の販売価格が高止まりしている限り、家賃も数年単位で上昇を続ける傾向があるからだ」(不動産コンサルタント・秋田智樹氏)
野村不動産ソリューションズの試算によると、23区内の分譲マンション平均価格は2026年も上昇を続ける見込みで、平均1億円突破が現実味を帯びている。住宅ローン金利の上昇圧力もあり、購入に踏み切れない層がさらに賃貸市場へ流入すれば、家賃相場の上昇に拍車がかかる構図だ。
では、なぜこれほどまでに賃貸供給が増えないのか。
「主な要因は土地不足、建設コスト、人手不足の三重苦にある。まず土地。都心部では再開発が相次ぐものの、賃貸向けの土地が確保できない。駅近の土地はオフィス・商業・タワーマンションに優先的に割り当てられるため、一般的なファミリー向け賃貸マンションの新規建設が難しい。
次に建設コスト。鉄骨やコンクリートなど建設資材の価格は、2022年以降20〜30%上昇した。加えて建設現場の人手不足で人件費も急騰。デベロッパーにとって賃貸物件を新たに建てる採算が合いづらい構造になっている」(同)
結果として、供給の大半がワンルームや単身向け物件に偏り、ファミリー層向けは希少価値を増している。国土交通省によれば、2024年度の首都圏賃貸住宅着工件数のうち、3LDK以上のファミリー向けは全体のわずか8%に過ぎない。
「郊外移住」も万能策ではない――現実的な選択肢とは?
「家賃が高いなら郊外へ」と考える人は多いが、実はそれほど単純ではない。リモートワークが定着していたコロナ禍とは異なり、2025年現在は「出社回帰」の流れが顕著だ。大手企業を中心に、週3~4日の出社を求める動きが広がっており、郊外移住のメリットは縮小している。
ただし、エリアを選べば“現実的な最適解”は存在する。不動産会社各社の調査を総合すると、神奈川方面よりも埼玉・千葉方面のほうがコストパフォーマンスが高い傾向がある。
具体的には以下のような傾向が見られる。

なかでも埼玉の「川口」や「南浦和」、千葉の「市川」「船橋」は、都心まで30分以内でアクセスできるうえ、商業施設・学校・医療機関が充実。家賃も東京の6割程度に抑えられる。
“二都居住”や社宅・シェアハウス再評価の動きも
興味深いのは、ファミリー層の間で「二都居住」や「週末拠点」の発想が広がっていることだ。平日は夫が会社近くのワンルームを借り、家族は郊外に定住する。あるいは、夫婦がそれぞれ週2~3日ずつ出社し、都心の“セカンド拠点”をシェアする。住宅関連サービス「OYO LIFE」や「Addresso」では、こうした新しいライフスタイルに対応した短期賃貸や多拠点プランの利用が増えているという。
また、企業側の福利厚生として「社宅制度の復活」「住宅補助の拡充」に動く企業も増加。パナソニックやNTTグループなどは、従業員の居住支援策を強化している。「住宅の確保」が人材採用・定着の鍵になる時代が到来しているともいえる。
行政側も手をこまねいているわけではない。東京都は2024年度から「子育て世帯等家賃補助制度」を開始し、18歳未満の子を持つ世帯に対して最大月額1万円を補助する制度を拡充した。加えて、区単位でも支援の動きが活発だ。
たとえば荒川区や足立区は、3人以上の子どもを持つ世帯向けに家賃助成や引越し費用補助を実施。中央区や江東区もファミリー向け公営住宅の増設を進めている。しかし、補助金の規模は家賃高騰を相殺するには力不足であり、「焼け石に水」との声も根強い。
一方で、郊外自治体では「東京都勤務者向け誘致策」が広がっている。埼玉県和光市は、池袋まで15分という立地を活かし、子育て支援や家賃補助制度を拡充。千葉県市川市や流山市も同様の戦略をとっており、結果として首都圏全体の人口バランスが緩やかにシフトしつつある。
「買えない・借りられない」時代、どう備えるべきか
もはや、東京23区で「買う」ことも「借りる」ことも容易ではない。それでも現実的に暮らしていくためには、3つの視点が求められる。
・居住エリアを柔軟に再定義する
「職住近接」だけを絶対視せず、交通・教育・医療など複合的に考える。特に埼玉・千葉方面の交通利便性が高いエリアは、今後も相対的な優位を保つ。
・ライフステージごとに“住まい戦略”を設計する
子どもが小学校に入る前後で居住地を変える選択肢を想定し、長期的なローンよりも柔軟な賃貸を活用する。二拠点生活や短期契約型の賃貸も検討に値する。
・住宅支援策や補助制度を最大限活用する
国・自治体の補助金、企業の住宅手当制度を調べて組み合わせることで、実質的な家賃負担を軽減できる。知らないままでは「損をする」時代になっている。
住宅価格も家賃も高止まりするなかで、ファミリー層が直面するのは「都心に住めるか」ではなく、「どこでどのように暮らすか」という根本的な問いである。郊外移住・二拠点居住・短期賃貸・企業支援など、多様な選択肢が出そろいつつある今こそ、柔軟な発想と情報収集力が試される。
“25万円時代”の東京で、住宅をめぐる選択は、もはや「住まい」ではなく「経営判断」に近い。その意思決定力こそが、これからの首都圏ファミリーにとって、最大の資産となる。
(文=BUSINESS JOURNAL編集部)