銀行の預金封鎖も現実味、過去に日本でも実施…自分の“資産を防衛”する具体的方法

「Getty Images」より
今年1月、マイナンバーと金融機関の預貯金口座を連結する制度の義務化について、高市早苗総務相が財務省と金融庁に検討を要請したと報じられています。2021年の通常国会での共通番号制度関連法改正を視野に、20年中に具体策をまとめる方針とのことです。さらに4月20日には総務省が、新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策として1人あたり10万円を給付する「特別定額給付金」の受給対象者は、2020年4月27日時点で住民基本台帳に記載されている人であると発表しました。給付方法は「郵送申請」および「オンライン申請」の2通りあるものの「オンライン申請」は、マイナンバーカード所持者のみが利用可能です。これらの政府の対応に対して「預金封鎖への布石か?」「政府による個人財産の監視だ」などの声があがっています。
預金封鎖とは?
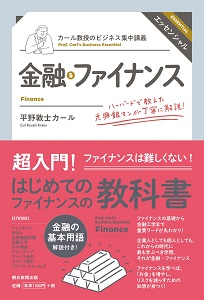
預金封鎖とは、国が国民の私有財産である銀行の預貯金口座を凍結して、お金を引き出せなくすることです。多くの場合、突然課税して強制的に徴求します。引き出せるのは少額の生活費用の金額のみとなります。
日本でも戦後の1946年、新しい円に切り替え旧通貨が使えなくなった日の翌日にあたる休日から実施され、戦後賠償金の返済などに国民の資産を充てたのです。預金だけでなく株式や不動産、金などあらゆる資産に資産税が最高90%という高い率で課税されました。資産が多い人ほど累進的に課税されました。当時はインフレが300%くらいだったともいわれていますから、貨幣価値は暴落してしまいました。そして今の日本では、政府が国会審議もなく決定できるようになっています。
日本以外にもキプロス、ロシア、アルゼンチン、ブラジルなどでもハイパーインフレの際に預金封鎖が行われました。当時(1990年代)、私は興銀マンとして国際本部にいたので、中南米国のデフォルト(債務不履行)によるリスケジュール(元本や利息の支払いを猶予する)に追われたのを覚えています
20年ぶりにお札のデザイン変更
2019年4月9日の閣議後の記者会見で、麻生太郎財務相が1万円、5000円、1000円の3種類のお札(日本銀行券)と500円硬貨のデザインを新しくすると発表しました。“お札の顔”には、1万円札は「近代日本経済の父」と呼ばれる渋沢栄一、5000円札は日本で最初の女子留学生としてアメリカで学び津田塾大学を創始した津田梅子、1000円札には破傷風の治療法を開発した細菌学者の北里柴三郎の肖像画が使われることで話題になりましたね。そうすると、2024年の新札への切り替えの土日が、預金封鎖実施のターゲット日になる可能性はゼロではないといえるかもしれません。そんなことは起きないと信じていますが。
国にとってはメリットだらけ
ハイパーインフレになれば、国の借金もチャラになるといわれています。円建ての借金であれば、為替が大幅な円安になるからです。当然、株も土地もすべての価格が暴落します。しかし、その後、円安を背景に輸出産業は急成長する可能性があります。実際にそうして復興している国もあるのです。政治家たちがどう財産を動かすかをチェックしておくと良いかもしれません。
国の借金がチャラになって、その後復興するのであれば、国民の財産よりも国の健全化を優先する政権の場合には、預金封鎖や資産課税、預金課税をする危険性はゼロではないでしょう。実施するためには預金などの国民の財産状態を政府が把握する必要があります。それがまさにマイナンバーの目的だという指摘もあるほどです。
どうすれば資産防衛できるのか?
実はロシアなどでも海外に資産を有していた人が、資産価格が暴落した後に土地などを大量に買って富豪になっている例があります。つまり資産防衛のためには、海外に資産を円建て以外で保有したり、金(きん)などの国際的に換金性のある実物を保有することが有効かもしれません。なお、日本の金融機関は預金封鎖の対象になるので、日本の金融機関以外を通して保有する必要があります。
今は海外不動産なども5000万円以上は登録が必要ですし、海外送金もチェックされています。金も200万円以上の購入は把握されています。このため富裕層ならば海外へ移住するのもひとつの方法なのかもしれませんが、新型コロナウイルスが世界的におさまらない限り難しいかもしれません。本来、海外の不動産なども良いかもしれませんが、なかなかハードルが高いですね。
一番簡単なのは、著名な経営コンサルタントも以前勧めていた「米ドルなどの外貨を現金でタンス預金する」ことなのかもしれません。もっとも今の新型コロナウイルスの影響で円相場の先行きも不透明なのでタイミングも重要です。あとは、やはり場所を問わず稼げる仕事、たとえばネットだけで稼げるようになるスキルを身に着けることも重要でしょう。そのためにも、金融やファイナンスについての基礎知識を持つことをオススメします。
私は日本が大好きなので、杞憂に終わることを祈るばかりです。
(文=平野敦士カール/株式会社ネットストラテジー代表取締役社長)











