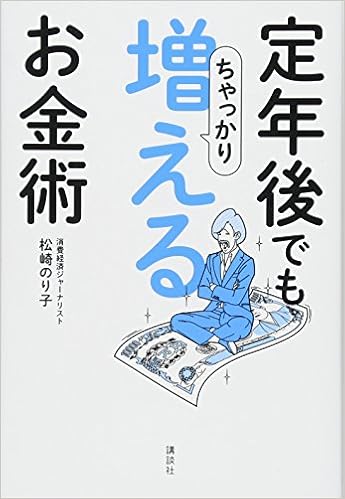有料化されたレジ袋、その都度買った方が“まとめ買い”より安上がり?単価を検証してみた

ご存じのように、2020年7月1日からレジ袋が有料化された。コンビニやスーパーなどでの会計時には「レジ袋は有料となりますが、必要ですか?」というやり取りが加わった。消費者のみなさんは、どのくらいレジ袋を買っているだろう。
この有料化、もとはといえば、海洋プラスチックごみ問題や地球温暖化に対し“脱プラスチック”に取り組んでいますよ、と世界にアピールするもの。19年6月には、世耕弘成経済産業大臣(当時)がG20のエネルギー・環境相会合で「オリンピック・パラリンピックに間に合うように2020年4月には有料化できるようにしたい」と述べていた。
その言葉通り、大手流通は今年4月に有料化をスタートさせたが、国を挙げて7月1日開始と決めたのは、くだんのオリンピック・パラリンピックを見据えたのだろう。全世界からの目が日本に注がれ、海外客も押し寄せる7月のタイミングで「日本も脱プラに取り組んでいますよ」とアピールしたかったのではないか。
しかし、そこへきて新型コロナだ。オリ・パラは延期され、しかも感染防止の観点から容器類は使い捨ての方が望ましいと、海外では使い捨てのポリ袋に回帰しているとも聞くのに、日本はかたくなにエコバッグ推奨とは。ちょっと脱力する。
しかも、レジ袋はプラ汚染の主犯とはいえず、経産省HPにも「普段何気なくもらっているレジ袋を有料化することで、それが本当に必要かを考えていただき、私たちのライフスタイルを見直すきっかけとすることを目的としています」とあり、つまりは意識改革目的でしかない。
それなら、せめて感染が落ち着くまで延ばせばいいのにと思うが、まあ「決まっちゃったからやらなきゃいけない病」はコロナにも勝る日本の風土病なのだろう。
とはいえ、買い物ごとにレジ袋代を払うのは、ただでさえコロナで傷んでいる我々の家計にとってはダメージだ。筆者もエコバッグはかなりの数を持っているが、ゴミ出しなどに重宝していたレジ袋が手に入らなくなるのは困る。特に、我が家にはゴミ箱がなく、レジ袋をフックにひっかけて使っているので、持ち手つきレジ袋は必須なのだ。
そこで考えた。どうせ買うなら、まとめ買いしたほうが安いのでは? と。
Mサイズは最低限の買い物用
有料化に関して、国は「価格も売り上げの使途も、事業者自ら設定してください。ただし、1枚あたりの価格が1円未満では有料化といえないのでダメです」としている。筆者の地元の店では、コンビニが1枚3円(特大は5円)、スーパーがMサイズ3円・Lサイズ5円、ドラッグストアがM2円・LL4円、100円ショップがS2円・M4円・L7円という価格設定。税込税別は店によりまちまちとなる。
SとかMとか言われても、これまで意識したことがないのでぴんとこない。記事のために、あえてスーパー、ドラッグストア、コンビニで買い物をして、レジ袋を購入してみた。実感として、Sサイズはけっこう小さい。たとえば、コンビニでおにぎりとペットボトル、おやつをひとつ買ったときの適量というイメージ。今回、セブン-イレブンでレトルトの袋めん2つとお菓子2つを買い、袋に入れてもらったところ、後でレシートを見たら、それはMサイズの袋だった(※コンビニはS・M・Lも同じく3円)。
さらに、スーパーで一家分の食材を買うと、Mでは心もとない。イオン系のミニスーパーの場合は、レジかご半分の量でM(2円)、レジかごひとつ分ならL(5円)が必要だとある。
数日分まとめ買いするなら、Lでないと入りきらないだろう。むろんコンビニやスーパーごとにレジ袋のサイズは異なるが、Mは最低量の買い物用と考えたほうがいい。
では、Mサイズ以上のレジ袋をまとめて買うとしたら、1枚あたりいくらで買えるかを検証しよう。
ドラッグストアでまとめ買いは割高に?
まず向かったのは、庶民の味方100円ショップだ。持ち手つきのレジ袋も売っているに違いない。100円で買えるならきっとそっちがお得だろうと、売り場に向かったのだが――ない。ないというか、SSやSサイズしか在庫がない。MやLは見事に売り切れだった。みな、同じことを考えるのだ。
しかし、様子はわかった。ダイソーはS相当サイズが65枚入り、Mが46枚入り、LLが35枚入り。キャンドゥはSが40枚入り、Mが30枚入り。それらが税込みで110円となる。
次にドラッグストアに向かったが、やはり1店目は売り切れ。次の店で発見したのは、S50枚入り250円、M50枚入り272円、L50枚入り305円(※税込み価格)。
ここで、1枚当たりの価格を計算してみよう。ダイソーはSが約1.7円、Mが約2.4円、LLが約3.1円。キャンドゥはSが約2.8円、Mが3.7円。先に書いたように、100円ショップの有料レジ袋はS2円・M4円・L7円なので、ダイソーは売り場で大量パックを購入した方が安いが、キャンドゥではほぼトントンということに。
さらに、ドラッグストアに至っては、SとMが1枚当たり約5円、Lは約6円だから、なんとレジで有料レジ袋を買った方が安いのだ(レジで買うとMなら2円)。がっかりではないか――。
まあ、小売店はグロスで業務用をまとめ買いしているのだから、我々が小売りで買うよりは安くなるのは道理かもしれない。でも、有料レジ袋のほうが安いなんていうのは悔しいので、次は業務用の価格を調べてみよう。
バイオマス配合もレジで買った方が安い?
業務用パッケージ商品を扱うECサイトで、価格をチェックする。今回は2種類のサイトの数字で検証した。これまで、S・M・Lとざっくり書いてきたが、サイトの表記に従うと、だいたいこんな感じとなる(これもレジ袋の種類により異なる)。※平らにしたときの幅×高さ、マチは含まず。
S 180mm×380mm
M 215mm×430mm
L 250mm×480mm
LL 295mm×530mm
3L 345mm×580mm ※スーパーのLサイズはこれだったので加えておく
ちなみに、セブン-イレブンで買ったM袋を計ってみたら、この中で最も近いのはLサイズだった。
次は価格だが、2つのECサイトで扱う100枚入りパック価格を1枚あたりに直すと以下の通り。※個人が買える価格で計算
S 1.2~1.5円
M 1.7~1.8円
L 2.3~2.7円
LL 3.4円
3L 5~5.5円
これを見ると、有料レジ袋が2円とか3円とかをつけるのは妥当な気もしてきた。
それだけではない。コンビニやスーパーで有料レジ袋として販売されているのは、バイオマス成分(植物由来原料)配合のものも多い。本来なら、バイオマス成分を25%以上配合し、バイオマスマークもしくはバイオマスプラマークが印字されているレジ袋は今回の有料化の対象外。
そのため、7月1日以降もこっちのレジ袋を配布している販売業者もいる。ただし、バイオマス成分配合レジ袋は従来物に比べて値段が高いので、業者側がすべてを切り替えるのは難しいわけだ(コンビニやスーパーは環境に配慮していますよという姿勢を見せるため、あえてこっちを販売しているのだと推察する)。
では、バイオマス配合のレジ袋はいくらなのか、さっきの業務用サイトで調べてみよう。
S 1.7~2.4円
M 2.1~3円
L 3.3~4.3円
LL 4.4~6.3円
3L 6.3~8.9円
いかがだろうか。たぶん、スーパーやコンビニでその都度買うのと、業務用サイトでまとめ買いするのと、さほど変わらないか、もしくはレジで買う方が安いかもしれない。節約のつもりで100枚まとめ買いしたのに――という人には残念だが。
小売りの現場も大変だ。レジでのひと手間が増え、場合によっては客に嫌な顔をされ、袋が必要ならと買い控えも起き、とはいえ袋で儲けるわけでもない。コロナで大変なところ、本当にお疲れさまと言いたい。
エコバッグ持ち歩きも悪くはないが、筆者のようにゴミ袋として必要で、しかも環境に優しいバイオマス配合レジ袋が欲しいという人は、その都度買った方がいい。手間もかからず、それがよろしいという結論に達した。これからは安心してお金を払おうと思う。
(文=松崎のり子/消費経済ジャーナリスト)
『定年後でもちゃっかり増えるお金術』 まだ間に合う!! どうすればいいか、具体的に知りたい人へ。貧乏老後にならないために、人生後半からはストレスはためずにお金は貯める。定年前から始めたい定年後だから始められる賢い貯蓄術のヒント。