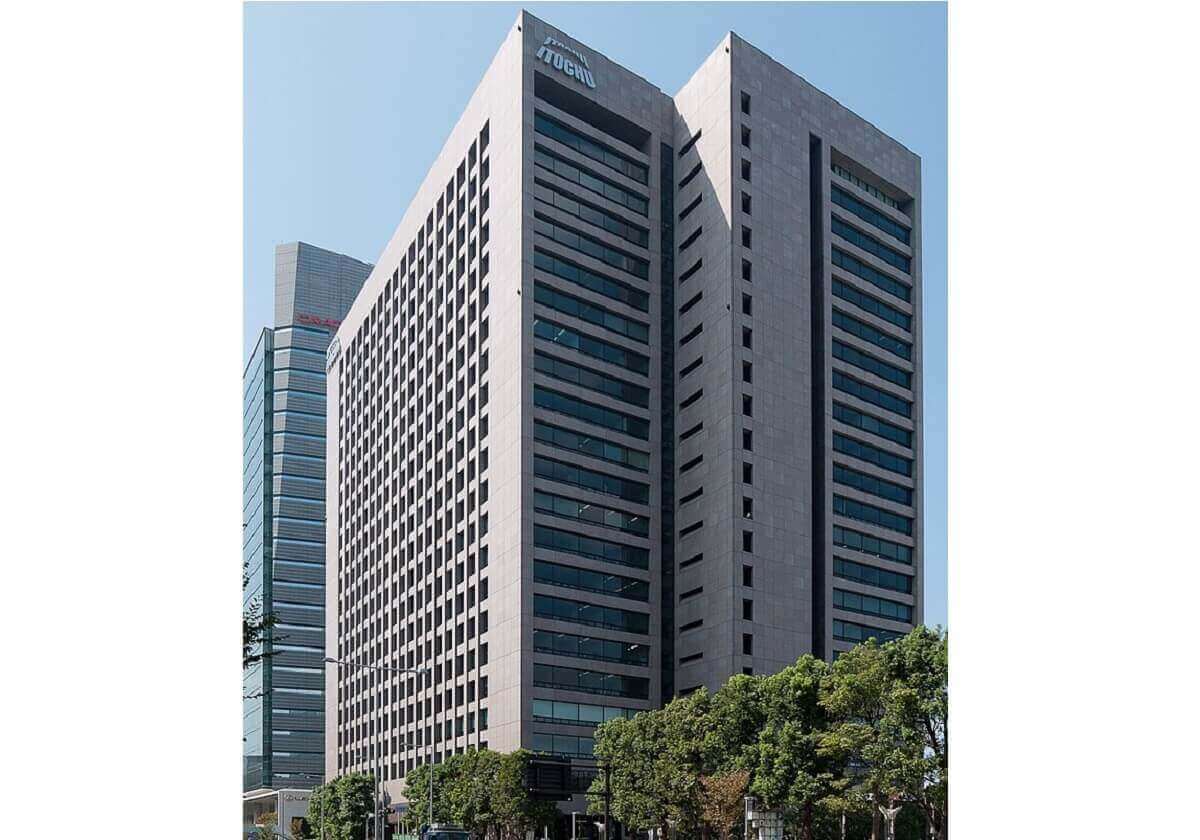
日本の大手総合商社の事業戦略が大きな変革を迫られている。その背景の一つとして、新型コロナウイルスの発生や中国経済の成長の限界などによって、これまで収益を支えた資源ビジネスが業績と財務面の重石となり始めたことがある。
そのなかで注目されるのが伊藤忠商事だ。過去5年間、同社の株価は60%程度上昇し、旧財閥系の総合商社の株価変化率を上回った。その理由の一つは、伊藤忠商事が市況に左右されやすい資源関連よりも、中国を中心に消費関連事業の強化に取り組んだことがある。それは2020年3月期決算において伊藤忠商事と他社の業績の明暗を分けた一因だ。
今後、伊藤忠商事は、中国をはじめ増大傾向にある世界経済の不確定要素に機敏に対応し、持続的に収益を獲得しなければならない。リスクに耐えられる収益と財務力を確立するために、伊藤忠商事はかなりのスピード感を持って改革を進めることとなるだろう。それに同社全体の組織が一丸となって取り組むことができるか否かが当面の焦点だ。
総合商社決算の明暗分けた資源関連ビジネス
リーマンショック後、旧財閥系を中心に大手総合商社は基本的には資源関連の事業を重視した。背景には2つの要因がある。1つ目が中国経済の成長だ。2008年11月、中国政府はリーマンショックの発生による景気の落ち込みを支えるために、総額4兆元(当時の邦貨換算額で57兆円程度)の経済対策を発動した。それは銅、鉄鉱石をはじめとする鉱山資源や原油や天然ガスなどエネルギー資源の価格の上昇を支えた。
2つ目が世界的な低金利環境だ。リーマンショック後、主要国の中央銀行は景気回復を支えるために積極的に金融緩和を進めた。世界の金融機関や事業会社の資金調達コストが低下し、価格の上昇期待が高まったコモディティー=商品市場に資金が流入した。米国ではシェール・ガスやオイルの開発が進み、商品価格の上昇期待が追加的に高まった。その結果、買うから上がる、上がるから買うという強気心理が連鎖し、世界的な“コモディティー・バブル”が発生した。それが総合商社の業績を支えた。ただし、価格上昇が未来永劫続くことはあり得ない。2014年半ば、コモディティー・バブルははじけ資源価格に下落圧力がかかった。
しかし、その後も旧財閥系の総合商社は資源事業を重視する戦略を続けた。その背景には、中国の景気対策や主要国の金融緩和策への期待があった。米トランプ政権の経済政策なども追い風となり、2018年の年央頃まで資源事業を重視した戦略は総合商社の業績拡大を支えた。
その一方、伊藤忠商事はバブル崩壊の影響を重く受け止めた。2015年、同社は、金融を中心とする中国の国有コングロマリット(複合事業体)企業である中国中信(CITIC)に約6000億円を出資し非資源事業の強化に戦略をシフトした。
2020年3月期決算を見る限り、事業ポートフォリオに占める資源関連事業の比率が、大手総合商社の明暗を分けた。市況に左右されやすい資源事業を重視した総合商社は、新型コロナウイルスによる需要低迷に直撃され業績悪化が著しい。
CITIC出資で意識改革を目指す伊藤忠商事
伊藤忠商事にとって、6000億円もの資金を用いて中国の国有企業との協業を深めることは大決心だった。中国の商習慣は、日本はもとより欧米とも大きく異なる。そう考えると、CITICへの出資によって伊藤忠商事は組織全体に新しい価値観をもたらし、消費分野でより多くの商機を手に入れるよう組織全体に意識改革を求めたといえる。
それを象徴する一つの取り組みが、デサントへの敵対的TOB(株式公開買い付け)の実施だ。日本企業同士の敵対的買収はまれだ。組織間の軋轢を生むリスクを冒してまで伊藤忠商事はデサントへの敵対的買収を断行した。一つの理由は、競争力あるブランドや商品企画力をもつデサントが同社の中国事業の強化に重要だからだ。また、デサントが過度に韓国事業に依存していたことの是正も目指された。
経営陣が刷新された後、デサントは中国での店舗増加に取り組み始めた。現在、デサントは欧米事業を売却し、中国に経営資源を集中的に投じようとするなど対中重視姿勢は一段と鮮明だ。その背景に、CITICとデサントの協働によって中国事業を強化したいという伊藤忠商事の思惑が影響している可能性は軽視できない。
懸念されるのは、中国を重視する経営陣の考えに組織全体がついてこられるか否かだ。冷静に考えると、現在の環境が本当に中国事業の強化に適しているか否かは議論が分かれるだろう。なぜなら、中国経済のリスクが上昇しているからだ。伊藤忠商事がCITICに出資した2015年頃から中国経済の成長率の鈍化が鮮明化し、債務問題が深刻化している。CITICの株価低迷はその裏返しだ。
それに加えて、新型コロナウイルスの感染拡大と米中対立の先鋭化も中国経済のリスクを高めている。コロナウイルスの感染状況に関してはワクチン開発などの動向から大きく影響される。当面、米中対立はさらに激化する可能性が高い。そう考えると、伊藤忠商事がCITICとの協働の成果実現を求める心理はかなり強いと考えられる。ある意味では、同社は中国事業の成果実現に焦っているようにさえ見える部分がある。
伊藤忠商事に求められる組織の結束強化
今後、伊藤忠商事に求められることは組織を一つに束ね、変化に対応することだ。世界経済を取り巻く不確定要素は増大している。同社経営陣は組織全体が向かうべき方向を明確に示し、人々が変化を機敏にとらえて行動する体制を整備しなければならない。
新型コロナウイルスの感染の影響は深刻だ。当面、世界全体で需要は低迷するだろう。中国経済は成長の限界を迎え、同国の景気対策に多くは期待できない。万が一、新型コロナウイルスの感染が一段と深刻化すると同時に米中対立がさらに激化すれば、世界経済にはかなりの影響がある。その場合、伊藤忠商事が海外で取得した資産の価値が毀損するなどし、業績と財務面に無視できない影響が及びかねない。
先行きの不確定要素が増大する状況下、伊藤忠商事は5800億円を投じてファミリーマートを非上場化する方針だ。その狙いは、安定した収益の獲得が見込まれる国内コンビニエンスストア事業を強化し収益基盤を強固にすることだ。それに加えて、伊藤忠商事は中国におけるコンビニ事業の強化も目指しているだろう。
懸念されるのが、完全子会社化によってファミリーマート事業を支えた人々の気持ちが伊藤忠商事から離れてしまうことだ。仮に、人々のやる気が低下してしまうと、ファミリーマートの完全子会社化が想定された成果を発揮することは難しくなる恐れがある。
そうなってしまうと、組織全体が変化に適応することは難しくなる。新型コロナウイルスの発生によって、世界経済の環境変化のスピードは加速化している。米国では老舗のアパレル企業ブルックス・ブラザーズなどがIT化の遅れやコロナ禍の影響に耐え切れず、日本の民事再生法に相当する連邦破産法11条の適用を申請した。その一方で、世界経済のデジタル化が進行し、衣食住に関連する多くの経済活動がIT空間に取り込まれている。
消費分野を重視する伊藤忠商事にとって、そうした変化は死活問題といえる。伊藤忠商事はコンビニ事業などを中心にデジタル技術の導入を迅速に進め、変化への対応力を高めなければならない。経営者が従業員一人一人のやる気を引き出し、組織を一つにまとめて改革を実行できる体制を整備できるか否かが、今後の業績に無視できない影響を与えるだろう。
(文=真壁昭夫/法政大学大学院教授)


















