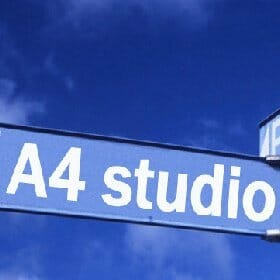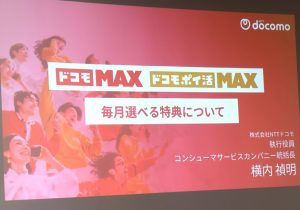睡眠時間3時間、高速道路は使えない…長距離バス運転手の過酷な労働実態と事情

3月18日付東京新聞が報じたところによると、厚生労働省の審議会は、かねてより議論されていたバス・タクシー運転手の休憩時間に関して「最低9時間とする」という厚労省の報告案を了承したという。
しかし、この9時間という休憩時間は、当然ながら食事や入浴、通勤といった時間をすべて含めた数字。実質的に睡眠時間が3、4時間程度になってしまう運転手もいると見られており、健康被害や運転中の事故にもつながるのでは、という懸念も強いようだ。
もともと厚労省はEUや国際労働機関(ILO)が業界各社に勧告している内容を参考に、「最低11時間とする」案をまとめていたが、これに運行会社側が「運行計画が立てられない」と反発。結果として今回の「9時間」に着地したのだという。
そこでバス・タクシー運転手の労働環境の過酷な実態、そして休憩時間が長く取れない状態になぜ陥っているのかを紐解くため、業界事情に詳しい桜美林大学の戸崎肇氏に話を聞いた。
かつての規制緩和で激増した公共交通機関各社の競争
そもそも今回の改定前、バス・タクシー運転手の休憩時間の定めはどのようなものだったのだろうか。
「これまでの休憩時間の定めは『最低8時間とする』というもので、1989年に告示されました。今回の報告案は『最低9時間』なので、1時間増えるならばいいではないかと思うかもしれませんが、問題はそう単純ではないのです。
当時は今ほど運行本数が多くなかったこともあり、比較的この休憩時間でも問題なかったのですが、2002年に改正道路運送法が適用されたことにより状況は変わっていきます。規制緩和により運輸業界各社の競争は激化するようになり、運転手たちの労働時間は増加していきました。こうなってしまうと、これまでの休憩時間の規定では運転手に負担がかかりすぎるわけです」(戸崎氏)
休憩時間の問題はタクシー業務とバス業務で異なってくるという。
「まずタクシーに関してですが、1回の業務の拘束時間だけで見ると非常に長いです。基本的な勤務形態でいえば、朝5時から翌日の朝5時までという24時間労働となっているんです。ただ、24時間ずっと働きっぱなしではなく、その間の休憩はある程度運転手の裁量に委ねられています。また24時間勤務後は24時間の休養が与えられるため、一概に“勤務時間が長いから休めない”というわけでもないかと思います。
次にバス、なかでも路線バスはタクシーよりは不規則性が低いとはいえ、早朝と夜に勤務が集中してしまう傾向があります。というのも、路線バスは通勤通学と帰宅の時間帯に利用者が激増するので、運行会社がその時間帯に本数を多くしているからです。運転手にとってみれば帰宅ラッシュを乗り切り午後9時に勤務が終わっても、翌朝の午前5時から勤務が始まり出勤ラッシュに突入するということが多々あるという状況。タクシー運転手と比較すると、心身への負担はバス運転手のほうが大きいかもしれません」(同)
終業後も作業? 実質3時間しか寝られないケースも
今回改定となった「9時間」という休憩時間。一見すると充分な時間が確保できていると思えるかもしれない。だが、その内訳を紐解いていくと、運転手たちの過酷な労働実態が見えてくる。
「9時間の休憩といっても、通勤に退勤、入浴に食事、自由時間などが含まれるので、実質的な睡眠時間は4、5時間取れればいいほうでしょう。また、運転手たちは運行が終わった後に報告書を作成するのですが、そうした作業をこの休憩時間で消化しなければならない人もいるでしょうから、なかには睡眠時間が3時間ほどになってしまうという人も少なくないはずです。
そんな毎日が続けば当然疲れとストレスは溜まり、睡眠時無呼吸症候群を発症して睡眠の質が低下することも考えられます。運行中にうたた寝をしてしまい、大きな事故につながるなんて可能性も高まるかもしれません。また、睡眠不足は心筋梗塞などの疾患にもつながりかねませんし、ストレスから乗客とのトラブルに発展する場面も出てくるでしょう」(同)
戸崎氏は、こうした休憩時間問題の影響を一番受けやすいのは、運輸業界のなかでも長距離バスの運転手だと指摘する。
「長距離バスの場合、路線バスのように昼間の時間帯は運行本数が減るといったことがあまりないので、忙しさに切れ目がないのです。さらに、この業界は不況の影響が大きく関わっており、好景気時と不景気時の収益の落差が激しいので、運行会社側は運転手を多く雇えないという問題があるのです。そのため、ここ十数年間は現状の運転手数で運行のやりくりをするほかなく、運転手たちの負担は増加の一途です。
また、会社側は運行時の高速道路利用を推奨していますが、これはあくまで表向きという印象。実際にはコストカットを優先して、運転手たちに“高速は利用しないでほしい”という暗黙の了解的圧力がかかっているといった声も、運転手たちから挙がってきています。高速道路を使わないと運転時間が長引くため、運転手の負担増になるということは想像に難くないでしょう」(同)
運賃を値上げして、その分運転手の人数を増やせばいいと思うかもしれないが、そう簡単な問題でもないようだ。
「バス会社同士の競争原理が働いているため、値上げは難しいのです。運賃を値上げして他のバス会社を利用されるようになってしまっては、自分たちの首を絞めることになってしまいますからね。そうして運賃の値上げをすることができないとなると、そのしわ寄せがジリジリと運転手たちにいってしまうというわけです。今回の休憩時間の改正に際し、当初厚労省の『最低11時間』という提案に対し、運行会社側が『運行計画が立てられない』と反発したのには、こうした背景があるのでしょう」(同)
解決策が見出せぬ「休憩時間問題」の行く末は……
今回、厚労省の審議会が了承した「9時間」という休憩時間の決定に関して、戸崎氏はこう所感を述べる。
「とりあえず決めるものは決めなければいけないので、一旦はこの数字を折衷案的にしたのでしょう。ですがここで終わりにせず、今回の報告案で問題が改善しているのかということを精査し続けることが肝心。むしろ、コロナ禍から世界が元に戻ったときに、この案で通用するのかというのが試されるでしょう。
また、近年は高齢者ドライバーが免許返納していく流れや、若者の免許取得率の低下が顕著になっており、公共交通機関の需要はこれまで以上に高まるはず。そうなったときに、現状の規定の微調整で本当に対応できるのかという懸念もありますが、需要が高まれば業界全体で運賃値上げに踏み切って、運転手の労働環境が改善されていく可能性もあるでしょう」(同)
利用者の安全も脅かしかねない運転手たちの睡眠時間不足問題。休憩時間を十分に確保しようとしない運行会社側の姿勢は非情に映るかもしれないが、経営状況的に確保してあげたくてもできないという事情もあるということのようだ。こうした問題がコロナ禍でどう変貌してゆくのか、これからも注視していきたい。
(文=A4studio)