新型コロナ、株相場はリーマンショック級どころか“標準的な値下がり”という事実
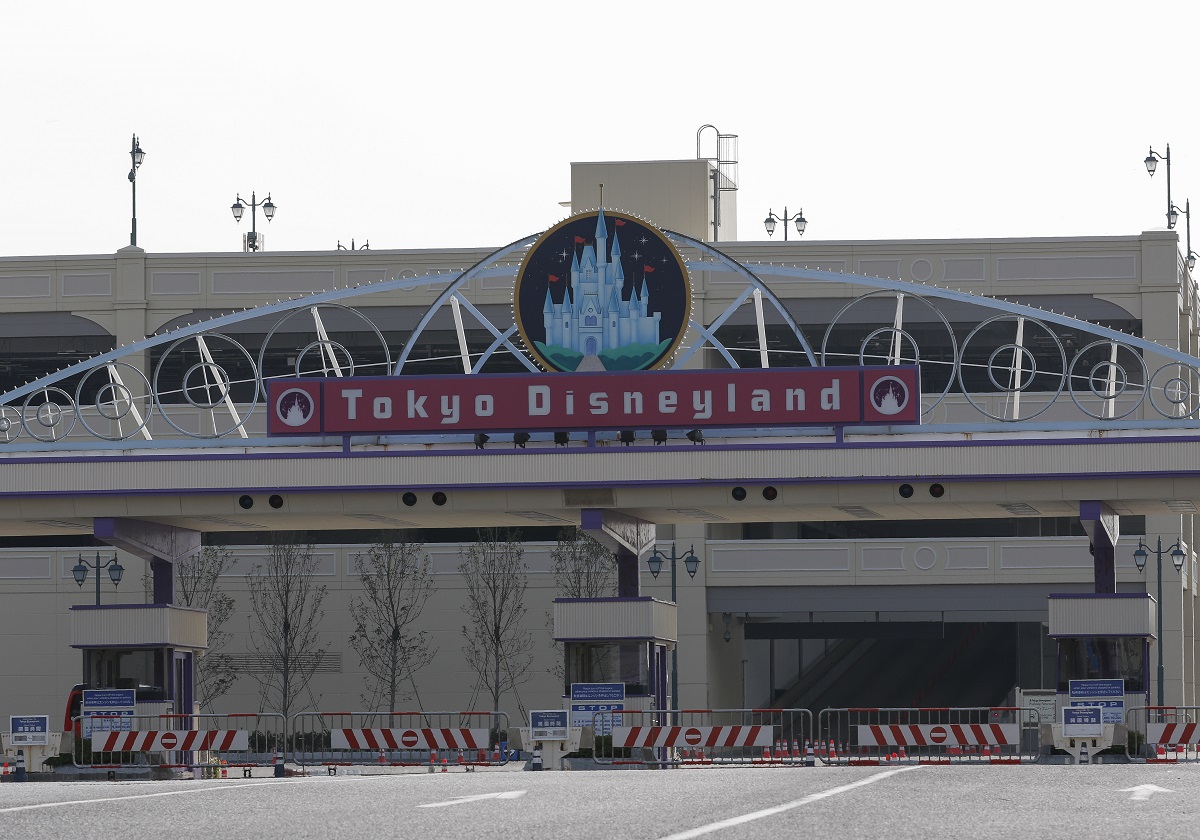
新型コロナウイルスの世界的な流行によって、株式市場もまた大混乱に陥っている。国内外で感染者数の急増が伝えられた2月の後半から東京市場は荒れ模様になっていたが、3月に入ってからは9日に下落幅で4桁、同じく率にして5%超(いずれも前日終値比)の暴落に見舞われ、平均株価は長く定位置にしていた2万円をあっさり割り込んだ。さらに週をまたいだ13日には再度の暴落が発生、平均株価は1万7000円台まで下落した。
「相手が人殺しウイルスでは手の打ちようがないよ」(70代の個人投資家・投資歴40年)
「変動率の高い相場は望むところだが、今回に関してはどうも怖い」(デイトレード経験の豊富な50代の投資家・投資歴20余年)
日頃交流のある手練れの投資家もお手上げの様子だ。
確かに今回、市場の暴落の原因になっている新型コロナウイルスはいくつもの厄介な性格を持っている。3つあげるのならば、
(1)局地(ひとつの地域・国家)ではなくグローバルに悪い影響を与える
(2)参考にしやすい過去の事例が見つけづらい
(3)景気拡大が長期化した状況で発生した
ことである。特に(3)は、過去の暴落からも長い調整局面が続くことにつながりやすい。
ただ、いかに広い範囲で経済に深刻な影響をもたらし、かつ参考になるケースが見当たらない極めつけの悪材料であっても、これに対応する株式市場が計り知れないほどの消化能力、言い換えれば復元力を持っていることも確かだ。世界恐慌の再来まで真顔で語られた十余年前のリーマンショックにしても、破局には至らずに収束した。
折から、そのリーマンショックに絡めて興味深い見解が飛び出した。3月15日に民放テレビの報道番組に出演した西村康稔経済再生担当大臣が、コロナショックが日本経済に及ぼす影響について「リーマンショック並みかそれ以上かもしれない」と述べたのである。当時の暗い記憶を持つ方ならば震撼してしまったかもしれない。さすがに断言はしていないものの、現在進行形の事象を過去の最も悪い事例に準えるのは、少なくとも穏当ではあるまい。
では、株式に関してこの見解が妥当なものなのか、検証してみよう。
リーマン並みの水準なら底値は1万1800円?
リーマンショック時の株式市場の推移を振り返ってみると、改めてその異様さに驚く。前年から取り沙汰されていた米国のサブプライムローン問題が、より顕在化、深刻化した2008年の株式市場は年央から軟調な展開になり、10月8日から12月2日にかけて暴落(平均株価の当日終値が前日終値比5%超下落)が11回発生した。戦後の株式市場で2カ月あまりのうちに、これだけ大幅安が頻発したことはない。この間、平均株価は年間最高値となった大発会終値の1万4691円から、10月27日の同7162円まで率にして51%、ほぼ半値になった。
現在までのところ、新型コロナウイルスに関する暴落は先述した2回である。3月初旬を起点にすると、5月中旬までにあと9回の暴落が起こることで、リーマンショックに並ぶことになる。
またリーマンの1回目、2回目の暴落が、それぞれ前日終値比で9.4%、9.6%安であったのに対して、今回は同5.1%、6.1%安だ。今年の平均株価の最高値2万4083円(1月20日終値)からリーマン並みの半分の水準まで下落するならば、底値は1万1800円になる。
想定外のことが起こりやすい株式市場ではあっても、そうなることは、まず考えづらいところだ。下落率からもわかるように、リーマンは10%近くに達するのに対して、今回のそれは数%であり、同じ暴落でも前者は弩級、後者のそれは標準的なものである。また平均株価の1万2000円割れは上場企業(日経225採用銘柄)の解散価値を下回る。
結果がどうなるかは、感染症流行のピークアウトを待つよりほかはないが、指標を対比してもコロナショックが、リーマン並みやそれ以上になる可能性は高くはあるまい。立場上、警鐘を鳴らす意図が含まれていたとしても、異常心理が増幅している状況下を考えれば、西村大臣の発言は軽率の誹りを免れないだろう。
(文=島野清志/評論家)











