ホンダ、最も困難な選択「エンジン全廃」の裏にEVでの勝利の確信…第二の創業へ
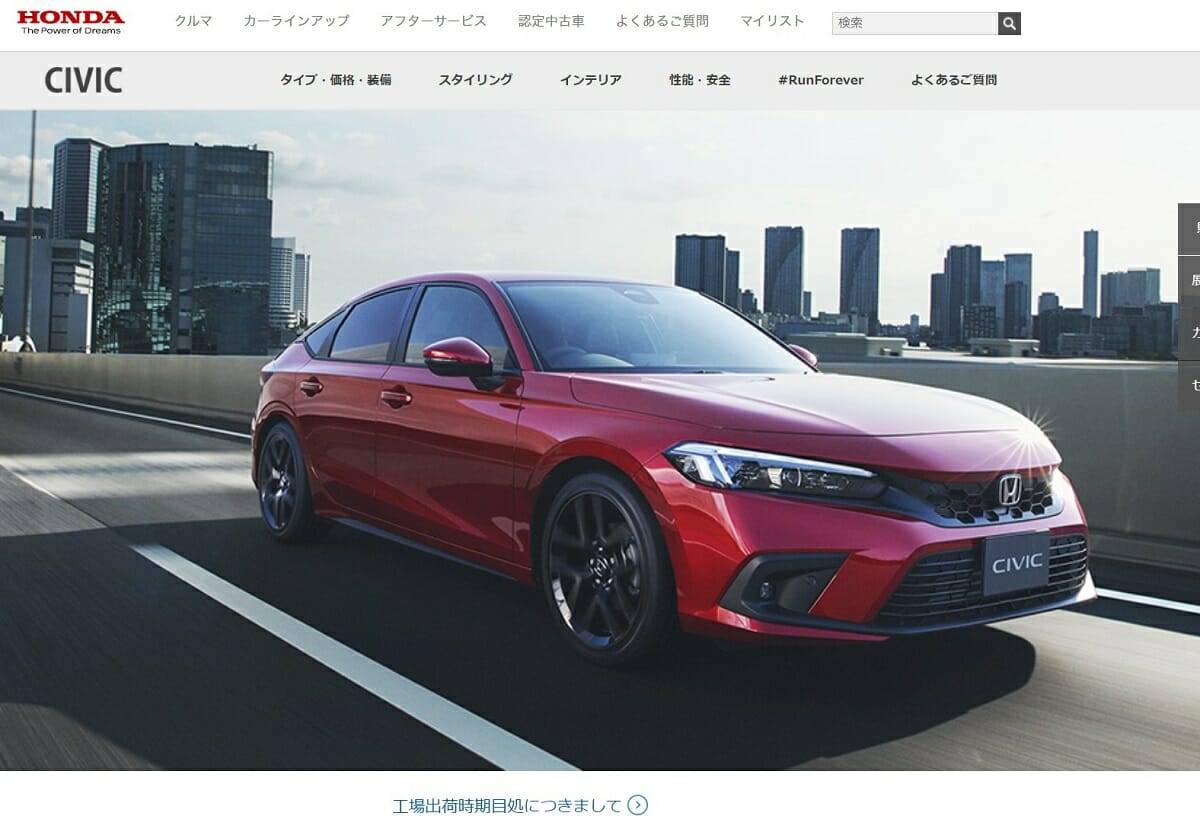
脱エンジン 第二創業ホンダの命運を占う
エンジン技術の頂点、F1を何度も制覇し、エンジン技術で世界を席巻してきたホンダがエンジンをやめる。世界一のエンジン・メーカー、ホンダは本当にエンジンと別れられるのか。
今後のホンダを探るには、「勝負には必ず勝つ」という勝負師の姿と、常に「もっとも厳しい競争に挑む」というチャレンジャーの姿と、「世界初にして世界最高をめざす」というプライドの高さを知らなければならない。それらが脱エンジンのその後のホンダの牽引力だからだ。
勝負には必ず勝つ
ホンダは長らく社運を賭けて強敵と闘い、そして栄光に包まれたF1から撤退する。理由は、「勝てそうもない」からか? そうではない。今期のホンダは、F1のチャンピオン・エンジンのタイトル奪取が濃厚である。勝負には必ず勝ってきたホンダである。メルセデスからチャンピオンの座を奪い取るに違いない。
かつてホンダは、F1の貴公子セナ、そして勝負師のプロストという2人の天才ドライバー擁し、さらに名門チーム、マクラーレンと組んで連戦連勝を重ね、何度も世界チャンピオンに輝いた。今回の挑戦はそうした過去の栄光を追ったのか、最初はマクラーレンチームと組んだ。
それが誤算だった。まったく勝てず、手痛い失敗を重ねた。しかし、チームをレッドブルに替えるや、またたくまに優勝。常勝メルセデスのハミルトンを寄せ付けず、タイトル奪取に向けて走り続けている。ホンダは勝負には必ず勝つ。それが流儀だ。
こうした勝負魂が培われたのは、ホンダの屋台骨になっている二輪の世界であった。失敗を重ねながらも二輪の世界GPを席巻した。世界一厳しいコースといわれるマン島(英国)のTTレースも制した。
その勢いをかって、まだ軽自動車しかつくっていなかったにもかかわらず国内メーカーとして初めてF1 GPにチャレンジした(1964年)。そしてわずか2年目の65年の最終戦、メキシコGPで経験豊富なヨーロッパ勢を尻目に優勝した。バイクのエンジンを横に12基並べた「横置きV型12気筒エンジン」という大胆な技術での優勝だった。二輪GPで鍛えた技術であった。
勝負には必ず勝つというホンダ・スピリットである。
環境技術でも勝つ
自動車の性能は、走る性能と扱いやすさの性能でほぼ決まる。ここに「環境性能」が加わったのは、自動車の誕生から半世紀ほどたってからであった。
自動車が急激に増えた米国の都市では、戦前から排ガスによる大気汚染が問題になっていた。とくにカリフォルニア州では1943年にはスモッグが発生し、「ロサンゼルス・スモッグ」と呼ばれるようになっていた。ペンシルバニア州では、1948年に発生したスモッグによって20人が死亡したといわれる。
やがてスモッグと自動車排ガスの関係が認識されるようになり、1959年に自動車排ガスに規制が設けられるようになり、1965年にエドモンド・マスキー上院議員(民主党)を中心とした排ガス規制法が提出された。しかし、自動車業界とニクソン政権(共和党)の執拗な攻撃を受け成立が危ぶまれた。
しかも、フォードは「どんな巨額の資金を投じようとも、マスキー法をクリアする自動車は1975年1月1日までに開発できない」と議会に訴えるまでになっていた。マスキー法は1974年春には施行される予定であったにもかかわらずだ。
しかし、数ある世界の自動車メーカーでただ1社、ホンダは違った。「わが社は環境技術(のレース)でも勝つ」と宣言し、その技術である「CVCCエンジン」を発表したのだった(1973年)。ホンダは世界でもっとも厳しいマスキー法と呼ばれた排ガス規制を、名だたる名門自動車メーカーを差しおいてクリアしてみせた。環境技術の開発という勝負でも、やるからには勝つのであった。
CVCCエンジンを積んだシビックを1973年に国内で発売、1974年に米国で審査に通り、75年から米国に輸出を始めた。ちなみにこの時のCVCC認定の担当者が、のちに社長になる福井威夫であった。
エンジンを捨てて勝つ
広報資料によれば、ホンダの三部敏宏社長は、今を「第二創業期」だという。創業者は本田宗一郎である。彼はエンジン技術者であった。たゆまずエンジンを改良することで、今日のホンダをつくった。エンジン(技術)でホンダをつくり、成長させた。これが創業第一期である。
だが、同じエンジン技術者である三部社長は違う。「10年、20年、30年のスパンで考えると、エンジンではホンダは立ち行かない」という。それは、「エンジン技術者だからわかる」ことだという。とことんかかわった分野であれば、その可能性と限界は、はっきりとわかるものなのだろう。
伝統のエンジンでは立ち行かないのであれば、ホンダは変わらざるを得ない。とすれば、「今が改革の絶好のチャンスだ」。そして「エンジンを捨てることで、ホンダの未来を拓こう」と決意したという。第二創業期の始まりである。
何かを手に入れて勝つ勝負もあれば、もっとも大切なものを捨てて勝つ勝負もある。後者は捨てることで退路を断ち、決意を新たに、しかも強固なものにする戦法である。追い込まれると「窮鼠、猫を嚙む」のだ。
とことん議論して、考え抜いて
今、自動車メーカーを襲っている嵐は、1886年に自動車が誕生して初めて遭遇する、とてつもないハリケーンである。2050年の脱炭素は、対立国、友好国の区別もなければ、どんな人種も、どんな年齢の人も、地球人はすべて従わなければならない約束である。
世界で排出される二酸化炭素(CO2)の20%を占める自動車は、変わらなければならない。そして、それが可能なのは2050年までのスパンではEV(電気自動車)である。HEV(ハイブリッド車)含めて、三部社長も言うようにエンジンでは無理である。ホンダにとってEVは、第一創業期を成長に導いたかつてのCVCCなのだ。
つまり、世界の自動車メーカーは、生き残りたければエンジンを捨てるしかない。しかし、エンジンを捨てれば半分近い技術者と労働者と協力企業、部品メーカーを失うことになる。行くも地獄、とどまるのも地獄である。この危機的状況を全社員が共有しなければ、難局は乗り越えられない。では、どうする? 三部社長の答えは「エンジンを捨てる」ことであった。当然、社内は賛否両論が渦巻いたという。社員が危機的状況を共有し始めた。
ホンダには、「わいがや」という議論のやり方があると聞く。関係部署のメンバーが集まり、無礼講で言いたいことを、言いたい放題、言い合うのである。「とことん議論して、考え抜いて、よりよいものを生み出そうというホンダの企業風土」であり、ホンダの原点だと三部社長は言う。
ホンダイズムに基づけば、おそらく議論の結果は、「世界初、世界一をめざし」「必ず勝負に勝って、達成感を味わう」というものではないだろうか。ホンダは、たとえばHEVといった既得権にしがみついたり、これまでの延長上でものを考えたりしない。楽な道を選んでいては、達成感は得られないからだ。達成感は、「もっとも厳しい闘いに勝つ」ことでしか得られない。それはHEVも含めてエンジンをやめることなのだ。
三部社長のめざすホンダ
まず考えるのは「ホンダが企業として持続できるようにするには、どうすればよいか」だという。少なくとも80年代は、その終わりにバブル経済が訪れたこともあり、企業の存続が難しかったことはない。それよりも、どうすればより成長できるだろうかが問われた。決して企業にとって困難な時代ではなかった。
しかし、資本主義が行き詰まったともいわれる現代は、地理的な市場の拡大は望めず、多くの先進国では「ロスト欲望社会」(橋本努北大教授)ともいわれるように、市民の多くから欲望が消えかかっている。自動車に関していえば、先進国ではこれ以上、自動車に欲望することはないだろう。それでも自動車への欲望を駆り立てるべく、「自動運転」やら「つながるクルマ」やらの新技術が用意されているが、果たしてマーケットは動くだろうか。
そうした行き詰まりの時代でホンダを持続させるには、「目先ではなく将来への種まきが必要だ」と三部社長はいう。だが、ホンダにはすでに用意がある。それらが、大きくなるビジネス用ジェット機であり、ロケットビジネスへの参加であり、すでに参入しているボートビジネスの拡大であり、アシモに代表されるロボットビジネスなのではないだろうか。そして、つい先日、発表された中国におけるホンダ・ブランドの新型EV、e:Nシリーズの展開である。
このような新しいビジネスの展開が整ったから、ホンダは脱エンジンを宣言したに違いない。ホンダは「勝負に勝つ」ためにEVにシフトするのであり、その準備は整ったということだ。
(文=舘内端/自動車評論家)










