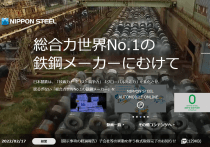脱炭素の国際的枠組みから世界の金融機関が脱退…だが脱炭素が加速する理由

●この記事のポイント
・みずほFGは、金融機関でつくる脱炭素を目指す国際的な枠組み「ネットゼロ・バンキング・アライアンス(NZBA)」から脱退。
・トランプ政権下で、化石燃料産業への融資制限を行うことへの批判が高まり、米国の主要銀行をはじめとする大手金融機関の脱退が相次ぐ。
・米産業界では脱炭素への企業努力がしたたかに続けられている。
みずほフィナンシャルグループ(FG)は3月31日、金融機関でつくる脱炭素を目指す国際的な枠組み「ネットゼロ・バンキング・アライアンス(NZBA)」から脱退した。NZBAは、2050年までに銀行の投融資ポートフォリオの温室効果ガス(GHG)排出量をネットゼロにすることを目指す国際的な金融機関の枠組みだ。近年、アメリカでは共和党議員を中心にNZBAに基づく活動が反トラスト法違反との見方が高まっていた。そして、トランプ政権下で、化石燃料産業への融資制限を行うことへの批判が高まり、米国の主要銀行をはじめとする大手金融機関の脱退が相次いだ。日本の金融機関は6行が参加していたが、みずほFGが脱退したことで、残っているのは三井住友トラストグループのみとなった。この動きは世界的な脱炭素の推進を大きく減速させる可能性はあるのか。専門家の見解を交えて追ってみたい。
●目次
NZBA は、2021年に国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)が主導して設立し、世界各国の銀行が加盟してきた。CO2分離回収・貯留・利用による産業界のカーボンニュートラルを専門とする早稲田大学理工学術院の中垣隆雄教授は「もちろん、決して良い動きではない」としつつ、「瞬間風速に過ぎないのではないか」との見方を示した。
「ファイナンスが引き上げてしまうと脱炭素の機運に水を差す。(脱炭素への投資は)リスクが高いということになるとファーストムーバーがいなくなってしまう。しかし、メガトレンド(大きな潮流)の推進にブレーキはかからない。トランプ大統領は温暖化の懐疑論者を総動員して再びキャンペーンしてくるかもしれないが、今更感がある。世界中の識者は冷静に判断して、やっても大勢は変わらないという感じだ。ただ、脱炭素における技術の優先順位はたぶん変わっていく。そこが大きく変わるところだろう」
中垣教授によれば、国や自治体、企業といった脱炭素のメインプレイヤーがこれまでやってきたような再エネ利用拡大によるデカボナイゼーション(一次エネルギーの脱炭素化)とエレクトリフィケーション(電化)の両輪、これは世界的でどこも同じ潮流だ。再エネや原子力などの非化石電源はその国や地域によって異なる。
「2月に決定された第7次エネルギー基本計画で、原子力の最大限活用を明言したというのは、やはり再エネ導入量のペースダウンとコストを考えたときに、まずはあるものを使わなければ、あと25年しかないCN(カーボンニュートラル)なんて到底間に合わないということだろう。政府としてはCN達成が無理だとも言えないので、技術進展シナリオという表現になった。トランプ政権下では化石燃料を使う産業が少し延命されるだろうと予想する。それはどこの国も同じような事情だという気がしており、例えば、欧州はすべてEVにして内燃機関を全廃すると言っていたが、少しトーンが変わってきた」
CO2を大気中から除去、地下貯留する技術への期待
脱炭素と電源構成を巡っては、日本は東日本大震災以降に迷走しているが、今のところLNG(液化天然ガス)が最適解になっている。しかし、アラスカ産LNGが本当に輸入されるかどうかは別にして、今後もずっとこのままというわけにもいかない。
「経産省はここ数年で、カーボンニュートラルから、カーボンマネジメントという考え方にシフトしている。カーボンニュートラルは目標設定であって、それをどういうふうに管理するのかがマネジメント。2050年までのトランジション期においては、化石燃料を全面的にやめて原子力と再エネとグリーン水素だけでいいというわけではなく、石炭も含めて少し化石を使いつつCN目指すということでマネジメントの考え方になっている。そうなると必然的にいわゆるCCS(Carbon dioxide Capture and Storage:地下貯留)、それから大気中からCO2を除去するCDR(Carbon Dioxide Removal:二酸化炭素除去)、この2つへの期待が高まるだろう」
主なCDR技術には、植林・森林再生、土壌炭素隔離、風化促進、バイオエネルギー炭素回収・貯留(BECCS)、DAC(Direct Air Capture:直接空気回収技術)、OAE(Ocean Alkalinity Enhancement:海洋アルカリ化増強)などがある。2050年まで時間的余裕がないことから、これらの中で中垣教授はDACや工業的な風化促進など,持続的で土地制約の少ないテックCDRと呼ばれる技術が重要だという。また、バイオ炭、海に囲まれている日本ではブルーカーボンなども相対的に重要度が高まるだろうと予測する。ブルーカーボンは海草や海藻などの海洋生態系が吸収する炭素のことで、バイオ炭は木炭や竹炭などのバイオマス資源を材料とした炭化物を指す。
二酸化炭素を回収して地中深くに貯める技術、CCSについては「特定区域」に指定された苫小牧では、2019年に実証事業で30万トンの累積圧入に到達している。経産省は苫小牧以外も特定区域に指定して、2030年度までに全国で600万トンから1200万トンの二酸化炭素を貯めることを目指している。
「国は2050年までの長期ロードマップも描いているが、まずはCCS事業法に則った形でしっかりスタートできるか、2030年までの苫小牧が一つの資金石だ。それができなければ、その後もどんどん遅れる一方でお手上げというか、やっても意味がなくなる。水素活用もかなり遅れているので、カーボンマネジメントの中では、排出されたCO2をどうにかしようという技術のニーズが高まる」
世界最大のCO2排出国、中国の脱炭素の取り組み
これまで脱炭素を先行して推進してきたのは欧州で、米国は民主党を中心にそれに追従してきた。しかし、実際にCO2排出量の多い国(2023年5月時点)は1位が中国、2位アメリカ、3位インド、4位ロシアで5位が日本だ。日本にも大きな責任があるのは間違いないが、「アメリカは1人当たり我々の倍ぐらいCO2を出している」(中垣教授)わけで、地球規模での脱炭素を考えた場合、中国とアメリカが本気で取り組まなければ実効性が伴わない。
中国は世界最大の電気自動車(EV)生産国・輸出国だが、脱炭素への取り組みについて中垣教授はこう話す。
「メタノール生産の世界シェア第一位の中国では、近年CO2と再エネ水素からメタノールを合成することも盛んに進めている。日本で言うところのいわゆるe-fuelを先進的に開発している。そのメタノールを作る技術の一つは、アイスランドのベンチャー企業、カーボン・リサイクル・インターナショナル(CRI)のものだ。同社はアイスランドで豊富な地熱を活用し、クリーンなメタノールを製造していた。よって、カーボンリサイクル燃料も中国はかなり先に進んでいる」
政府の政策に関係なく米国企業は脱炭素に前向き
世界の産業界における今後10年先の脱炭素をめぐる動きを見据えて、どのような企業が生き残っていくのか。
「例えば、水素とかCCU(二酸化炭素回収・有効利用)、CCUS(二酸化炭素の回収・有効利用・貯留)の観点で言うならば、自社のバリューチェーンでいろいろな要素をちゃんと抑えてオールマイティに進められる体力のある会社が強いのは変わらない。日本ではトヨタや三菱重工などは、すべてオールラウンドで技術を持っている。また、自社単独で解決できなくても、米マイクロソフトのようにVCM(ボランタリー・カーボン・マーケット:自主的な炭素取引市場)にて炭素除去のクレジットを調達している企業もある。そういう市場では需要に対して供給が極端に不足しているので、とにかく限界削減費用が少ない技術からどんどん選択するという動きは進んでいる。VCMでクレジットを調達するというのは、たぶん“ポストトランプ”を見越して進んでいくだろう」
VCMは、企業が再生可能エネルギーの導入や植林などによって削減した温室効果ガスの量に応じて「炭素クレジット」を発行し、それを取引する市場だ。温室効果ガスの排出量を1トン削減するのに必要な費用を「限界削減費用」と呼ぶが、米産業界では脱炭素への企業努力がしたたかに続けられている。実際、2017年に1期目のトランプ大統領が、正式にパリ協定からの離脱を発表した際、多くの米国内のリーダーたちは、地球温暖化対策の国際的な努力から手を引くのは科学的根拠に反するとして反対した。「We Are Still In」というイニシアティブも立ち上がった。
2期目のトランプ大統領がどのような政策を打ち出そうとも、産業界における脱炭素の流れは変わらない。
(文=横山渉/ジャーナリスト、協力=中垣隆雄/早稲田大学大学院教授)