恵庭OL殺人事件に冤罪疑惑 有罪ありきのずさんな捜査と裁判に、元裁判官も唖然
●日本の刑事司法は中世並み?
民事訴訟は、多くの場合、双方のストーリーのせめぎ合いであるが、原告のストーリーに相当のほころび、あるいは、一貫した説明を困難にするような事情があり、一方、被告主張のストーリーにそれなりの一貫性があれば、請求を棄却するのが普通である。それは、刑事訴訟でも同じことであろう。その原則をこの事件に当てはめれば、民事訴訟の感覚でも、検察の請求を認めることは難しい。まして、これは「疑わしきは罰せず」の刑事訴訟なのであるから、無罪は当然ではないかという気がする。アメリカの法廷でも、これで有罪はありえないと思う。
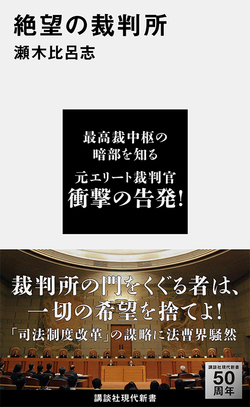 発売から3カ月で6万5000部突破! 司法界、ジャーナリストのみならず、海外まで含めた各方面から絶賛の声が続々と
発売から3カ月で6万5000部突破! 司法界、ジャーナリストのみならず、海外まで含めた各方面から絶賛の声が続々と弁護団(無罪判決の多い元刑事系裁判官として知られ、後に法政大学法科大学院教授も務めた木谷明弁護士も、メンバーに入っている)を含む関係者は、弁護側に好意的と感じられた審理中の裁判長の言動をも考慮し、当然再審開始決定がされるものと予期しており、そのため、先の再審請求棄却決定については、裁判官に何らかの圧力がかかったのではないかとの推測まで出たという。また、木谷弁護士は、決定のあまりのずさんさに失望と怒りを隠さなかったともいう。
考えにくいことではあるが、私は、若いころに、ある刑事系の有力裁判官が「刑事裁判は、導き出した結論によっては、辞めなきゃならんようなこともあるからなあ……」と問わず語りに語るのを聴き、「ああ、刑事は民事とは違うんだ……」と思ったことがあるのを、はっきりと記憶している。刑事の重大事件の背後には、民事系の裁判官であった私にさえ想像もつかないような深い闇が広がっている可能性が、もしかしたらあるのだろうか。
※本稿は、5月16日付「現代ビジネス」(講談社)記事に加筆・修正したものです。
※瀬木氏は、現在、日本の裁判の問題点と裁判官の判断構造を、数々の事例を通じて、体系的に、またリアリスティックに明らかにする『絶望の裁判所第2部』(仮称)を準備中であり、その中でこの事件についても取り上げる予定です。
●瀬木 比呂志(せぎ・ひろし) 1954年名古屋市生まれ。東京大学法学部在学中に司法試験に合格。1979年以降裁判官として東京地裁、最高裁等に勤務、アメリカ留学。並行して研究、執筆や学会報告を行う。2012年明治大学法科大学院専任教授に転身。民事訴訟法等の講義と関連の演習を担当。著書に、『絶望の裁判所』(講談社現代新書)、『民事訴訟の本質と諸相』『民事保全法〔新訂版〕』(ともに日本評論社、後者は近刊)等多数の専門書・一般書のほか、関根牧彦の筆名による『内的転向論』(思想の科学社)、『心を求めて』『映画館の妖精』(ともに騒人社)、『対話としての読書』(判例タイムズ社)があり、文学、音楽(ロック、クラシック、ジャズ等)、映画、漫画については、専門分野に準じて詳しい。










