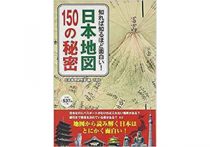アラムコ攻撃で暗雲? サウジ経済改革が抱える根本的問題
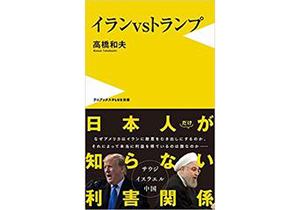
サウジアラビアのアブカイク原油処理施設がドローン攻撃を受け、生産能力に大きなダメージを負った事件は、被害の度合いと犯行主体の断定を巡って紛糾し、まだまだ収束の気配が見えない。
イランと敵対し、サウジアラビアとほとんど盲目的といってもいい友好関係を結ぶアメリカは、イランによる犯行と疑っている。しかし、イランがそれを認めるはずもなく、一方でイエメンの武装勢力「フーシー」が犯行声明を出している。そして攻撃を受けたサウジアラビア側も被害状況を一切明らかにしていないため、全容解明はまだ時間がかかり、そして解明されるかどうかもわからない。
■石油施設攻撃で突かれたサウジアラビアの「急所」
今回の攻撃は、サウジアラビアにとってまさに「急所」を突かれた形になった。それは唯一無二の産業である「石油ビジネス」の要所を攻撃された、というだけではない。
今回攻撃を受けたアブカイク原油処理施設を所有するのはサウジの国有石油会社「サウジアラムコ」である。サウジアラムコといえば、国際市場への上場が(延期されてはいるが)噂され、投資家の注目を集めている中東の注目企業だ。
この上場によって得られる資金によって、サウジは「ビジョン2030」と名付けられた自国の経済改革を実現させようとしていた。今回の攻撃によって明らかになったサウジアラムコの石油関連施設の脆弱性を投資家がリスク要因と評価すれば、サウジのこの計画が狂ってしまう可能性があるのだ。
ただ、この経済改革は上場が首尾よく進み、サウジが目指すだけの資金がえられたとしても、いくつかの疑問符がつくものだ。
元々、サウジアラビアは王族が権力を独占し、資源は一度国がすべて吸い上げた上で、国民に分配するというある種の「福祉国家」である。国民は政治に口を出さない代わりに、無料の医療、教育、住宅、電気、ガス、石油などを享受できる。もちろん税金もない。
ただ、この国の収入はほとんどが石油関連ビジネスによるものだ。原油の価格が低い状態が続くと財政が苦しくなる。だからこそ、サウジアラビアは経済改革を行い、石油依存体質から脱却しようとしている。これは国の経済構造を根本から変える大手術であり、当然国民にも変化が求められる。
放送大学名誉教授である高橋和夫氏は『イランVSトランプ』(ワニブックス刊)で、この経済改革の課題の一つに「国民への十分な雇用の提供」を挙げている。
端的に言えば、サウジは国民を働かせたいのだが、これがなかなか一筋縄ではいかない。海外から投資を呼び込んで大規模な雇用創出をはかりたいという狙いとはうらはらに、現段階では外資はサウジへの投資に及び腰なのだ。
またもう一つ、高橋氏が指摘しているのが「納税と政治参加」の問題である。もし国民が労働し税金を納めるようになったとしたら、その税金の使い道に口を出す権利を求めるようになるのではないか。つまり、国民から政治参加を求める声が上がるのではないか。それこそは、サウジ王室がおそらくもっとも恐れていることであり、同時に経済改革が内包する、サウジアラビアという国家を崩壊させかねない課題なのだ。
◇
『イランVSトランプ』は、今回の攻撃が突発的に起こったものではなく、イランとアメリカの長い対立関係の歴史に導かれたものであることを明らかにする。そして、この問題がイランとアメリカの二国間の対立ではなく、サウジアラビアやイランといった中東のアクターを含みこんだ規模の大きな問題であること、この問題が今に至った経緯についても詳述されており、世界情勢のホットトピックであるイラン問題を理解するために役立ってくれるはずだ。
(新刊JP編集部)
※本記事は、「新刊JP」より提供されたものです。