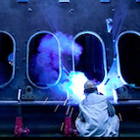ホンダジェット(画像提供:ホンダ)
ホンダジェット(画像提供:ホンダ)
ホンダは、小型ビジネスジェット機「ホンダジェット」の開発を進めてきた。当初、「“二輪屋”のホンダに、飛行機をつくれるはずがない」というのが、世間の見方だった。それはそうだろう。富士重工業やロールスロイスなど、母体が航空機エンジンメーカーの企業が自動車をつくった例はあっても、自動車メーカーが航空機をつくった例はかつてない。
また、航空機産業では、機体とエンジンの開発・生産のすみ分けが進んでいる。ボーイングのような航空機メーカーは、航空機エンジンを生産していない。ホンダのように、両方の開発・生産を手掛ける民間企業は、世界に例がない。この事実からしても、ホンダはじつに不思議な会社である。
しかも、不思議なことに、「ホンダなら、本当にやるかもしれない」という期待を抱かせる何かを持っている。なぜだろうか。それは、ホンダのDNAともいうべき「夢」への挑戦にあるだろう。
ホンダの不思議についていえば、普通、ジェット機のエンジンは、左右の主翼の下、ないしは胴体後部左右に搭載されている。ところが、ホンダジェットは左右主翼の上にエンジンが搭載されているのだ。主翼上にセットすれば、乱気流が生じ、非効率とされる。にもかかわらず、ホンダは業界の常識を覆した。不思議なスタイルである。
しかしその結果、ホンダジェットは、ライバル機に比較して最大巡航速度は約10%向上の時速778km、実用上昇限度は約5%向上の約1万3100m、燃費性能も数値こそ発表されていないが約20%の向上を実現。客室の広さも、約18%向上の高さ1.46m、幅1.52m、長さ5.43mであり、パイロットを含めて7人乗りである。そのホンダジェットは今、離陸に向けた秒読み段階に入っているのだ。
●技術革新を見据えた長期的経営視点
ジェット機の開発は、そもそもホンダ創業者である本田宗一郎の「夢」だった。1917年、当時10歳だった宗一郎は、米飛行士アート・スミスの曲芸飛行を見ようと、自宅から20km以上離れた浜松練兵場へ自転車で向かった。手持ち金不足で入場できなかったために、木に登ってそれを鑑賞した。以来、飛行機に憧れ続けたというのは、あまりにも有名な話だ。
それから45年を経た62年、二輪レースの世界最高峰マン島TTレース(イギリス)で前年に初優勝するなど勢いに乗るホンダは、朝日新聞が掲載した「国産軽飛行機 設計を募集」の広告に協賛した。そして同年、宗一郎は社内報で「いよいよ私どもの会社でも軽飛行機を開発しようと思っております」と発言している。
ただ、宗一郎の決意があったとしても、航空機の開発はそんなに簡単なことではない。ホンダが航空機の開発に正式に取り組むのは、それから24年後の86年である。
ホンダは同年、「和光基礎技術研究センター(基礎研)」を極密に開設した。その2~3年前からテーマの模索が行われていたが、その際、シェア一番になることより、技術の新規性、進歩性においてトップになることこそホンダが追求すべき道だ――と考えられた。つまり、10から20年先の技術革新を見据えていた。長期的経営視点である。
選ばれたテーマは、航空機エンジン、航空機体、ロボット、バイオエタノールやソーラーを使う次世代エネルギーの4つで、いずれも極秘開発プロジェクトとしてスタートした。二足歩行ロボット「ASIMO」の開発も、そのときに始まったのだ。
航空機エンジンの開発のため、若手技術者数名が集められた。極秘研究というので、開発者たちは10年以上にわたって家族にすら研究内容を話すことが許されなかった。これも、不思議を通り越してクレイジーな話といわなければならない。エンジンに必要な材料チタンにしろ、専用ベアリング1つにしろ、業者に用途を伝えられなかったり、しかるべきメーカーに発注ができなかった。秘密保持の苦労は続いた。