学校の国語教育が、どうやら文学より契約書などの「実用文」メインになりそうだ

「Getty Images」より
著名な作家の小説や詩を鑑賞し、鋭い文化評論で視野を広げる。国語の授業というのは、私たちにとってそのような場だったはずだ。それが事務的な文書を読む訓練の場になるとしたら、恐るべき教育改革というべきではないのか。本当にそんなことになるのだろうか。
国語の授業で実用文を学ぶ時代に?
国語の授業で夏目漱石の『こころ』を読んだ記憶のある人が多いのではないか。大学の推薦入試の際に、自己アピールの文書に「趣味は読書」と書いてある受験生が目立った。そこで、面接の場で「最近はどんな本を読みましたか」と尋ねると、ほとんどの受験生が「夏目漱石の『こころ』です」と答える。他にどんな本を読んだかを尋ねると答えられない。突っ込んで聞いてみると、『こころ』も国語の教科書で読んだだけで、ごく一部しか知らないという。
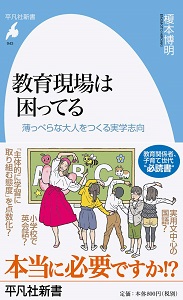
これではとても趣味が読書とはいえないが、どんなに読書に縁のない人物でも、学校の国語の授業を通して文学にちょっとでも触れているというのは、とても貴重な経験なのではないだろうか。
高校2・3年生用の「現代文B」の教科書では、芥川龍之介や森鴎外、宮沢賢治、中島敦、井伏鱒二、萩原朔太郎など、文学史に名を刻む作家たちの作品が載っている。ごく一部にしても、読んだことがあるというだけでも親しみが湧くし、何かのきっかけでちゃんと読んでみようと思うこともあるかもしれないし、ちょっとした話題についていくことくらいはできるだろう。
だが、学校の国語の授業でほとんど文学に触れることがなくなり、契約書や取扱説明書などの読み方を中心に学ぶようになったら、ふだん読書をしない人は、文学にほとんど触れない人生を送ることになる。
それは非常に淋しいことである。それに加えて、実用文のような平坦な文章ばかり読むのでは、作者の言いたいことを読み取ったり、登場人物の心理を読み取ったりといった高度な読解の鍛錬が行われず、人の言うことやその背後の気持ちを読み取ることのできない読解力の乏しい人間になってしまうのではないか。
でも、まさか国語の授業が文学の読解から実用文の読解の場にシフトされるなど、あり得ないと思う人が多いかもしれない。だが、じつはその可能性が高まっているのだ。
大学入学共通テストで駐車場契約書が出題
昨年末、英語の入試問題の民間試験利用が白紙撤回され、国語や数学の記述式問題の導入が見送られたことで、大学入試改革はますます混迷を極めることになった。そのような状況下においても、入試改革は着々と進行している。
これまで行われてきたセンター試験が廃止になり、それに代わって大学入学共通テストが導入されるのは2021年であり、数カ月後に迫っている。そこでは、これまでと違ってどのような問題が出るのか。それは、受験生にとっても教育関係者にとっても重大な関心事である。
そこで、新たに導入される大学入学共通テストのモデル問題が2017年に提示されたわけだが、国語の問題をみると、あからさまに実用文が出題されたのである。ある自治体の「『街並み保存地区』景観保護ガイドラインのあらまし」という文書をめぐる問題が出題され、「駐車場利用契約書」をめぐる問題までが出題されたのだ。
ここまでの実用文が出題されるとは予想もしていなかったのだろう。教育関係者の間に衝撃が走った。私にとっても想定外の問題だった。学校の国語の授業といえば、著名な作家の小説を味わうことで人生について深く考えたり、詩歌の鑑賞によって心を豊かにしたり、評論を読んで社会を見る目を養ったりするといった印象がある。国語が自治体の広報文や駐車場契約書の読み方を学ぶ教科だといった認識はなかった。
だが、大学入試でこのような実用文が出題されるなら、これからの国語の授業はそれに対応せざるを得ない。しかし、それでは何とも味気ない授業になってしまう。
こうした動きを受けて、日本文藝家協会は、国語改革に関して問題提起する表明を出し、「実学が重視され小説が軽視される」「国語教育は実用的な力をつけるための内容に変えるべきだという意見が強まり、結果として大学入試問題や教科書から文芸作品が減っている」とし、「おそらく戦後最大といってもいい大改革であり、日本の将来にとって大変に重要な問題をはらんだ喫緊の課題」であり、この流れをより良い方向に修正するために一丸となって取り組んでいくとしている(文藝家協会ニュース2019年1月号より)。
新学習指導要領により、実用文を盛り込んだ教科書を使うようになる?
いくらなんでも、そんな改革が行われるはずがないと思われるかもしれない。だが、2022年の高校1年生から年次進行で順次適用される高等学校学習指導要領によれば、それは杞憂ではないのだ。分厚い資料なので、ごく簡略化すると、これまで高校2・3年生が学んできた「現代文B」という科目が「論理国語」と「文学国語」に分かれ、いずれかを選択することになる。
学習指導要領によれば、新たな科目である「論理国語」では、論説・評論・学術論文などの論理的な文章のほかに、報道や広報の文章、案内、紹介、連絡、依頼などの文章、法令文、キャッチフレーズ、宣伝の文章などの実用的な文章が盛り込まれることになっている。
大学入試で実用文の読解問題が出題されるなら、文学を鑑賞したりするよりも、実用文を中心に論理的に読解する授業をせざるを得ない学校が多くなるだろう。その場合、「文学国語」でなく「論理国語」の教科書で学ぶことになる。それにより、従来は文学史に名を刻む文学作品に国語の授業を通して触れていた高校2・3年生が、そうしたものに触れずに実用文中心の授業を受けることになる。
これまでの国語の授業では、小説や詩を鑑賞したり、評論や随筆を読んで作者の言いたいことを読み取ろうとしたりすることで、想像力や思考力が鍛えられるとともに、深い教養を身につけることができた。だが、広報や契約書など実用文の内容を理解しようとする授業になってしまったら、そうした知的鍛錬にもならなければ教養を身につけることもできない。
実用文が読めないのでは社会に出てから困るというのはわかる。ただし、国語の授業は、実用文の読解ができるようにすること以上の役割を担ってきた。大学入学共通テストの出題者も、新学習指導要領を元にした新たな教科書の作成者も、こうした事情を踏まえて、実用文をしっかり理解できる程度の読解力を身につけるのは最低限の目標とし、それ以上の読解力の鍛錬の場にすべく、国語の授業の質を落とさないような工夫をぜひお願いしたい。
(文=榎本博明/MP人間科学研究所代表、心理学博士)











