中国、内側からの解体…大量破産に備え法整備を検討、民間の利払い額が過去最高水準
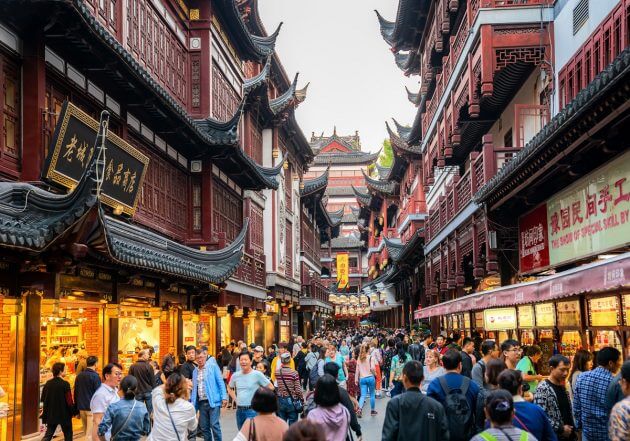
「日本と韓国は米国のために自国の利益を犠牲にしてはならない」
このように主張するのは、中国国営メディア「環球時報」の3月16日付記事である。米国のブリンケン国務長官とオースティン国防長官が日本と韓国を相次いで訪問し「同盟関係」を誇示する姿勢に中国当局が警戒感を募らせるなか、中国国営メディアが日米韓の足並みを攪乱させる動きに出始めている。中国と尖閣諸島や黄海周辺で軍事的な緊張を高めている日本と韓国に対して「中国との経済的メリットをないがしろにしてはならない」と強調しているのである。
米国では中国に対する不満が急速に高まっている。米ピュー・リサーチ・センターが2月上旬に実施した米国内での世論調査によれば、70%が「中国との経済関係が悪化しても、中国における人権を促進すべきである」と回答した。米国民は中国に対して経済よりも人権問題を重視しており、党派色が強まっている連邦議会でも同様である。
ブリンケン国務長官は就任時のビデオメッセージで、ナチスによるホロコーストの生存者である義父を紹介したように、人権問題に対して強い信念を持っているといわれている。しかし前述の世論調査では、「中国への対処」に関して肯定的に回答したのは53%にとどまっており、新政権の対中国外交の期待値がそれほど高くないことを示唆している。
新疆ウイグル自治区で「ジェノサイド」が行われているとする米国の主張に対し、中国外務省の報道官は10日、「我々は過去40年でウイグル族の人口を555万人から1200万人へと2倍以上に増加させたが、米国はインディアンの人口を1492年の500万人から20世紀初めには25万人へと95%も急減させた」と反発した。
このように、中国に対して「人権が最も重要」とのメッセージを送るだけでは、中国に行動変容を起こさせることは困難である。米通商代表部(USTR)は1日に発表した通商政策の年次報告書で、「新疆ウイグル自治区での強制労働への対処が最優先課題の一つになる」ことを明らかにしたが、バイデン政権は今後、中国に人権重視の行動を執らせるために制裁に踏み切り、日本に対しても協力を求めてくる可能性がある。そのとき日本は、経済よりも人権をはじめとする安全保障問題を優先できるのだろうか。
人口減と負債増大
中国は3月上旬、第14次5カ年計画を発表した。「双循環(外需と内需を組み合わせる)」という新しい概念が盛り込まれ、「2035年までに1人当たりのGDPを中等先進国並みに引き上げる」との長期目標が掲げられた。各国のシンクタンクがこのところ「2030年頃に米中の経済規模が逆転し、中国が世界最大の経済大国になる」との予測を出しており、日本でも「既に日本の対中貿易は対米貿易を上回っており、中国と距離が近い日本はいやおうなく中国経済圏に引きずり込まれていくだろう」との論調が出てきている(3月16日付ニューズウィーク)。
一方で「中国は米国を抜く経済大国にはなれない」との主張もある(2月22日付ニューズウィ-ク)。2月20日付コラムで述べたように、「人口動態の逆風が足かせになる」というのがその理由である。アリババが最大株主であるサウスチャイナ・モーニング・ポストは4日、「中国が直面する深刻な課題は『人口減』と『負債増大』である」と報じた。中国政府は2月18日、「黒竜江、遼寧、吉林3省で先行して産児制限の撤廃を検討する」と発表していたが、3月上旬の全国人民代表大会では「空巣青年の数が直近3年間で約1500万人増加し9200万人になった」との報告が政治局からなされた。空巣青年とは独身ひとり暮らしの若者のことである。
李克強首相は5日に行った政府活動報告の中で「2021年から2025年にかけて年金の支給開始年齢(現在、男性60歳、専門職の女性は55歳、一般職の女性は50歳)はを段階的に引き上げる」方針を示した。少子高齢化に伴う労働力不足を補う措置だが、国内では反発の声が早くも上がっている。
全人代では今後予想される「大量破産」を想定した破産法の整備なども議論されている。全人代の開催中に中国の株式市場が下落するという異例の事態が起きたことについて、「習近平国家主席のメンツを潰すために反習近平派の大物が嫌がらせを行った」との噂が流れている。2月17日付米ウォール・ストリート・ジャーナルは「アリババ傘下のオンライン決済会社アントの株式上場を政府が中止させたのは、同グループの主要株主である江沢民派の存在を警戒したからだ」と報じていたが、株式市場をめぐって権力闘争が繰り広げられているとすればただ事ではない。
陰謀論的な話は置くとしても、「世界的に金利上昇が起きていることで中国の民間部門の推定利払い額の名目GDP比率が過去最高水準に達している」との分析がある(相場研究家の市岡繁男氏)。破竹の勢いで成長してきた中国経済だが、潜在的なリスク要因が目白押しなのである。
「安全保障面では米国との関係を強化し、中国経済の恩恵を引き続き享受する」とする日本の方針がいつまで通用するかわからないが、「最善の対中政策は何もしないことだ」とする醒めた見方もある(3月8日付ニューズウィーク)。「21世紀に入り経済は5倍に膨れあがった中国が新たに築いた対外関係の多くは当初希望に満ちていたが、今では敵対関係に変貌している」とした上で、「静観していれば中国はますます孤立し、その原因は自らにあると気づくかもしれない。中国の体制は米国が打倒できるものではなく、内側から解体するのを待つ」とする戦略である。
いずれにせよ、やっかいな隣人となった中国への対応は、その時々の状況に応じた柔軟なものにならざるを得ないだろう。長期戦の覚悟が必要である。
(文=藤和彦/経済産業研究所コンサルティングフェロー)











