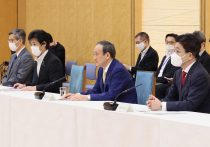CAを相互監視制度で締め付け…ANA、連綿と続く“人事評価制度”と“労使一体”の実態

ANAホールディングス(HD)の中核企業、全日本空輸(ANA)で労使が完全に一体化し、現場からの問題点や批判の声が経営に反映されるのが非常に困難な状況にあることは、連載第18回で詳述した。今回はANA労働組合(ANAユニオン)で役員となるのが出世コースとなってきたことや、1992年に導入された人事評価制度の結果、社員同士が相互監視し合う社内風土が出来上がった経緯について報じる。
ANAはユニオン役員が出世コース、ANAHDの会長と役員も幹部経験者
労使が一体となったANAでは、ユニオン役員を経ることが出世コースだ。実際に、現ANAHD会長の伊東信一郎氏は元副委員長、元ANA社長の篠辺修氏は元委員長、また、2021年から執行役員になった塩見敦与氏は元副委員長だ。現ANAHD社長の片野坂真哉氏が組合の主要幹部を経験していないのは「当時珍しかった東大出身者で、汚れ仕事を長くさせないように配慮があった」(ベテラン社員)ことが要因という。
実際、昨年9月にユニオンの全国大会が開かれた際、ANAの平子裕志社長が「特別来賓」として以下のような挨拶をしている。
「労働組合が果たす役割は非常に重要であり、経営チェック機能を果たすと同時に、組合員の声を聴いて、我々に届けてくれることを期待している」
「(筆者注:組合役員に期待することとして)『対話』 にはふたつの意味があり、ひとつは『経営者との会話』、 もうひとつは『組合員との会話』である。組合員を誰ひとり取り残すことなく、一体感を醸成しながら、スピーディーな行動をお願いしたい。そのために我々も単なる報・連・相にならないように尽力する」
「どのような時代でも、価値を生み出すのは 『人』である。私たちは『挑戦』のDNAを刻み込まれている。挑戦のDNAでこの難局を乗り越え、有望な未来を語っていきたい。苦しい時期が続くが『将来有望』を実現するために、今こそ踏ん張り、知恵と勇気を発揮していこう」
ANAユニオンが経営チェック機能を果たしていない点は、この連載でたびたび指摘した通りだが、CAがSNSに匿名で投稿しただけで数時間も密室で説教され懲戒処分を受けるような現状で、経営者と組合員が対等に「対話」できる雰囲気が生まれるのかは疑問である。
なお、ANAユニオンの全国大会でANAの社長が挨拶する慣例が始まったのは、大橋洋治相談役が社長を務めた2003年からだ。大橋氏は当時200億円の大型人件費削減を実行したが、組合員を前にして「明るく、ニコニコ、コストカットに取り組もう」と発言し大顰蹙を買ったのは、社内では知られた話である。
92年の人事評価制度導入が相互監視を強めた
労使一体が1986年にANAが初めて国際便を就航させて以降、急速に進んだことはすでに書いたが、社員、特にCA(客室乗務員)に関する締め付けが厳しくなったのもこの頃だ。特に、長らく旧運輸省次官経験者の天下り先だったANAで、生え抜き社長が続く流れを決定づけた故普勝清治氏の時代に定着した人事評価制度である「目標チャレンジ制度(MBO)」が、絶大な効果を発揮した。93年から97年までANA社長を務めた普勝氏は、92年から導入されたこの制度を社内統制に利用した。
バブル崩壊直後の当時、日本企業ではそれまでの年功序列制度を維持することが困難になり、成果主義による人事制度が広がったが、MBOもその一つだ。社員は勤続年数の長さではなく、仕事の成果に応じて給与や昇格を決定することになるため、モチベーションが高まるといったメリットもあるが、成果主義の人事制度を2000年代に入り見直す企業が続出した。以下はある経営コンサルタントの解説。
「結局のところ、『成果』というのが何で、それを誰が定義するのか、というところが曖昧すぎて社内の空気を悪くしたり、日本的なチームワークを潰したりして企業の競争力が低下するケースが増えたということに尽きます。企業側も基本的には人件費圧縮のための方便として導入した側面が大きかった。日本社会が米国のような個人型競争主義に馴染まなかったという文化的な側面もあるでしょう。
特にANAのような交通インフラ系企業の場合、営業といったわかりやすく数字で『成果』がわかるところ以外のCAのサービスやパイロットの運行状況、整備の巧みさなどの部分は数字で捉えにくい。こうなると、上司が自分の点数を稼ぐために部下に役割を割り振り、成果を『数字』で示す傾向が強まり、余裕のあるサービスというよりは杓子定規なサービスや本来必要のないコスト削減のようなものがまかり通ってしまったとしても不思議ではありません」
30年前からの恣意的な人事評価制度による統制が現場の疲弊を招いた
評価基準が曖昧だということは、管理職の恣意的な運用がまかり通る組織風土を定着させてしまったということでもある。以下は当時をよく知るANAのOGの証言。
「現場が何か建設的なことを言おうとすると、『身分をわきまえろ』というようなことを言われるようになり、上意下達の言論統制が異常に強まった。評価は管理職が決めるので、うかつな発言をしないようになり優等生的に振る舞うことが暗に要求された。目をつけられた職員は村八分のような扱いを受けるようになり、御用化した組合に頼るわけにもいかなかった。80年代まではANAは国内線だけで余裕のある家族的な社内風土だったが、完全にそれが失われてしまったと感じた」
これと同様の証言を複数のANAのOBとOGから得ているが、97年に出版された『全日空は病んでいる』(田中康夫/ダイヤモンド社)にも同様の内容の記述が出てくる。ヨイショ本も多いANA関連本のなかで珍しくANAに批判的な本だが、同書内の記述をいくつかご紹介しよう。
――以下、引用――
・選別。その基準は曖昧模糊で疑心暗鬼が生じる
・上意下達
・「風通しの良いアットホームな社風」は全日空の身上ではない
・現場を見ようとしない本社族の覇権主義、事なかれ主義
・言論統制
・会社の方針に批判は許されない
・サービスをいかに良くするかを話すとアカと呼ばれる
・意見を言っても変わらない雰囲気が蔓延
・人を「売って」偉くなる体質
・91~92年くらいから変質していったような気がする。人が人を管理する体制が隅々まで行き渡った
・組合の意見と本社の企画室の意見が全部一緒
――引用ここまで――
本連載でたびたび指摘してきたポイントとまったく同じで、ANAの現在の体質は90年代から約30年も続く根深いものであることをうかがわせる。
ANA、CAに「品質」を90年代から要求する人権感覚、恣意的な評価制度で統制
少なくない日本企業が成果主義の人事制度から撤退するなか、ANAは逆に現在でも労務管理に徹底的に利用していることは、連載第1回で報じた通りだ。ANAのCAの労働現場では、戦前の隣組のような「班」による相互監視や、評価者(班長や管理職)の評価による格付けによって本給や乗務手当を決める制度が採用されている。評価項目として「お客様の心に残る笑顔の発揮」「日本らしいおもてなしの心を感じる対応ができる」「安心感や新鮮さを感じるサービスができる」など、主観的で抽象的な基準が盛り込まれており、これでは評価者の機嫌を損ねることなどできない。
なお、90年代にANAはCAに対して「一人ひとりの品質をより高めていく」という方針を打ち出したが、本来モノに対して使われる「品質」という言葉を人間に当てはめている時点で、人権感覚が希薄な様子がうかがえる。それが現在まで続いて、CAの平均勤続年数が6年半という超短期間にとどまり、「眼鏡NG」「妊娠したら一足飛びに無給休職」といた状況を生んでいる。
田中康夫氏「ANAは中身のスカスカのゴボウ」と著作で指摘
この本の中で田中氏は、普勝氏が「ハイクオリティー・ローコスト」の「競争力のある体質」に向けた社内改革を推進した結果、「ロークオリティー・ローモラール」の「競争力なき現場の疲弊」を生んでしまった現実も看過すべきではない、と指摘している。その上で、田中氏は以下のようにANAの体質を批判する。
「中身がスカスカのまま伸ばそうとしているゴボウみたいなものなんだ。現場がその隙間を埋めようと、サーヴィスの向上で頑張っているのに、そんなことには目もくれず、背丈を伸ばすことばかりに夢中になっている」
これは現在のANAグループ全体にも当てはまることだろう。「アジアNo.1」「世界No.1」という「中身のスカスカのゴボウ」の背伸びは続いているからだ。現場の福利厚生などの人件費や整備コストなどを削減して生み出したカネを「国際線至上主義」「打倒JAL」に徹底的に集中させるという普勝氏が敷いた路線は、現在のANAHDの片野坂社長をはじめとしたANAグループ経営陣に至るまで連綿と受け継がれている。
普勝氏は97年に社長を退任してからも相談役として社内に隠然たる影響力を持ったとされるが、2000年代に入って実質的に普勝路線を継いだのは、ANAのカリスマ経営者とされる現相談役の大橋氏である。大橋氏は社長時代に国際線を初めて黒字化させたことや、経団連副会長に航空業界で初めて就任したことが対外的な実績とされているが、人件費削減などの労務管理のエキスパートとして「普勝路線」を推し進めた側面について、今後詳報する。
(文=松岡久蔵/ジャーナリスト)