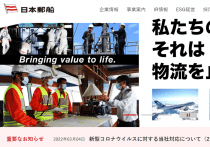日本郵船、空前の純利益1兆円で過去最高益…収益源の多角化に成功

ウクライナ危機などをきっかけに、世界経済が大きな変化の局面を迎えている。1990年代初頭以降、ベルリンの壁が崩壊したことなどをきっかけに世界経済のグローバル化が加速した。国境の敷居は下がり、あたかも世界中が一つの国のように経済活動を行うことが可能になった。その最大のメリットは、各国の経済運営の効率性が高まり、景気が良くなっても物価が上昇しづらくなったことだ。
しかし、ここへきて、米中の対立やウクライナ危機などによって国境の壁が上がり、経済のブロック化などが進む「ディグローバリゼーション」が進み始めたように見える。ディグローバリゼーションは、グローバル化と反対の動きと考えれば良い。世界全体でサプライチェーンの寸断は深刻化するだろう。
そうした状況下、日本郵船が航空運送事業の強化を急ぐなど、収益源の多角化を目指して事業ポートフォリオの変革を加速し始めている。中長期的な目線で見ると、世界経済のデジタル化は加速するだろう。陸海空での物流需要が高まることはあれど、減少基調に転じる展開は想定しづらい。その一方、物価高止まりの懸念上昇など世界経済を取り巻く不確定要素は増える。設備投資に慎重になる、あるいは減らす企業は増えるだろう。リスク管理を徹底し、成長期待の高い分野に経営資源をよりダイナミックに再配分できるか否かが日本郵船の今後の事業展開に大きく影響するとみられる。
過去最高益を更新した日本郵船
現在、日本郵船の業績は絶好調だ。2022年3月期の売上高は2兆2807億円に達し、前年から6723億円の増収で、純利益は前期比約7.2倍の1兆91億円と過去最高益となった。だった。その背景の一つには、コロナ禍の発生によって世界経済全体で人の移動(動線)が寸断され、物流が逼迫したことが大きい。特に、世界の工場としての地位を発揮してきた中国において感染が再拡大したことによって、上海など世界的な規模を誇る港湾施設の稼働率が低下した。それによってコンテナの積み下ろしや輸送が停滞し、貨物船の稼働率も落ち込んだ。さらに、中国内外で接触を避けるためにトラックの運転手や船員の不足も深刻化した。その結果、世界のタンカー輸送などの目詰まりが深刻化し、海運市況が逼迫したのである。コンテナ船などの料金が跳ね上がり同社の業績は拡大基調だ。
米国の物価の上昇ペースが幾分か鈍化する兆しが出てはいるものの、世界経済の現状はかなり深刻と見るべきだ。日本郵船が公表している海運市況データによると、中国から欧州、米国向けの定期船運賃は幾分か調整はしたが高値圏で推移している。共産党政権がゼロコロナ政策を続ける姿勢であることを考えると、中国から欧米向けの定期船市況は逼迫した状況が続くだろう。それに加えて、ドライバルク船(鉱山資源などの乾貨物を梱包せずに輸送する貨物船)の市況も反転基調だ。ウクライナ危機の発生はそのきっかけの一つとなった。そうした要素を背景に2022年3月期の定期船事業の経常損益は7342億円と前年から5934億円増だった。
それに加えて航空運送事業も堅調に推移している。半導体など重量が軽く、小さく、かつ単価が高い製品を迅速に輸送するために航空貨物へのニーズは急速に高まっている。例えば、韓国ではコロナ禍による旅客需要の落ち込みに対応するために大韓航空とアシアナ航空が貨物事業の強化に集中した。2021年の大韓航空の単独営業利益は前期比6倍も増えた。急速な空運需要の高まりを背景に日本郵船でも航空運送事業の経常損益は740億円と前期から407億円増加した。
ディグローバリゼーションがもたらすビジネスチャンス
今後の業績に関して、日本郵船は慎重だ。2023年3月期の経常損益は7600億円と前年から2431億円の減益予想だ。経営陣は2022年3月期の業績は世界的な海運などの物流市況が一時的かつ急速に引き締まった結果と考えているだろう。ある意味では、追い風参考記録という認識があるように見える。それに加えて、ディグローバリゼーションの加速によってエネルギー資源や穀物などの価格が高止まりし、世界経済全体で成長率は低下する恐れが強まっている。
注目したいのが、その状況下、同社が収益源の多角化に取り組んでいることだ。その一つが、航空運送業の強化だ。事業の運営方針として、先行きの不確定要素に対応しつつも、日本郵船はディグローバリゼーションがもたらすサプラーチェーンの寸断深刻化などをビジネスチャンスに変えようとし始めたように見える。
1990年代初頭、冷戦の終結によって世界経済全体で国境の敷居が下がった。中国など新興国企業への技術移転も加速した。その結果、世界の企業は、より生産コストの低いところでモノを生産し、高価格で販売できる国に供給する体制をより迅速に整備できたのである。その裏返しとして世界全体でジャストインタイムのサプライチェーンが整備された。グローバル化によって世界経済の効率性は高まった。
しかし、米中の対立やコロナ禍の発生、さらにはウクライナ危機に加えて台湾海峡の緊迫化など複合的な要因によってグローバル化とは逆の動き=ディグローバリゼーションが加速している。その結果、毛細血管のように張り巡らされたサプライチェーンの寸断が深刻化している。その状況下、米国は半導体などの国内生産の体制整備を急いでいる。ただし、その実現には時間がかかる。半導体や画像処理センサなど高付加価値型の製品をより早く輸送するために航空貨物への需要が増えている。そうした需要を日本郵船はより多く、より効率的に取り組むために航空運送事業を強化している。それは、海運事業への依存度を引き下げ、業績の安定感を高めることに資すだろう。
加速する事業運営体制の変革
このように考えると、2023年3月期の収益見通しには控えめに見える部分がある。航空運送事業以外の分野でも、日本郵船のビジネスチャンスは増えるだろう。例えば、自動車の運送に関して、昨年夏のデルタ株による感染再拡大などによって世界の自動車生産が停滞する中にあっても同社の収益は拡大した。現在、半導体など部品の不足によって国内の自動車生産の回復は容易ではない。裏を返せば、潜在的な需要として部品などの輸送体制強化は本邦自動車メーカーにとって喫緊の最重要課題といえる。
ディグローバリゼーションの加速によって、そうしたニーズは多くの業界で増えるはずだ。口で言うほど容易なことではないが、日本郵船はそうした潜在ニーズを見つけ、収益化することにより集中すべき時を迎えている。世界全体でエネルギー資源や穀物の不足も深刻化している。ロシアからのパイプライン輸送によって天然ガスを輸入してきたドイツでは浮体式のLNG設備を急遽導入しなければならないほど、エネルギー不足への危機感が高まっている。世界全体でLNGや穀物の輸送、貯蔵に関するニーズは増えるだろう。
長めの目線で考えると、脱炭素への取り組みも増える。タンカー輸送、航空機の分野で同社が脱炭素への取り組みを進めたり、再エネ事業を強化したりすることは、社会の公器としての存在感を発揮するために不可欠だ。
楽観はできないが、ディグローバリゼーションが加速するとともに、日本郵船のビジネスチャンスは拡大基調で推移する可能性が高い。チャンスを収益に確実につなげるためには、経営陣が事業運営体制の変革を加速させ、新しい取り組みを増やさなければならない。具体的には、海運事業などで獲得した資金を海外企業の買収やより効率的なタンカー、及び航空機の運航システムの開発、再エネ事業などに再配分することが考えられる。それによって同社は急激な世界経済の環境変化に対応し、エネルギーや穀物から半導体などの最先端分野の輸送需要をより効率的に取り込むことができるだろう。
(文=真壁昭夫/多摩大学特別招聘教授)