準戦争行為の場・地球環境問題に裸同然で出ていく日本は、世界中から“批判の的”になる
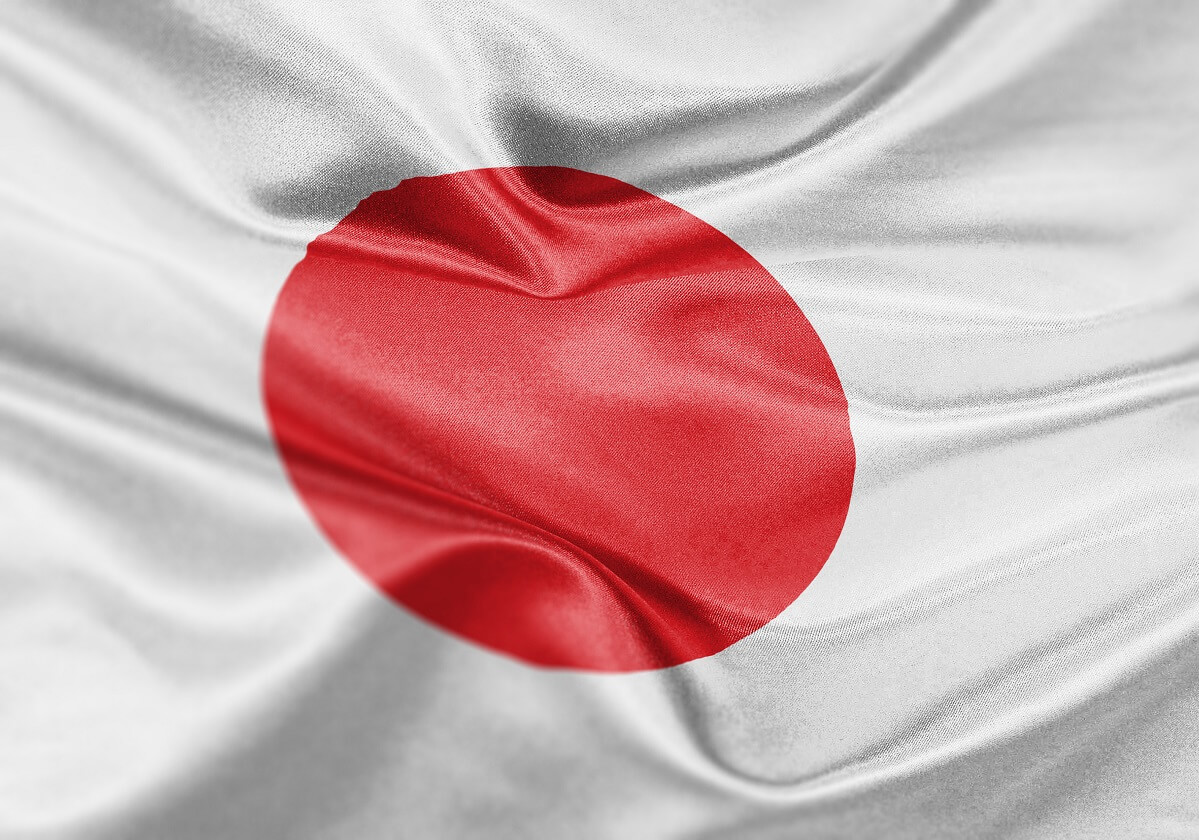
経済産業省が二酸化炭素を大量に排出する低効率な石炭火力発電所の休止を促す方針を固めた。石炭火力にこだわる日本に対しては環境問題を軽視しているとの批判が寄せられており、こうした声に押された格好だ。
国内では脱炭素論について、単なる環境問題としてしか捉えていない人が多く、これが日本の環境政策を誤ったものにしている。地球環境問題というのは、国際社会における冷徹なパワーゲームの場であり、次世代の国家覇権を賭けた権力闘争そのものである。日本では環境問題はタテマエにすぎず、国際社会に対して現実的な提案を行うべきとの考えが主流だが、黒でも白にしてしまう極めて政治色の強い世界に、こうしたナイーブな議論は一切、通用しない。
低効率な石炭火力を廃止しても、政治的には意味がない
日本国内には現在140基の石炭火力発電施設があるが、ほとんどが低効率で二酸化炭素の排出量が多い。気候変動問題が深刻化していることから、国際社会では二酸化炭素を大量に排出する石炭火力への風当たりが強まっている。各国は、温室効果ガス排出削減を定めた「パリ協定」に基づき石炭火力の段階的な廃止を打ち出しているが、日本だけが石炭火力を維持している。
石炭火力の維持に積極的な日本に対しては批判の声が高まっており、国際会議などにおいて日本が矢面に立たされる場面が増えている。今回の決定は一連の批判を受けての決定と思われる。
だが、今回の方針転換だけでは、日本が置かれた状況を好転させる結果にはならないだろう。その理由は、日本の環境政策の基本方針が何も変わっていないからである。今回の決定を受けて、低効率な石炭火力は段階的に廃止されるだろうが、石炭火力そのものは従来と同様、維持されることになる。結果的に脱石炭にはならないので、やはり国際社会からの批判は収まらないだろう。
現時点において、日本以外の国も石炭火力を稼働させているし、日本は二酸化炭素の排出量が突出して多いわけでもない。それにもかかわらず、なぜ日本だけが批判されるのだろうか。その理由は、日本が何の戦略性も持たずに、裸同然で戦場にノコノコと顔を出しているからである。
冒頭にも述べたが、環境問題は国家覇権をかけた争いであり、限りなく戦争に近い行為と考えた方がよい。生きるか死ぬかの闘争の場に、何の装備もなく無邪気に顔を出せば、身ぐるみ剥がされるのは当たり前のことである。では日本の環境政策の何が間違っているのだろうか。それは脱炭素、あるいは脱石油に対する基本的な考え方である。
脱石油が理想論かどうかなど、権力闘争の場ではどうでもよいこと
現時点において、完全に脱石油を実現するのは困難であり、理想論に近い面があるのは事実である。だが、ここ数年で状況は大きく変わってきた。気候変動の問題が深刻化したこともあるが、もっとも大きいのはテクノロジーの驚異的な進歩である。
日本にいるとあまりピンとこないかもしれないが、再生可能エネルギーやITを使った分散電力管理など、近年の環境関連のイノベーションの進展には目を見張るものがある。技術的な難易度は極めて高いものの、脱石油社会は実現不可能とはいえなくなっている。もし脱石油が実現した場合、それは破壊的イノベーションとなり、従来の産業秩序はもちろんのこと、国家間のパワーバランスを激変させる作用を持つ。
重要なのは、脱石油が「実現可能かもしれない」ことである。すぐには実現できないにしても、実現できる可能性が「見えた」という事実は、国家覇権を争う国際社会では極めて重要な意味を持つ。
過去100年の国際社会はすべて石油を中心に回ってきたといっても過言ではなく、米国が覇権国家として君臨できたのも、米国が世界最大の産油国のひとつだったからである。中東問題もすべては石油に関する利権がベースになっている。
現代社会における支配構造の中核となっていた石油への依存度を下げられる可能性が見えてきた今、米国から覇権の奪還を狙う欧州各国がこの破壊的イノベーションに目を付けないわけがない。つまり欧州初の脱石油という流れは、米国覇権の抜本的な転換を狙った準戦争行為であり、「環境を大事にしょう」といったレベルの話ではないのだ。
こうした国際的な覇権争いには、必ずと言ってよいほど国際金融資本の利害が絡むのが世界の常識である。近年、ITが急速に社会に普及したことで、多くの産業において限界コスト(一単位の生産量増加に必要なコスト)が低下するという傾向が顕著となっている。ウーバーなどのシェアリング・エコノミー企業はその典型で、すでに存在しているリソースを再利用するだけなので、IT化社会では、既存の資産を流用するだけで、いとも簡単に新しいサービスを開発できる。
こうした産業構造の変化は金融システムに対して極めて大きな影響を及ぼすことになる。高度にIT化された社会においては、新規に設備投資をしなくてもサービスを開発できるため、経済圏全体で必要とする資金量が減ってしまう。つまりIT化社会では、資本に対する対価の減少、つまり低金利化が進むことになる。
国際金融資本は何を狙っているのか?
近年、全世界的に低金利が続いており、一般的には量的緩和策の影響と理解されているが、それだけが原因ではない。大量のマネーを必要としなくなる新社会の到来を市場が察知しており、それが低金利の遠因となっている可能性が高い。
そうなってくると、今後、金融資本は従来と同じ水準のリターンを得られなくなるが、ここで重要な意味を持ってくるのが地球温暖化対策である。対策の実施には巨額の資金が必要とされており、行き場を失った資本にとっては高いリターンを得られる最後のチャンスと映る。国際金融資本が環境問題に前のめりになる理由はまさにここにある。
米国から政治的覇権を奪還したいという欧州の政治的な野心に、国際金融資本という利権が加わったものが、今、進展している地球環境問題の本当の姿である。欧州側は脱石油を実現するのは困難であることを重々承知の上で、あえて難易度の高い政治的な賭けに出ている。
一方、日本は、効率の高い火力発電所の開発を行い、この技術を通じて「世界における気候変動問題への対応をリードする」(安倍首相)と主張している。つまり地球環境問題は二酸化炭素の排出量を減らすことだけが目的であり、それを実現すれば、各国から評価されると考えているフシがあるのだ。ここに日本と欧州各国の致命的な認識の違いがある。
欧州はある程度、無謀であることを理解しながらも、高度に政治的な理由から石油を使わない社会の実現を打ち出している。これに対して世界最大の石油産出国である米国は、真っ向から反対しているという図式だ。石油を使わない社会の実現を政治的・戦略的に主張している相手に対して、効率を上げて石油を使い続ける提案を行っても、批判されるのは当たり前である。
それどこか、日本がこうした中途半端な提案を続けていると、脱石油が実現しないのは日本のせいだとして、大きなペナルティを科されてしまう可能性すらある。冷酷な国際社会において「不当だ」と叫んだところで、誰も助けには来てくれないだろう。日本人同士で欧州勢はアンフェアだとグチを言い合ったところで問題は解決しないのだ。
日本における再生可能エネのポテンシャルは高い
では日本は環境問題についてどのように取り組めばよいのだろうか。選択肢は、積極的に再生可能エネルギーへのシフトを宣言するか、米国と歩調を合わせ脱石油を目指さないのかの2つにひとつしかない。今のまま表面的には欧州に追随する姿勢を打ち出しながら、現実には石油依存からの脱却を行わないという中途半端なスタンスを続ければ、ほぼ確実に批判のターゲットになるだろう。
米国は石油を含むすべてのエネルギーを自給自足できることに加え、世界最大の経済力と軍事力を持つ覇権国家であり、国際社会から孤立しても何の問題も発生しない。一方、日本は石油依存を続けたところで、ほぼ100%輸入に頼るという状況に変わりはなく、エネルギーの安全保障という観点では、石油依存を続けることにも大きなリスクがある。総合的に考えれば、再生可能エネへのシフトを強く打ち出した方が圧倒的に有利だ。
欧州と歩調を合わせ、各国よりも高い目標を掲げれば、日本は国際社会での議論をリードできるし、対米交渉という点でも有力なカードを握ることができる。
再生可能エネルギーの話題になると、ほぼ100%、再生可能エネルギーは石油の代替にならないという話が出てくるが本当にそうだろうか。先にも述べたように再生可能エネや電力に関するイノベーションは驚異的な進歩を見せており、決して実現不可能な領域ではなくなっている。
もし、これが実現できれば、エネルギーの一部を外国に頼らずに済むので安全保障上、絶大なメリットを享受でき、しかも国際社会での発言力も飛躍的に向上する。そこまで脱石油が実現できなくても、高い目標を掲げることで、国際社会のパワーゲームで有利に振る舞えるのは間違いない。
資源エネルギー庁の調査をもとに環境省が分析した結果によると、日本における再生可能エネのポテンシャルは、火力を中心とした現状の発電電力量の何と6倍以上にもなるという。つまり、日本は本気さえ出せば、再生可能エネルギーをフル活用できる国であり、むしろこの技術を戦略的に活用したほうが圧倒的にメリットが大きいというのが現実なのだ。
欧州に指摘されたので、嫌々二酸化炭素の排出を減らしますというスタンスこそが、もっとも国益を損ねる行為だと筆者には思えてならない。
(文=加谷珪一/経済評論家)














