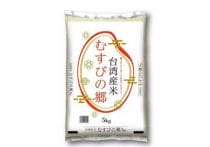トライアルが西友を買収で「意外に絶大な相乗効果」…最強の店舗で高い集客力

イオン、「ドン・キホーテ」を運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)、トライアルホールディングス(HD)が買収に名乗りをあげていたイオン争奪戦を制したのは、ダークホースとみられていたトライアルHDとなった。買収額は約3800億円とみられる。西友の売上高は6648億円(23年12月期)で、トライアルHDのそれは7179億円(24年6月期)と規模はほぼ拮抗しているが、西友はトライアルHDの子会社となる。両社ともに黒字経営で“勝ち組同士”の一体化といえるが、業界関係者は「意外に絶大な相乗効果が期待できるかもしれない」と指摘する。
1963年(昭和38年)創業の西友はコンビニエンスストア「ファミリーマート」や日用品・雑貨店「無印良品」を生んだことでも知られている(ともに現在は他社が運営)。1990年代に入ると経営危機が叫ばれるようになり、2002年には米国ウォルマートの傘下に入り、08年にはウォルマートの完全子会社となり上場を廃止。21年には、「楽天西友ネットスーパー」で協業していた楽天グループが西友の株式の20%を取得し関係を強化し、同年にはウォルマートは西友株の85%をKKRに売却。その後、23年には楽天は保有する西友株をKKRに売却。同年にはウォルマートの基幹システムを西友独自のものに入れ替える大規模なシステム更新作業を行い、ウォルマートとの関係解消を進めてきた。
24年には北海道の店舗をイオン北海道に、九州の店舗をイズミに売却して事業を本州に集中させる方針に転換。現在の全国の店舗数は約240店舗であり、「EDLP(エブリデー・ロープライス)」を掲げ、日用品から食品まで幅広いラインナップを取りそろえるPB(プライベートブランド)「みなさまのお墨付き」に代表される低価格がウリ。23年12月期決算は売上高が6648億円(前期比5.8%減)、営業利益は260億円(同24.8%増)、経常利益は270億円(同29.6%増)となっており、近年は黒字が定着している。
両者にとって良い買収
西友はウォルマートからの自立を契機に上場を目指しているとも伝えられていたが、他社から資本を取り入れて生き残る道を選択。昨年頃から西友の株式の85%を保有する米投資ファンド・KKRが株式売却手続きを進めており、イオン、PPIH、トライアルHDが入札に参加していた。
「イオンとPPIHが有力とみられていた。西友は首都圏の駅近に多くの店舗を持つ一方、イオンは郊外の店舗が多く、イオンにとって西友の店舗網は魅力的。ただ、両者は長年ライバル関係にあり、西友としては、さすがにイオンの子会社になるのは社内の士気の問題などから難しかったのではないか。一方、PPIHであれば業態が異なるので現場レベルで衝突するリスクは少なく、西友の店舗の地下フロアと1階の食品売り場を残したまま2階より上の階にドンキのディスカウントストアを入れることで、集客力の高い店舗づくりが見込める。よってPPIHのほうが有力とみられていた。
第3候補とみられたトライアルHDが買収することになったのは業界的には意外な結果だが、トライアルはドン・キホーテ以上に低価格路線のディスカウントストアであり、西友の店舗に同社の食品売り場を残したままトライアルの売り場が入れば、絶大な相乗効果が生まれる最強の店舗をつくれるかもしれない。結果的に両者にとって良い買収といえるだろう」
別の大手小売りチェーン関係者はいう。
「トライアルのメイン商圏は九州、西友は本州なので重複が少ないのは大きな判断要因の一つになったのでは。また、小売業の歴史的には西友のほうが長く、食品スーパーのノウハウも実績も西友のほうが上なので、買収されても一定の主導権を握れるという西友側の思惑も影響したのかもしれない。これが相手が同業のイオンだと現場・経営の両方のレベルで社員間の摩擦が生じるリスクがある。このほか、トライアルも西友もシステム活用・投資を重視して積極的なことで知られており、相性が良いと感じた部分もあったのでは」
トライアルの特徴
当サイトは2024年8月7日付記事『有名な格安スーパー、カード規約違反は本当?食料品は不可、計3千円以下も不可』でトライアルの経営戦略を解説していたが、以下に再掲載する。
――以下、再掲載――
ディスカウントストア「TRIAL(トライアル)」が、食品購入に際してはクレジットカードを使えない、ということが話題になっている。その理由は、クレジットカード加盟店は、有効なカードを提示した会員に対してカード払いを拒否できないことが一般的だからだ。一方で、クレジットカード払いに制限をかけることで安さを実現できている、と理解を示す向きもある。では、トライアルは実際にクレジットカードの規約違反をおかしているのだろうか。
SNSで物議を醸すきっかけとなったのは、あるXユーザーが行ったこんな投稿。
「利府(宮城)に新しくできたトライアルに行ってみた。いい加減クレジットカード会社の規約守ろう?コンプライアンスとか無いのかな」
トライアルは、食品スーパーとディスカウントストアを一体化させ、衣食住すべてのカテゴリを扱うスーパーセンター業態を中心に、北海道から九州まで幅広く店舗を展開している。
トライアルを展開するトライアルカンパニーは、中国から大量に技術者を自前で採用・育成し、同社で使うシステムの開発や保守、運用などに活用し、業界内外から注目を浴びている。自社のIT技術を駆使した物流コストや仕入れコストの削減、計画的な在庫コントロールなどにより、年間を通して常に低価格を実現している。
トライアルでは、店舗で買い物をする際、酒を含む飲食料品やタバコ、地域指定のゴミ袋など一部の商品代金を除いた金額が税込み3001円以上の場合のみクレジットカードを利用することができる。ちなみに、ネットストアではクレジットカード払いが可能。
だが、クレジットカード会社は「加盟店規約」を設けており、そのなかで加盟店に対し、会員が有効なカードを提示した場合に、拒絶したり、現金払いやその他の決済手段の利用を求めることを禁止している。クレジットカード取引に詳しいファイナンシャルプランナーは、「違反すればペナルティーが課される場合もある」と話す。
「たびたびネット上で、『セール商品はカード払いNGだった』『ランチの時間帯はクレジットカードお断りと言われた』『1000円以下は現金のみの店がある』といった報告がありますが、カード利用に条件をつけたり、利用時間帯を制限することは規約違反となります。ただ、この加盟店規約について、カード会社が優越的地位を利用して一方的に押し付けているとして適法性を問う声もあるので、将来的には店舗判断で自由にカード利用に条件を付けられる日が来るかもしれませんが、利用者の立場からすると、いつでもどこでもカードを使えることが望ましいのは確かでしょう」
トライアル、カード会社との契約は?
少なくとも現状において、カード会社が加盟店に対して求めている規約に照らしてみると、トライアルが飲食料品等の買い物においてカード払いを拒否することは、規約違反の可能性は否定できない。そこで、Business Journal編集部はトライアルに対し、カード支払いに制限を加えることが規約違反に当たらないのか、話を聞いたところ、以下のように返答があった。
「クレジットカードのご利用条件につきましては、今現在、カード会社と継続して協議を行っております。本件の詳細は、会社間の守秘義務の観点から、お答えすることができません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」
SNS上では、「元々トライアルはカード利用不可だったのに、カード会社がカードを取り扱うようにねじ込んできて、その時に現在の条件をのませたらしい」という真偽不明の情報も出ており、トライアルとカード会社で特殊な契約を結んでいると指摘する向きもある。
加盟店はカード会社に対し、カードでの売り上げから一定割合の手数料を支払うことから、ディスカウントストアなどではカードの取り扱いを行っていないケースが少なくない。カード手数料をなくすことで、コストを抑えているわけだ。そのため、トライアルが飲食料品等においてカード利用を制限していることに理解を示す声も多い。
トライアルでは、独自のスマホアプリ「SU-PAY」とプリペイドカードを展開しており、それら以外は飲食料品等の買い物にキャッシュレス決済が利用できない。さらに、飲食料品等以外かつ3001円以上の買い物でも、クレジットカード払いをしようとするとレジでは対応しておらず、サービスカウンターで清算しなければならない。独自ルールが多く、慣れるまでは不便に思うこともあるだろうが、その分、安さというかたちで利用者に還元されていると思えば、受け入れられる方も多いのではないだろうか。
(文=Business Journal編集部)