日本市場に注がれる熱視線…異端VCが世界へ羽ばたくスタートアップを生み出す
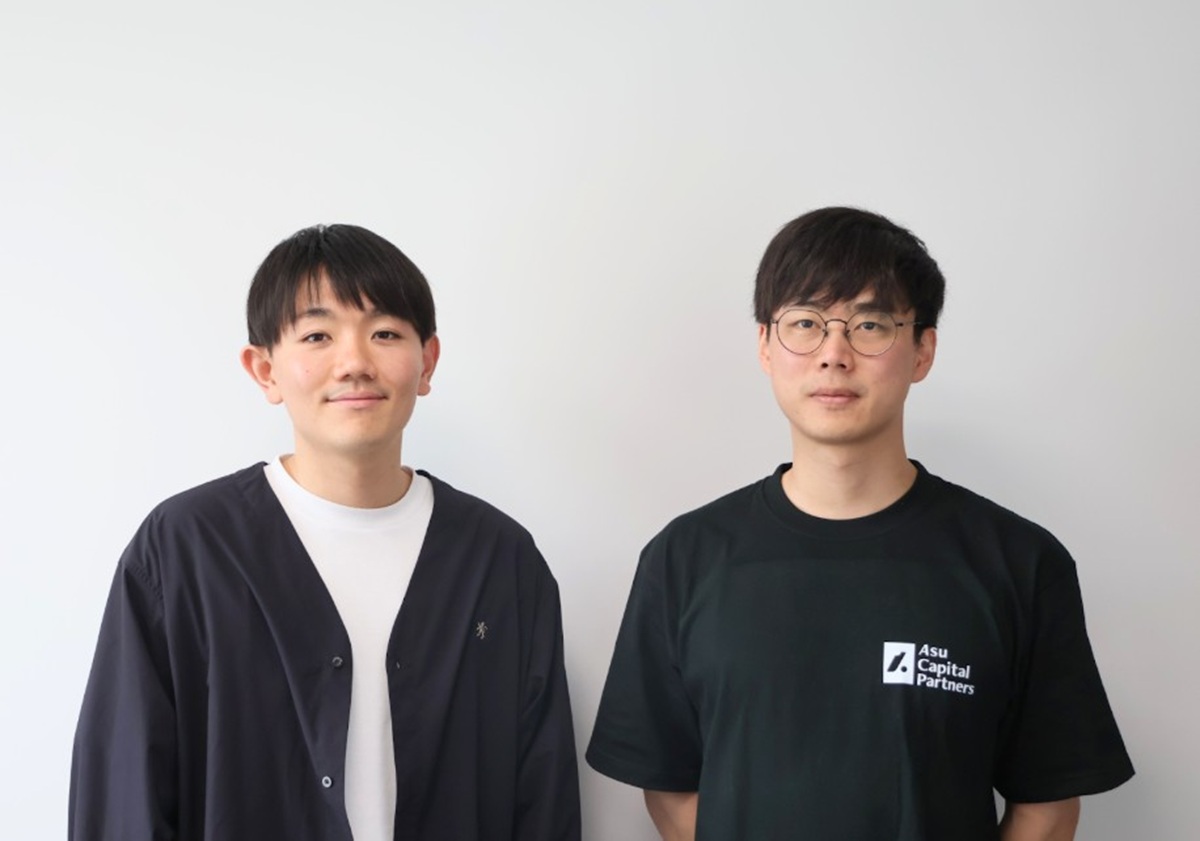
●この記事のポイント
・海外の投資家は日本のスタートアップに注目しているという。そんな流れを生かすために、海外の投資家と日本のスタートアップの橋渡しをしようとファンドを立ち上げたVCがある。
・「Japan to Global」という目標を掲げ、他のVCと異なる独自のポジションを確立しようとしている。異色のVCを立ち上げた2人の若き投資家を取材した。
「日本発スタートアップへの注目が、確実に高まっている」ーーその潮流を誰よりも早く感じ取り、動き出した2人の若き投資家が立ち上げたのが、Asu Capital PartnersというVC(ベンチャーキャピタル)だ。
創業者の二人は、East Ventures、YJキャピタル(現 Z Venture Capital)といった有力VCを経て2023年に独立。プレシード期から海外展開を見据えるスタートアップに対し、資金だけでなく人材、ネットワーク、グローバル発信までを支援する。ACPが目指すのは、資本だけでつながる関係ではない。情報や文化の「翻訳者」として、日本と世界の間に立つ存在だ。
なぜ今、日本なのか。そして、なぜファンドを作り、世界との橋をかけようとしているのか。彼らの原体験と戦略に迫る。
目次
- 「日本にはチャンスがある」新進気鋭のVC
- 中国でスタートアップの熱狂を体感した二人
- 世界中で壁打ち 海外投資家は日本をどう見ていたか
- 世界の「共通スタンダード」目指せる企業に投資
- 高い「翻訳力」 他VCも味方につける独自ポジション
- 「Japan to Global」の実現へ
「日本にはチャンスがある」新進気鋭のVC
「今、日本には大きなチャンスがあります」。そう語るのは、2023年8月にAsu Capital Partners(以下、ACP)を創業したFounding Partner・夏目英男氏と同・李路成氏だ。
ACPは、「Japan to Global」を掲げ、日本発でグローバル市場に通用するスタートアップへの出資を行うVCだ。最大の特徴は、LP(リミテッド・パートナー)の約4割が海外投資家で構成されている点にある。次世代の日本発プロダクトに対する関心の高まりを受け、国外のVCや個人投資家が早期から同ファンドに参画している。また、MIXI、ディー・エヌ・エー、TBSといった事業会社や金融機関も出資に名を連ねており、国内外で高い信頼を獲得していることがうかがえる。
夏目氏と李氏に共通するのは、日本語・英語・中国語の3言語を自在に操るトリリンガルであることだ。国内の投資家としては稀有なこの言語能力を活かし、それぞれ著名VCを経て独立。ACP自体もまた、スタートアップのようにゼロから立ち上げたファームである。
なぜ彼らは独立を選び、いかにしてファンドを立ち上げたのか。「日本のチャンス」を語る前に、その成り立ちをひもといていきたい。
中国でスタートアップの熱狂を体感した二人
夏目氏は元East Ventures、李氏はYJキャピタルの出身。二人の共通点は、中国における国家主導のスタートアップ熱を、現地で肌で感じた原体験である。
夏目氏は、両親の仕事の関係で5歳のときに中国・北京に移住し、2000年から2019年までを現地で過ごした。アリババ、テンセント、DiDi(滴滴出行)、バイトダンス、拼多多(Pinduoduo)──いまやテックジャイアントとなった企業群が、まさにスタートアップとして登場し、急成長していく様を目の当たりにした世代だ。大学時代には、清華大学に在籍しながら、日本のスタートアップ経営者による「中国スタートアップ視察ツアー」のアテンドを手伝うこともあったという。
「ライドシェアについて『面白いと聞いたので教えてほしい』と聞かれたのですが、中国ではすでにそれが当たり前になっていました。ある国においては『当たり前』のことが、別の国では『特殊』だと捉えられる。これがイノベーションだと思いました」と夏目氏は振り返る。

一方、李氏は中国・上海生まれで、2013年に早稲田大学政治経済学部に進学した。ちょうどその頃、中国では「大衆創業・万衆創新」という国家主導のイノベーション促進政策が進行中であり、李氏の高校時代の同級生たちも、次々とスタートアップやVCに進んでいた。李氏も起業したいと思い、大学1年生で会社を興した。チームは100人を超え、売上が短期間で300万円から3000万円に変わるというスタートアップ的体験をしたという。
そうした原体験を持ちつつ、それぞれ別のVCで経験を積んできた。転機となったのは、2022年夏のこと。日本にやってくる海外投資家が次々と彼らに面会を求めてくるようになったのだった。
その頃の夏目氏と李氏は、他社にいながらも週に3〜4回は会うほど仲が良く、情報交換を密に行っていたのだが、あるときそれぞれがアポを取っていた投資家が、結局どちらにも会っていたことに気づく。「日本のスタートアップへの関心が高まっているみたいだ。だったら一度海外投資家を招いたカンファレンスをやろうか」と話し始めた。
2022年12月、二人は初めて共同でカンファレンスを開催。海外投資家、日本の起業家、外国人起業家を一堂に集めた場は、深夜まで熱気に包まれた。「誰も帰らないから、『そろそろ帰ってください』とこちらから声をかけるほどでした」と李氏は苦笑する。グローバルのキャピタルアロケーションが再配分されるに違いないーー、二人はその胎動を感じていた。
その場で参加者から「ファンドを作らないのか?」という問いが投げかけられたことをきっかけに、「この熱を一過性のものにせず、継続的な場を作りたい」と二人は強く思うようになる。年が明けてまもなく、ACPの実現に向けて彼らは本格的に動き始めた。
世界中で壁打ち 海外投資家は日本をどう見ていたか
スピード感のある立ち上げだったとはいえ、当初から順風満帆だったわけではない。創業当初は、日本在住あるいは来日した外国人起業家を支援する構想が中心にあった。しかし次第に、地政学的な変化やマクロ経済の動向、日本が持つ独自のポテンシャルを踏まえた戦略へとシフトしていく。
その転換の裏には、世界中の投資家と行った約300件に及ぶ壁打ちとディスカッションがある。前職時代のネットワークだけでなく、積極的なコールドコールを通じて投資家にアプローチ。限られた資金での海外出張では空港泊も辞さず、二人は世界を飛び回った。
対話を重ねる中で見えてきたのは、海外投資家たちの「日本市場に対する関心と不安」だった。興味はある。だが、情報が届かない。スタートアップが本当に存在するのか、どんな起業家がいて、どのVCがどんなテーマに投資しているのかーー言語と文化の壁の中で、何も見えていなかったのだ。
「それなら、自分たちがその橋渡しをしよう」。海外との対話を重ねる中で、彼らのミッションは明確になっていった。日本に眠る起業家やスタートアップが、もっと海外に対して発信力と接点を持てるプラットフォームを築く。それこそが、ACPの果たすべき役割だと。
「“ファンドを作った起業家だ”と、LPの方から言っていただいたこともありました」と夏目氏は語る。その言葉には、ゼロから仕組みを立ち上げた二人の情熱と信頼が映し出されている。
世界の「共通スタンダード」目指せる企業に投資
「2023年以前と現在を比較しても、『天と地の差』と言えるほど海外投資家による日本スタートアップへの出資は急増しています」と夏目氏は言う。
この要因は二つある。一つは、「スタートアップ育成5か年計画」をはじめとする、スタートアップ支援施策など日本政府の政策的な後押しだ。
もう一つは、地政学の変動と他のマーケットの状況だ。特に米中の経済対立により相互の投資が難しくなる中、グローバルで見ると米国・中国以外の「第三極」として日本が再注目されている。東南アジアも選択肢として挙がるが、流動性やExitマーケットの面でまだ弱さがあるという。
「日本のチャンスは少なくとも今後5年から10年は続くと考えています」(夏目氏)
そうした潮流のなかで、ACPが出資するのは、どのようなスタートアップなのか。現在の投資先は12社。プレシード〜シードラウンドが中心で、1社あたりの投資額は数千万円規模が主流だ。業種にはこだわらず、「世界で共通スタンダードを取れるかどうか」が、最上位の投資判断基準となる。
出資先には、日本と世界のスタンダードを接続するような企業が並ぶ。たとえば、野球の投球データを解析するKnowhereは、千葉ロッテマリーンズやMLBのテキサスレンジャーズにも技術を導入している。
「野球のルールは万国共通。その中で、日本はWBCでの優勝実績もあり、日本人選手の活躍も目覚ましい。ニッチな市場に見えるかもしれませんが、日本のスタートアップが“共通スタンダード”を取りにいける領域だと考えています」(夏目氏)
こうした視点は、他の支援先にも通底する。次世代音楽IP制作プロダクションのVOLVE CREATIVEは、YouTube経由で5万人以上のフォロワーを獲得し、中国・韓国・欧州にも広がるファン層を持つ。また、AIとIPを組み合わせ、中間業者を介さず玩具を自動デザイン・生成・製造するAdofaerなど、プロダクトだけでなく製造プロセスそのものに革新を起こす企業にも投資している。
ACPの特徴は、「グローバル=米国」という一元的な見方を取らない点にある。中国、韓国、東南アジア、欧州など、それぞれの市場で日本企業が“勝てる戦い方”があるという視点で支援を行っている。
カギとなるのは「違和感」だ。
「海外の人にとって“違和感”のあるものこそ、実は市場がある」と二人は口をそろえる。夏目氏と李氏は、ともに海外にいた時期が長かったぶん、日本の文化とその他の文化の間にある違和感を感じ、そこにマーケットが見えるのだという。
「日本由来のイチゴを生産・販売するOishii Farmが米国で話題になったのは、米国には野イチゴのような酸っぱいイチゴしか存在せず、日本のように形が整っており、甘いイチゴがなかったから。日本人から見た『普通』が世界の『普通』でなかったとき、圧倒的なマーケットになる可能性があります」(夏目氏)
現場の空気をしっかりと感じるために、毎年米国、中国、さらに韓国、東南アジアに足繁く通う夏目氏と李氏。必ず見て回るのは、スーパーマーケットと大学だという。
「スーパーマーケットで消費トレンドを観察したり、知り合いづてに学生とアポを取り、現地のトレンドや価値観を探るんです」(夏目氏)
高い「翻訳力」 他VCも味方につける独自ポジション
ACPの強みは、単なる出資にとどまらない。市場選定、資金調達、ローカルチームの構築、人材紹介、ピッチ資料の作成、海外発信支援──スタートアップのグローバル展開に必要なサポートを、あらゆる側面から提供している。
たとえば、先述のVOLVE CREATIVEは、プレスリリースを日中英の3言語で同時発信した。それぞれの地域に最適化されたかたちでメッセージを届ける裏側には、ACPの支援があった。
海外投資家から見れば、「よくわからない日本のスタートアップ」に出資するのは容易ではない。そこでACPは、出資先スタートアップの成長状況を定期的にアップデートし、「以前お話ししたあの企業が、1年で大きく成長しています」といった形で投資家の関心をつなぎとめる地道な活動も行っている。
こうした支援は、単に語学力だけで対応できるものではない。「ピッチ資料一つとっても、海外投資家には日本の常識が通用しない。競合環境や市場背景など、前提となる情報を補完しないと、相手には刺さらないのです」と夏目氏は語る。英語を話せるだけでは足りず、文化そのものを“翻訳”する力が求められる。ACPとしては、「このスタートアップは信頼に足る」と思わせる“レファレンスチェック可能な存在”であることを目指している。
人材面でも独自のネットワークを活かしている。ACPは、バイリンガル・トリリンガル人材とのつながりを活用し、スタートアップとグローバル人材のマッチングを支援している。たとえば、米ハーバード大学を卒業し、現在は東京大学大学院に在籍する人物がVOLVE CREATIVEに参画するきっかけを作ったのも、ACPの紹介によるものだ。
さらに注目すべきは、その立ち位置のユニークさである。ACPは、同じラウンドで投資を行う他のVCから声がかかることも多い。通常であれば競合関係にあるはずのVCとも協業関係を築けるのは、ACPが提供する支援機能が他と異なっているからにほかならない。
「私たちは“ファンド”というより、“ファーム”だと思っています。今の日本にとって最適な支援手段がベンチャーキャピタルファンドだったのでこの形をとっていますが、本質はそこではない。ファンドごとにテーマを変えるのではなく、マクロの流れを見据えたうえで、必要な打ち手を戦略的に設計し、ファンドという器に落とし込んでいく。それが私たちのスタンスです」と夏目氏は語る。
「Japan to Global」の実現へ
「Japan to Global」という高い志を掲げる二人だが、実はその性格は対照的である。
夏目氏いわく、「行動力が異常」なのが李氏だ。とにかく打席に立ち、バットを振り続ける。あるとき、李氏が米国出張に行った際に、社内のSlackを見ると彼から面談メモが届いていた。詳しく予定を聞いていなかった夏目氏が詳細を見てみると、セコイア・キャピタルをはじめ、米国の名だたるファンドの著名パートナーとの面談内容が記載されていた。その上、まだ帰国してもいないのに、これらの投資家を起業家にすでにつないでいたというので、さらに驚かされた。

こうした大胆さを持つ“攻めの李”に対し、“守りの夏目”は戦略を緻密に組み立て、足場を固めてから動くタイプだ。「空中戦の李と、地上戦の私。地上からも空中からも攻めてこそのACPなのです」と語る。
この両極のスタイルが共存していることが、ACPの柔軟かつ立体的な支援の源になっている。彼らの挑戦は、日本という国が再び世界とつながるための橋渡しの試みでもある。「Japan to Global」という旗印は、スタートアップ個々の挑戦だけでなく、日本市場そのものの再定義につながるかもしれない。
実際、資本や人材が再び日本に流れ込む今、日本はこれまでとは異なるかたちで“選ばれる”フェーズに入りつつある。こうした潮流の中で、彼らが見据えるExit戦略も、国内IPOやM&Aにとどまらない。グローバル企業によるM&Aも視野に入れており、「共通スタンダード」を見つけたスタートアップが、日本から世界の産業構造に橋をかける存在になることを目指している。
「海外の投資家が“日本市場の壁を越える”だけでなく、“その壁の中に入ってもらう”ことも見据えています」と夏目氏は語る。
記者は最後にこう尋ねた。
「あなた方は、世界のどこででも起業できたはずです。なぜ日本なんですか」
少し考えて、夏目氏は言った。
「日本が好きで、その日本が今最大のチャンスを迎えているからですね」
またとないチャンスの時期だと日本に賭けた二人。ここからユニコーンが生まれることに期待したい。
(寄稿=相馬留美/ジャーナリスト)











