水辺の安全を1秒で守る――プライムセンス「Meel」が変える溺水事故防止の未来
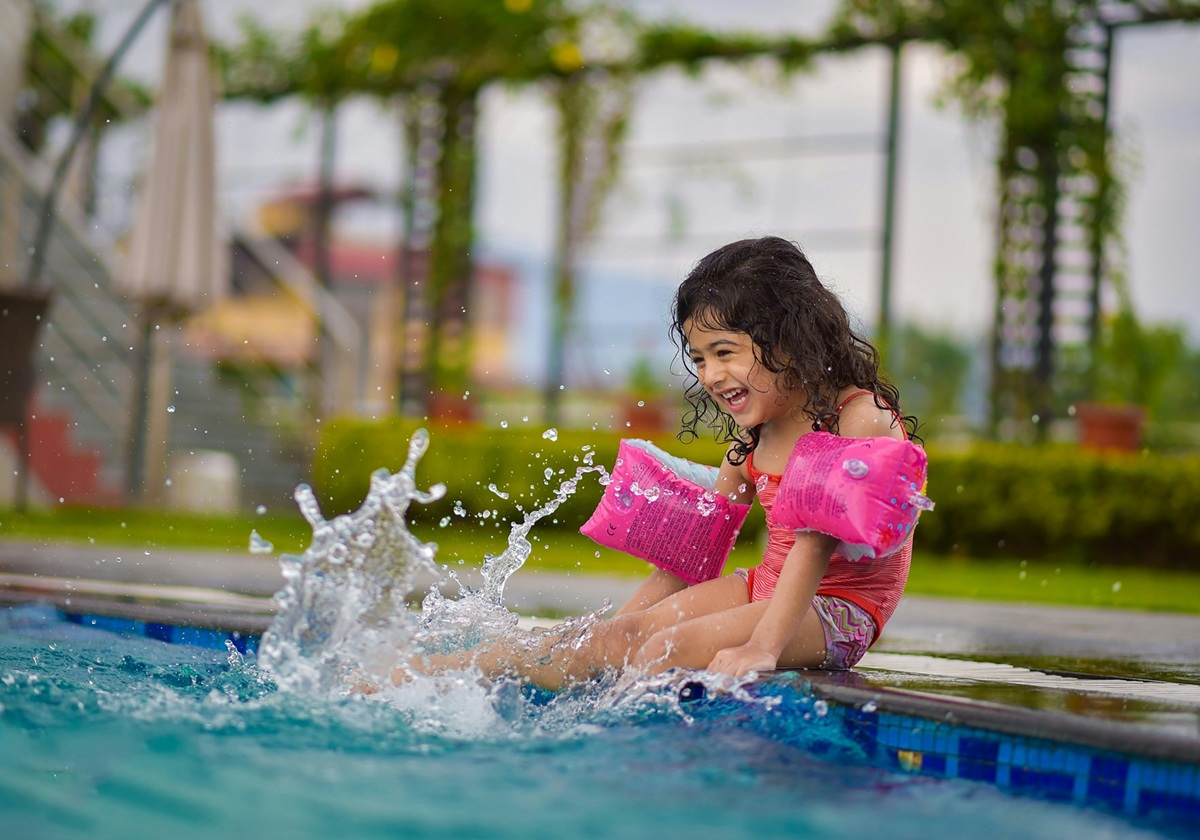
●この記事のポイント
・2025年夏、東京・小金井市のスイミングスクールで小1児童が溺死する事故が発生。全国的にも溺水事故は増加しており、監視の死角や救助までの時間が課題となっている。
・株式会社プライムセンスが開発した「Meel」は、RFID技術を用い、溺水の兆候を検知して約1秒で通知。プライバシーに配慮しつつ誤検知も少ない。来シーズンには閉鎖水域での導入を予定し、将来的には海水浴場などへの応用も視野に入れる。
・普及にはコストや装着ルール、文化的課題が残るが、同社は業界団体や行政との連携で社会実装を目指す。水辺の安全を社会インフラとして標準化し、「1秒で命を救う」未来を創ろうとしている。
2025年夏、東京・小金井市のスイミングスクールで小学1年生の児童が溺死する事故が起きた。事故はさまざまなメディアでも報じられ、SNS上では監視体制や施設運営の在り方を巡って激しい議論が交わされた。
監視員が配置され、一定の安全対策が講じられているはずのスイミングスクールで、なぜ命が失われてしまったのか――。その背景には、施設運営の人員不足や監視の死角、そして「異常を発見してから救助までの時間の長さ」という課題がある。
実は、全国的にも溺死事故は増加傾向にある。警察庁の統計によると、コロナ禍による外出自粛の影響で一時的に減少していた溺水事故は、2023年以降、再び増加に転じた。暑さの厳しい夏が続く中、川や海だけでなく、管理されたプール施設でも事故が相次いでいる。
溺水事故は数十秒で命に直結する。特に子どもは静かに沈むため、周囲が気づきにくい。監視員が異常を発見してから救助に向かうまでの数十秒〜数分の遅れが、生死を分けることになる。
目次
- 検知から通知まで約1秒――「Meel」の革新性
- 技術の中核はRFID――プライバシーに配慮した検知方式
- 市場投入は来シーズン、まずは「閉鎖水域」から
- 溺死事故は「どこでも」起きる――普及の急務
- 導入の壁――コスト、運用ルール、文化的課題
- スタートアップが挑む「社会実装」
- 技術を「社会の標準」に――命を守るインフラとしてのMeel
検知から通知まで約1秒――「Meel」の革新性
こうしたなか、株式会社プライムセンスが開発したプール向け安全監視システム「Meel(ミール)」が注目を集めている。溺水の兆候を検知してから通知まで、わずか約1秒。現場の監視員やインストラクターに即座に知らせ、救助活動を開始できる。
代表取締役の高木淳氏は、開発の背景をこう語る。
「私はもともとトライアスロン競技の経験者で、水泳の危険性を肌で感じていました。子どもたちが安全に水泳を学べる環境を作りたい。でも、これまで世の中に本格的な溺水検知システムはほとんどなかった。それなら自分たちで作ろうと、千葉大学との共同研究を始めたのです」
高木氏自身、泳げない状態からトライアスロンを始め、水の怖さと正しい泳ぎの重要性を実感してきたという。その経験が、命を守る技術の開発を後押しした。
技術の中核はRFID――プライバシーに配慮した検知方式
Meelの心臓部は、交通系ICカード「Suica」や「PASMO」にも使われるRFID(無線自動識別)技術だ。ただし、同社が採用するのは長距離通信に対応した周波数帯で、25メートルプール全域をカバーできる。
利用者は、RFIDチップを内蔵した小型センサーを水泳帽やゴーグル、首輪状のバンドに装着。監視システムは、センサーが一定時間水中に留まり続ける状態を検知すると、瞬時に警報を発する。
検知~通知の所要時間は約1秒。人間の視覚監視に頼るより圧倒的に早く、誤検知率も低い。
最近は監視カメラ映像+AI解析による検知方式も開発されているが、日本ではプライバシーへの懸念や設置コストの問題で普及が進みにくい。対象が水着という特性から、この問題は避けて通れない。RFID方式は顔や身体を映さずに検知できるため、導入の心理的ハードルも低い。
市場投入は来シーズン、まずは「閉鎖水域」から
現在、Meelは大学との共同研究フェーズを終え、実証実験の最終段階にある。リリースは来シーズンを予定しており、当面はスイミングスクールや小学校プールといった閉鎖水域に特化する。
その理由は明快だ。
第一に、海や川など広大な水域では電波が届きにくく、監視精度が落ちる。第二に、一般客が集まる海水浴場ではセンサー着用を義務付けるのが難しい。ただし、沖に浮かぶ小規模なフロートや限定水域では導入の可能性がある。近年、沖合に人工浮島を設置した海水浴場が増えており、こうした限られた範囲なら技術的に対応可能だという。
さらに、太陽光発電による駆動も実証済み。電源確保が困難な屋外施設でも、日中であれば安定稼働できることが確認されている。
溺死事故は「どこでも」起きる――普及の急務
高木氏は「事故が多いのは海や川だけではない」と強調する。プールでも事故件数は増加しており、特に夏休みの水泳教室やレジャープールでは監視体制が追いつかないケースがある。
実際、小金井市の事故をはじめ、過去数年でも市民プールや学校施設での死亡例は報告されている。
「Meelのようなシステムが全国のプールに配備されれば、数秒で救える命が確実に増えます」
導入の壁――コスト、運用ルール、文化的課題
全国展開には課題も多い。まずは導入コストだ。機器本体やセンサーの価格、メンテナンス費用は自治体や民間施設にとって負担となる。
また、利用者全員にセンサーを装着させるためのルールづくりや、学校・保護者の理解も必要だ。
海外では監視カメラ+AI解析方式のシステムが導入され始めているが、日本はプライバシー意識の高さから慎重姿勢が目立つ。RFID方式はその懸念を回避できるが、「装着を嫌がる子ども」や「自由度の高い海水浴場」での対応は依然として課題だ。
スタートアップが挑む「社会実装」
安全分野の製品は、開発後すぐに売れるわけではない。社会全体での信頼獲得と制度整備が必要だ。高木氏はこう語る。
「我々だけでやるのではなく、水泳連盟、スイミングクラブ協会や教育委員会、ライフセービング協会など、関係者が手を組むことが重要です。安全は競争ではなく、協力で作るものです」
補助金や助成制度、保険会社の割引制度などが組み合わされれば、導入の加速も期待できる。スタートアップとしては、技術面だけでなく行政・業界団体との連携が成功のカギとなる。
技術を「社会の標準」に――命を守るインフラとしてのMeel
水辺の安全はサービスではなく、社会インフラだ。道路に信号機があるように、プールや海水浴場にも「命を守る仕組み」が当然のように備わる未来が必要だ。
高木氏は最後にこう締めくくった。
「溺水事故をゼロにすることは難しいかもしれません。でも、1秒で気づけるなら、防げる命は必ずある。そのために技術を磨き続けます」
事故は起きてからでは遅い。今求められているのは、「誰もが安心して水辺を楽しめる社会」を実現するための行動だ。その第一歩として、Meelはすでにスタートラインに立っている。
(文=UNICORN JOURNAL編集部)











