小山田圭吾「擁護論」がまかり通る日本人の精神構造…「障害者いじめ」による死亡者が出続ける文化的特異性
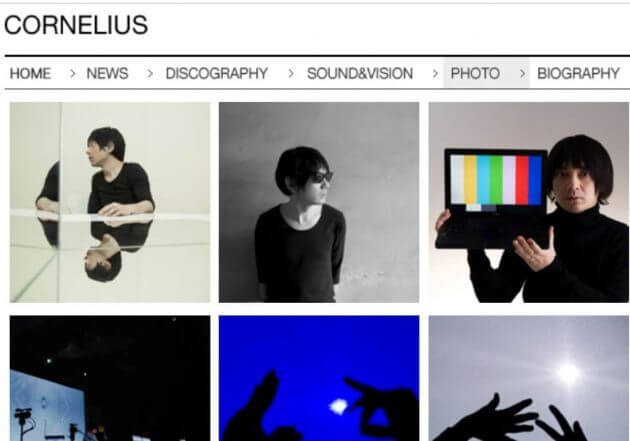
「障害者いじめ」で東京オリンピック・パラリンピック開会式の音楽担当を辞任に追い込まれた小山田圭吾氏の「炎上」がなかなか鎮火しない。
所属事務所社長がインタビューで、「この五輪の仕事は(本人も)あまり乗り気ではなかったんです。私も本来は引き受けるべきではなかったと思います」と述べたことが、せっかく消えかけている炎に燃料を大量投下することになっているのだ。
一方、ワイドショーでも芸能人がこの問題に対しての考えを求められ、「やったことは許されたことではないが、誰でもこのような恥ずべき過去があるのでは」「あまり一方的に叩きすぎるのも、いじめではないか」という「露骨な擁護論」を展開して、さらに灯油をぶっかけるようなことになっている。
小山田氏がやったことは「いじめ」などという甘っちょろいものではなく、「暴行」や「虐待」という違法行為。しかも、被害者側が一生消えない心の傷を、さらに雑誌で笑いモノにするということまでしている。さらに問題なのは、世間に公になるまで、ネットでいくら指摘されても、本人が謝罪や釈明の姿勢をまったく見せていなかった点だ。これらを「若気のいたり」「誰でもスネに傷がある」などとかばうのは、善悪のネジがぶっ飛んでしまっているといわざるを得ない。
だが、実はこういう無理筋な擁護論を展開する人が、日本社会にはかなりいる。事実、問題発覚当初から、SNSや芸能人・有名人の中で「小山田氏=過去を蒸し返されて理不尽なバッシングを受ける被害者」という主張も散見されていた。
「その時代の価値観を知りながら評価しないと、なかなか難しいと思う。今の価値観で断罪してしまうことは」(お笑い芸人・太田光氏/TBS系『サンデー・ジャポン』内の発言)
「大昔の発言や行動記録を掘り出してネットで超法規的にリンチするのはよくないと思うので、いくらいじめが嫌いでもこの糾弾には乗れないですね・・・」(批評家・東浩紀氏/自身のSNSで言及)
小山田氏の「障害者いじめ自慢」インタビューは、これが掲載された90年代の「鬼畜系サブカル」という時代背景が生んだもので、それを今の価値観で裁くのはフェアではなく、「リンチ」だというのだ。
ただ、これもビミョーな話だ。確かに当時、そういう分野はあったが、日本社会の一般常識で「障害者をいじめて笑う」ことを正当化するようなカルチャーはなかった。むしろ、当時は愛知県の中学2年生男子が、11人から壮絶ないじめを受けて自ら命を絶つといったような「いじめ自殺」が多発して、このような悲劇をどう防ぐのかということが盛んに論じられていたのだ。
ちなみに、当時のインタビューでは、ライターが「いじめ被害者」の自宅に乗り込んで、小山田氏との対談を要請しているのだが、その際のやり取りで、被害者の母親は「正直自殺も考えました」と述べている。「サブカルチャー」や「時代」などというスカスカの言葉で片付けられない悪質な話なのだ。
「いじめ」を「子供の悪ふざけ」に矮小化
また、「大昔」の話を叩くのは良くないというが、被害者への謝罪などの「けじめ」をつけていないハラスメントでそのような主張をするのは、日本だけだ。
例えば、アカデミー賞を受賞した名優・ダスティン・ホフマンは、1985年の出演映画の撮影現場で、インターンに性的嫌がらせをしたことがメディアに告発され、謝罪に追い込まれている。同じく演技派として知られるケビン・スペイシーも、1986年に子役の男の子に性的な関係を持ちかけたことが告発され、全方向からバッシングを受けて、謝罪声明文を出している。
集団イジメ、暴行、虐待、セクハラや性的暴行などの加害者側は、時が経てば自分が何をしたのかという記憶が薄れていく。時には、インタビューを受けた当時の小山田氏のように、「あの頃は俺もヤンチャだったなあ」という感じで、「いい思い出」になってしまうこともある。
対照的に、被害者の心の傷というのはいつまでも経っても癒えることはない。30年経過しようとも、何かのきっかけでフラッシュバックする。小山田氏のような著名人からハラスメントや暴行を受けた被害者などは、テレビなどのメディアでその顔を見て、恐怖の記憶が一瞬でよみがえってしまうこともある。だから、世界では、「大昔」のことであっても、人権を蹂躙するような罪はいつでも蒸し返され、バッシングや法的な制裁を受けるのが、「常識」なのだ。
しかし、日本はそのような感覚が希薄だ。「いじめ」という言葉によって、集団暴行や精神的な虐待の罪を「子供の悪ふざけ」という感じで矮小化するようなカルチャーがあるからだ。
小山田氏が辞任した後、従兄弟である音楽プロデューサーの田辺晋太郎氏はSNSで「はーい、正義を振りかざす皆さんの願いが叶いました、良かったですねー!」と批判する人々を揶揄したが、この挑発的な言葉がすべて物語っている。
「大昔の子供の悪ふざけ」程度でバッシングをするのは、「行きすぎた正義の行使」だと考える人たちが、この国には一定数いる。
このような「いじめを悪ふざけに矮小化する日本」の現実は数字にもよく出ている。厚生労働省によれば、2019年度に全国の自治体などが確認した障害者への虐待の被害者数は3169人で、うち2人が死亡している。相談・通報は前年度より533件多い9110件で過去最多を更新している。
「障害者いじめ」を自慢していた小山田氏が「被害者」として擁護される一方で、「本当の被害者」は手を差し伸べられることもなく増え続けているのだ。
「小山田圭吾も運が悪いよな」「揚げ足取られて可哀想」なんてことを言っている間は、この醜悪な現実を変えていくことはできないのではないか。
(文=長谷十三)







