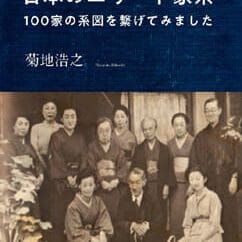『青天を衝け』で渋沢栄一vs岩崎弥太郎!…人材活用の違いに見る創業の渋沢、支配の三菱

『青天を衝け』、ついに登場した岩崎弥太郎、渋沢栄一と宴席で激論を闘わす
NHK大河ドラマ『青天を衝け』で岩崎弥太郎(演:中村芝翫)が登場。ついに渋沢栄一(演:吉沢亮)と海運事業をめぐって対決していく。第34回(11月7日放送)では、有名な逸話である船遊びでの激論が描かれる(大河ドラマでは宴席での話になっているらしい)。弥太郎が栄一を船遊びに誘い、企業活動の方針について持論を闘わせたのだ。
弥太郎「実は少し話したいことがある。これからの実業はどうしたらよいだろうか」
栄一 「当然、合本(がっぽん:株式会社方式で広く出資を募る)法でやらねばならぬ、(独裁的な)今のようではいけない」
弥太郎「合本法は成立せぬ。もう少し専制主義で個人でやる必要がある」
と大激論を交わした。収拾がつかなくなったので、栄一はその場を引き揚げたという(弥太郎が栄一に、共同で事業を進めていけば天下を取れると説得したという説もある)。
2人は明治初期を代表する起業家であるが、仲が良くなかった。性格の違いもあるが、考え方というか、事業のやり方に大きな違いがあったようだ。
多くの会社を興すも、支配し続けることに興味がなかった渋沢栄一
栄一はたくさんの会社を設立したが、それらを自分の支配下に置かなかった。栄一は渡欧経験があり、西洋文明のすばらしさを身をもって体験していた。それを日本にも広めたい。その思いが強かったこともあろうが、それ以上に新しい産業・会社を興すことが好きだったのだろう(性格的な問題だ)。ものを創ること自体に喜びを見いだすような人物は、できたものの維持運営には往々にして興味がない。
栄一もそのご多分に漏れず、設立した会社で金儲けすることにはあまり興味がなかったらしい。それらの会社を自らの支配下に置き続けるには株式を保有し続けることが必要だが、栄一はそれを売却して資金を用立て、次の会社を設立する原資とした。
できたものを維持運営するカネがあるなら、それで新しい事業を興したい。できた会社を支配するつもりがないから、出資は最低限でいい。残りのカネは合本(がっぽん)で集めよう! 合本は栄一の理想にきわめて合致したビジネス・システムだったのである。


支配し続けることにこだわった岩崎弥太郎、そして三菱・岩崎家の気風
これに対して、弥太郎はあくまでも岩崎家による支配にこだわった。三菱は会社の形式を取っているが、これは岩崎家の家業だ。意に沿わない者がいたら出ていってくれ――そう宣言しているくらいだ。
三菱の本業は海運業だった。しかし弥太郎の死後に、合併によって支配力が弱まると岩崎家は海運事業からスッパリ手を引いている。
弥太郎は新政府の庇護の下、日本近海の海運を独占し莫大な利益を上げた。それを忌々しく思った三井・小野・鴻池らが渋沢栄一と共同で、共同運輸会社を設立。熾烈なダンピング合戦を繰り広げるなか、弥太郎は胃がんで死去。跡を継いだ実弟の岩崎弥之助は共倒れを危惧し、三菱の海運部門と共同運輸会社を合併させて日本郵船会社を設立、事態の収拾を図った。すると、弥之助は日本郵船の経営支配には固執せず、むしろ手を引いて事業の再構築を図った(日本郵船は三菱の祖業であるにもかかわらず、戦後の三菱グループでは傍系企業と位置づけられている)。
完全に支配下に置かねば気が済まない。それが岩崎家の気風なのだろう。
会社を創らず、すでにあるものを運営する能力にこそ長けていた岩崎弥太郎
栄一はとにかくたくさんの会社を設立した。これに対し、意外なことに、弥太郎はほとんど会社を設立していない。
三菱財閥の母体はそもそも土佐藩営の貿易商社・開成館で、弥太郎が創ったものではない。三菱の事業である銀行、鉱山、造船も他者から購入したものが多い。三菱銀行は、臼杵(うすき)藩士が創った第百十九国立銀行が経営難に陥り、三菱の重役・荘田平五郎(しょうだ・へいごろう/旧臼杵藩士)に救済を依頼して三菱入りしたもの。三菱重工業の母体となった造船所は官営長崎造船所の払い下げ。高島炭鉱は後藤象二郎が手に入れたがうまくいかず、弥太郎の手に渡った。その他の鉱山では借金のカタで差し押さえたものなどがある。
つまり、弥太郎は自ら創り上げることよりも、すでにあるものを運営する能力に、圧倒的に長けていたのだ。
大量に学卒者を採用し、人材を育てた岩崎弥太郎は、自身も「土佐で3本の指に入る」秀才
弥太郎はすでにあるものを運営する能力に長けていた。その秘訣が何かと問われれば、おそらくそれは人材であろう。
弥太郎は土佐で「3本の指に入る」秀才だったという。江戸に上り、昌平黌(しょうへいこう)の教授・安積艮斎(あさか・ごんさい)の私塾で学んだ経験もある。
三菱の母体は土佐藩営の貿易商会だったため、同僚や部下のほとんどが学識のある武士出身者だった。そして、弥太郎は自身が学才に優れていたこともあって、東京大学や慶應義塾出身者の優秀な人材を採用した。学卒エリートに伍するほどの学才を身につけ、その上で商業上の経験を積んでいたから、かれらを使いこなすことができたのである。
学卒者の採用は今では当たり前だが、当時では非常に珍しかった。三井が学卒者の採用をはじめるのは、三菱に遅れることおおよそ20年。住友はさらに遅れて50年だった。これより遅い安田財閥は、江戸時代以来の丁稚(でっち)奉公を採用しており、学卒者を育成するルートがなかったので、たまに縁故採用で学卒者が採用されても退職してしまったという。他社も学卒者の幹部候補生が欲しいのだが、育成する土壌がない。そこで、三菱からヘッド・ハンティングすることが少なくなかった。弥太郎の人材育成は、意外なところで日本のビジネスに貢献していたのである。

学卒者採用に興味なし…「あとを託すべき優秀な1人」を見いだす渋沢栄一
渋沢栄一も学問を好み、教育機関への投資も積極的に行っていたが、それは自分の事業のためではなく、日本国家のためだった。
しかし、弥太郎が自分のためにせっせと人材育成したのに対し、栄一の視点は広すぎて、自分のためにはなっていない。栄一が設立し、最も目にかけていた第一銀行が1943年に三井銀行と合併すると、三井に比べて学歴の劣る第一銀行行員は不遇をかこち、不満が爆発して5年後に再分離している。換言するなら、栄一は学卒者の採用に必ずしも積極的ではなかったということだ。
栄一にとっての人材とは「自分の代わりに事業を続けてくれる人間」で、育成するというより、見いだすことが重要だったようだ。栄一は次から次へと会社を創っていくが、それらの維持運営には興味がない。あとは誰か優秀な人材に託すしかない。そのための人材である。
栄一が創った王子製紙。たまたま採用された甥の大川平三郎は、技術指導する外国人が手抜きで高慢ちきなことに我慢できず、独学で技術を習得して外国人を追い出した。そして、新技術の習得のために、会社に建言して欧米に留学させてもらう。
同様のことは三菱でもあった。造船所で技術指導する外国人がやっぱり何かと手抜きで高慢ちきだったのだ。そこで、弥之助は東京大学から理系社員を採用し、定期的に欧米に留学させて、やっぱり外国人を追い出した。ここでも、あとを託すべき1人を育成する渋沢流と、大量に採用して定期的に留学させて育成する岩崎流の違いが見て取れる。
渋沢栄一と岩崎弥太郎“唯一の合作”?…渋沢栄一が設立した東京海上保険が三菱傘下になったワケ
渋沢栄一は、元上司・井上馨が「三井の大番頭」と呼ばれるほどの三井派で、元同僚の益田孝が三井物産の初代社長を務めたように、人脈からして三井寄りだった。そのこともあって、岩崎弥太郎と共に仕事をした事例は少ない。その数少ない事例が、東京海上保険会社(現・東京海上日動火災保険)の設立である。
事の発端は、1872年にロンドン留学中だった旧徳島藩主・蜂須賀茂韶(はちすか・もちあき)が政府に鉄道会社の設立を建策したことである。
蜂須賀は旧大名らに出資金を募り、大蔵省で鉄道敷設を起案していた渋沢栄一に計画の遂行を一任したのだが、資金不足で頓挫してしまう。蜂須賀らはその資金で新たに公共的な事業を興してほしいと希望。政府関係者と協議の上、いくつかの候補が挙がり、1879年に東京海上保険会社が設立された。東京海上の設立者を渋沢栄一とするゆえんである。
栄一は三菱が有力な顧客になることを見越して弥太郎に資本参加を打診した。三菱はもともと海運会社だったので、損害保険に対する関心は強く、弥太郎は損害保険会社の設立を申請したが、海運会社との兼営はよろしくないとの判断から却下されていた。
かくして、三菱は東京海上保険会社の筆頭株主になった。栄一は後を託して次の起業へと向かい、弥太郎は手にした企業への影響力を強めていく。東京海上が三菱財閥の傘下企業になるにはそう時間がかからなかった。
1893年に東京海上が英国での保険業務に失敗して経営不振に陥ると、栄一は各務鎌吉(かがみ・けんきち)を取り立ててロンドンに派遣し、経営再建を果たした。のちに各務は東京海上を一流企業に成長させ、日本の損害保険業界の重鎮となるのだが、その一方で海運不況下の日本郵船社長に就任して再建、三菱信託(現・三菱UFJ信託銀行)の初代会長を務めた。実は1900年に各務は弥太郎の姪と結婚して、三菱財閥に取り込まれていたのだ。
ここにも「自分の代わりを託せる人材」を見いだす渋沢流と、「創造より維持運営がうまく、なんでも自分のものにしたがる」岩崎流の特徴が見て取れる。
(文=菊地浩之)