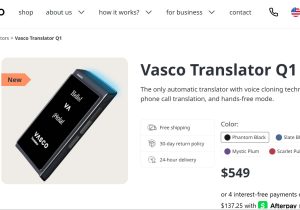精神科医が語る、徳川慶喜の“逃亡癖”と依存性パーソナリティ障害…長州征伐、大坂城逃亡

江戸幕府の15代将軍であった徳川慶喜は、評価が定まらない人物である。慶喜は十代の頃からその能力が評価され、“神君・家康”の再来とまで讃えられた。けれどもあらためて振り返ってみると、慶喜が特に傑出していたというよりも、当時の徳川家には、幕末の難局において政局を運営可能な「健康」な男性の後継者がいなかったというのが実情のようである。
13代将軍であった徳川家定は小児期から病弱であり、将軍らしい働きができないまま35歳で死去した。生来の知的障害であったという話も伝えられている。14代将軍となった徳川家茂は、13代将軍家定の従弟にあたる。
家茂は前将軍ともっとも血筋が近いということで、13歳で将軍に就任した。その後公武合体運動により天皇の妹である和宮を妻に迎えたが、21歳で遠征先の大坂城で死去した。
実は徳川家の将軍は、初代の家康、2代の秀忠を除けば、将軍としてそれなりの存在感のあったのは、8代将軍の吉宗以外には見当たらないように思える。
英知を称えられた慶喜は幕政改革に取り組んだが、薩摩、長州の攻勢に対して、敵前逃亡としかいえない行動を起こしてしまう。戊辰戦争において、維新軍に対峙した幕府軍は大坂城に陣取っていたが、慶喜は重臣数人を連れて、海路により秘密裡に江戸に帰ってしまったのだった。
江戸に戻った慶喜は戦意を喪失し、小栗上野介らの主戦論を退けてみずから江戸城を出て謹慎生活に入った。どうして慶喜は江戸幕府を見捨てるような行動をとったのであろうか。
以下の記述は、『徳川慶喜』(家近良樹著、吉川弘文館)、『運命の将軍 徳川慶喜』(星亮一著、さくら舎)、『徳川慶喜公伝』(渋沢栄一著、平凡社)などを参考にした。
水戸徳川家の七男坊、ハイカラ好みで豚肉好き、ざっくばらんで格式を重んじなかった徳川慶喜
徳川慶喜は天保8(1837)年、江戸・小石川にあった水戸藩邸において、藩主である徳川斉昭の七男として生まれた。母は有栖川宮織仁親王の王女の吉子である。母の姉は、第12第将軍・家慶の正室であった。いうまでもなく水戸藩は、徳川御三家のひとつである。
関ヶ原の戦いの2年後の慶長7(1602)年に、徳川家康の五男・松平信吉が水戸城主となった。だが翌年信吉は、21歳の若さで病死した。その後は家康の十男で当時2歳の徳川頼宣が引き継いだが、間もなく駿府藩に転封となり、頼宣の同母弟である家康の十一男で当時6歳であった徳川頼房がその後を継いでいる。これが、「水戸徳川家」の始まりである。水戸徳川家には、尊王の精神に富んだ水戸学が伝統として受け継がれていた。
慶喜の父である水戸藩の藩主斉昭は、「裂公」と呼ばれた強硬な攘夷論者であった。一時は幕政にも参画したが、井伊直弼との政争に敗れて江戸の水戸屋敷での謹慎を命じられ、政治の中枢から排除されている。
慶喜は水戸で育ち、藩校である弘道館で会沢正志斎らに学問や武術を教授された。武術のなかでは、手裏剣の名手であったという。弘化4(1847)年、慶喜は老中であった阿部正弘の意向により、徳川御三卿のひとつである一橋家の跡取りとして迎えられた。
慶喜はハイカラ好みで、洋装、洋食を好んだ。特に豚肉が好物だったために、豚一様(ぶたいちさま)と呼ばれていた。またざっくばらんな性格で、格式を重んじない傾向が強かった。

14代将軍は徳川家茂に決まるも、井伊直弼がたおれ、将軍後見職として政治復帰を果たした徳川慶喜
嘉永6(1853)年、12代将軍・家慶が病死し、その跡を継いだ第13代将軍・家定は病弱で男子をもうける見込みがないため、将軍継嗣問題が浮上した。ここで、慶喜を推す一橋派と、紀州藩主・徳川慶福を推す南紀派が対立したが、最終的には大老となった井伊直弼が裁定し、将軍継嗣は慶福(家茂)に決定した。ただし慶喜本人は、将軍職に積極的に就任しようとしていない。
安政5(1858)年、井伊直弼は勅許を得ずに日米修好通商条約に調印した。これに対して慶喜は江戸城に登城し直弼を問いただしたため、翌年の安政6年(1859年)に隠居謹慎処分を命じられてしまう。
ところが、安政7(1860)年3月、桜田門外の変において井伊直弼が暗殺されたことをきっかけとして、慶喜は9月に謹慎を解除された。さらに文久2(1862)年には、島津久光らによって、慶喜は将軍後見職に任命される。
慶喜は、政事総裁職に就任した松平春嶽とともに幕政改革を行い、京都守護職の設置、参勤交代の緩和などを行った。これ以後、幕府の内部は、攘夷と開国の間で大きく揺れ動くこととなる。
徳川慶喜は“朝敵”の汚名を恐れ、官軍に対峙する覚悟がなかった?
慶応2(1866)年の第二次長州征伐のさなか、将軍・家茂が7月に大坂城で死去する。慶喜は家茂の後継として次期将軍に推挙されたが、いったんは固辞し、12月5日になってようやく将軍に就任した。これ以後慶喜は、朝廷との密接な関係を保ちながら政権の運営にあたった。
孝明天皇と慶喜の協力関係は、攘夷をめぐって紆余曲折はあったものの、おおむね順調に推移した。孝明天皇は頑固な攘夷論者であり、本来は開国派である慶喜とは対立関係となるはずであったが、これについては政治的な駆け引きで乗り切ることができた。
しかし、慶喜にとって決定的に不幸であったのは、孝明天皇の突然の死去である。この件については本連載の孝明天皇の回『精神科医が語る“孝明天皇・毒殺説”…天然痘による病死?実際は岩倉具視がヒ素を盛った?』でも記したが、暗殺の疑いが濃厚である。孝明天皇が存命であれば、公武合体の精神は受け継がれ、幕府が大政奉還を行ったとしても、依然として慶喜を頂点にいただく幕府主体の「新徳川政権」が統治を続けていたことが予想されたからである。
これ以後、歴史の流れは急ピッチで進んでいく。慶応3(1867)年10月14日、慶喜は政権を朝廷に返上する(大政奉還)が、実態としては慶喜政権が継続されたままとなった。この状態を覆そうと、薩摩藩の西郷隆盛らは朝廷の岩倉具視らとともに12月9日、薩摩・土佐・安芸・尾張・越前の5藩による政変を起こして朝廷を掌握し、慶喜を排除しての新政府樹立を宣言した(王政復古の大号令)。このクーデターについて慶喜は事前に知っていたが、事態を黙認したらしい。
さらに12月25日、薩摩藩の挑発にのった旧幕臣が薩摩藩邸焼き討ちを強行したことにより、戊辰戦争が勃発する。翌年1月3日に鳥羽・伏見の戦いが始まったが、旧幕軍は連敗を喫した。1月6日、慶喜は秘密裡に大坂城を脱出し、幕府の軍艦・開陽丸で江戸に退却した。
慶喜が急遽江戸へ帰還した理由については、いくつかの説が提唱されている。そのひとつとして、“朝敵”の汚名を恐れ、官軍に対峙する覚悟がなかったとする説がある。水戸徳川家には徳川光圀以来の「朝廷と幕府にもし争いが起きた場合、幕府に背いても朝廷に弓を引いてはならない」という旨の家訓があったらしい。
公武合体論者であった慶喜は、盟友としていた孝明天皇が死去した時点で、すでに命運が尽きていたのであろう。皇室出身の母を持ち、尊王思想を家訓とした慶喜は、官軍と本格的に戦闘を行うという選択肢など持ちあわせていなかったのかもしれない。
江戸に戻った慶喜は、勝海舟らに事態収拾を一任して、みずからは上野の寛永寺において謹慎した。ただしどのような理由があろうと、軍の大将が敵前逃亡してしまってはその時点で負けは明らかであり、ここに江戸幕府の命運は尽きたのである。

第二次長州征伐取りやめ、大坂城逃亡、寛永寺蟄居…重要な決断からは“逃げてばかり”の徳川慶喜
江戸幕府を見捨てた慶喜は、新政府からは許され、駿河に移り住み悠々自適の余生を過ごした。さらに晩年には都内に住居を得て、貴族院議員にも就任しているが、政治的な発言はまったくしようとしなかった。
いずれにしろ、幕末における将軍としての慶喜の行動をどう考えればよいのだろうか。好意的にみれば、慶喜は維新軍と幕府軍の本格的な内戦を回避し、外国からの侵略を防いだ功労者とみなすことも可能である。しかし一方で、みずからの保身と徳川家の維持だけを目的にした利己的な行動に終始したようにも思える。
そもそも慶喜は、「名君」だったのであろうか。
その力量はさまざまな人たちによって評価されているが、実は疑問な点も多い。それらのなかには、かなりの“過大評価”ではと思われるものも多い。慶喜は政治的な課題に対して重大な決断をしようとしないで、そこから逃げ出すことを繰り返しているからである。
幕末の大坂城からの「逃亡」については、先述した通り幕臣に対する明らかな裏切り行為であったが、ほかにも慶喜による同様の行動は散見される。慶応2(1866)年の第二次長州征伐のさなか、将軍家茂が急死する。徳川宗家の跡取りとなった慶喜は、いったんはみずから幕府軍を引き継ぐ素振りをみせながらも、理由もはっきりしないまま取りやめてしまう。
大坂城から江戸に戻った際にも、似たことをしている。幕閣の間では主戦論と和解論が激しく対立していたが、慶喜はみずから議論をまとめようともせずに、勝手に寛永寺に蟄居してしまう。このように慶喜は、重要な決断からは常に「逃げる」ことを繰り返していた人物なのである。
徳川慶喜は「依存性パーソナリティ障害」だった可能性が?
このような傾向は、名家の跡取りである慶喜には修羅場の経験がなかったのだ――という生育環境から説明をすることも容易ではあろう。しかし精神医学の立場からは、「パーソナリティの特徴」としてとらえることも可能ではある。
慶喜の特性とぴったり当てはまる――とまではいえないが、ICD-10(国際疾病分類第10版)の診断基準にある「依存性パーソナリティ障害」とある程度共通する部分を持っているということはいえるかもしれない。この依存性パーソナリティ障害の人は、大事なところはすべて他人任せで、みずから決定することをしようとしないし、そういう場面からは逃げてしまうか、あるいは“固まって”しまう。
これは慶喜に限ったことではないが、戦国の世が落ち着いて以降、江戸幕府の将軍がみずから政治的な決断を行うことなど、実はほとんどなかった。政策を決めるのはたいてい、老中など幕閣の中心人物たちである。ところが慶喜は、信頼し、依存できる部下を持っていなかった。時代も激動期であり、重要な決定をみずから下していく必要があったが、慶喜にはそのような決断はできなかったし、その覚悟も持ちあわせてはいなかった。この点について、司馬遼太郎は次のように述べている。
「せっかく気力体力も人一倍充溢した生まれつきでありながら、不自然かと思われるほど野心が欠落しているのである」
「生まれつき貴種中の貴種であり、その礼遇をうけつづけ、それを当然と思い、それがために世俗的な向上心もなく、それを持つ必要もなかった」(司馬遼太郎『最後の将軍』文春文庫)
いずれにしろ平時であれば、ハイカラで格式にこだわらなかった慶喜は名称軍となっていたかもしれない。しかし幕末という乱世においては、“暗愚の将”とならざるを得なかったのである。
(文=岩波 明/精神科医)