これは暴力か?伝統校初女性応援団長が“シゴキ”の特訓の末に見たものとは?
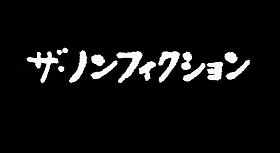 『ザ・ノンフィクション』公式サイト(「フジテレビ HP」より)
『ザ・ノンフィクション』公式サイト(「フジテレビ HP」より)【今回の番組】
9月22日放送『ザ・ノンフィクション 青春YELL!~史上初 花の女応援団長』(フジテレビ系)
高松遥之介君が帰って来た。去年は目を見開いて大声を上げ、涙を流して特訓に耐えていた彼が。
『ザ・ノンフィクション 青春YELL!』は前作に引き続き、明治大学付属明治高等学校・中学校の応援団を1年にわたって追う。村川絵梨のナレーションも続投されている。お姉さんのような視点が視聴者のそれと重なり、見ているこちら側が応援せずにいられない番組だった。
高松君を発見したことが、この番組を成功させた。初登場の彼を見た時は、僕は思わず声を上げて笑ってしまった。藤子・F・不二雄の漫画に登場しそうないじめられっ子を連想した。靴ひもも満足に結べず、始終なよなよとしている。「趣味はパソコンと漢字パズルです」と、か細い声で答えるのには、思わず「大丈夫か、この子」と心配になってしまった。事実、番組の中では何度も泣いていた。それでも、声を枯らして校歌を叫んでいた。
高松君の祖父は、孫の入部に対して賛成はできなかった。応援団に対しても「右翼的なイメージがありますね。暴力的な問題とか、いじめであるとか」と言っている。正直、僕も近い印象がある。だが、1年を経て高松君は変わった。女子たちからは「かわいい」「大好き」という声も上がっている。持ち前の愛嬌はそのままに、凛々しさを手にしているように見えた。新入生募集の際にも、先頭に立って応援団をアピールしていた。しかし、男子部員の勧誘には苦労を強いられている。今年の入部はゼロ。応援団のことを「元気がいい。変な人たち」とカメラの前で笑う1年生の気持ちも、わからなくはない。
女子の団長が応援団をまとめる
一方、女子のチアリーディング部は人気が安定している。そのリーダーである押田さんは、応援団の団長でもある。引き継ぎの男子部員がいないため、女子に団長を委ねる事態にまでなっていたのだ。前回の放送では、押田さんが団長になることを決意するのがひとつのクライマックスだった。押田さんを発見したことも、この番組の成功の一因だ。
自ら進んでなったわけではない団長だったはずだが、ある覚悟を持って引き受けていることが映像を通して伝わってくる。中でも、半世紀以上女子が入ることがなかった校歌・応援歌指導を見ている姿が凄かった。夏合宿で、最も過酷といわれるOBたちによる地獄の特訓は、前回の放送でも「ここまでやるのか」と驚かされた。どれだけ声を上げようとも「腹から出せ」「もう1度」と指導され、「ふざけるな」とまで言われる始末。応援団員は閉め切った体育館で汗だくになり、声を枯らす。唯一の中学生である高松君も、昨年と同じ必死の形相に戻っていた。これをシゴキと見る人もいるだろうが、押田さんは涙を流していた。チアの仲間の元へと戻り「具体的なことは何も思い浮かばないくらいの緊迫感があるのね、私は自然と涙が落ちるくらいの感情でした」と告白をする。
押田さんに変化が現れた。声の小さい団員たちに「今自分たちがやっていることが、応援されている側からうれしいと思う?」と問い、「いいえ」という答えが返ってくれば「じゃあ何でやってるの?」と問い返す。試合の際には、1点差の負けは応援団の責任とさえ言われるそうだ。場の空気を率先して作り、チームを一丸とさせるのが彼女、彼らの仕事だ。僕は、このような理不尽な問いと答えには違和感を抱いてしまうのだが、意思をまとめるという役割は確かにある。押田さんは、自ら嫌われ役となって団員に緊張感を強いる。
引き継がれる伝統
押田さんが引退する日、文化祭の体育館には大勢の生徒が集まっていた。指揮を執り、一同が校歌を歌う姿を見て彼女は「全校生徒が横に揺れていた。今が人生で1番幸せな時間だと思った」と語る。まだ早過ぎですよ、と僕は思ったのだが、その後、大学生となりキャンパスを颯爽と歩く姿を見て、確かに応援団が彼女にとって青春であったことは間違いないと思った。
団長は高校2年生の本多君に引き継がれた。彼がマジメなのは誰もが認めるが、マジメ過ぎるのが欠点。OBに質問をする際も、トイレにまで押し掛けて「何やってるんだよ、バカ」と怒られていた。しかし本多君がこの長を務め切れることは間違いないはずだ。先輩から厳しい姿勢を学んだはずだから。そして、その後には高松君もいる。この年は中学1年生が2名も入部した。『ザ・ノンフィクション』の取材は、まだまだ続くことだろう。
僕は、この番組を見るたびに、中学時代のバスケ部の苦い思い出がよみがえる。もうあんな時代には戻りたくない。『青春YELL!』のキツい部活を見ると、高松君の祖父のように反対もしたくなる。でも高松君や押田さんの姿を見ると、そう思うことさえ恥ずかしい。なぜなら彼ら、彼女らは「文句は言わせない」と、自ら決めた意思に胸を張っているからだ。押田さんが語るように「目の前にあることを一つひとつこなしていく」ことがいかに大変かを実感する。
文化祭で高松君のおじいちゃんは来校者の前で一生懸命応援をする孫にピンクのリボンを投げ、応援していた。その気持ち、僕もわかります。
(文=松江哲明/映画監督)





