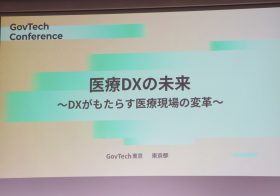米中同時バブル崩壊の懸念強まる…中国経済悪化と米国金融市場が連動

世界的なインフレ懸念を受けて、世界の株式市場は動揺し始めている。米ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は3月下旬の週から8週連続で下落し、世界大恐慌当時の1932年以来、90年ぶりの連続下落を記録した。将来の成長を見込んで買われていたハイテク株の下げが目立ったことが特徴だ。
新型コロナのパンデミックによる景気の冷え込みと闘うため、世界の主要中央銀行は合計約12兆ドルの資金を金融システムに供給する量的緩和を行ったが、約40年ぶりのペースで加速するインフレを退治するため、利上げと併せて量的緩和の巻き戻しを開始せざるを得ない状況に追い込まれている。
今年3月に利上げに踏み切った米連邦準備理事会(FRB)は、6月から量的引き締め(QT)と呼ばれる資産圧縮を実施するといわれている。資産の圧縮幅は前回(2017~19年)のピーク時を上回ることが確実視されている。イングランド銀行(BOE)は利上げを本格させており、欧州中央銀行(ECB)も7月から利上げを開始するとの観測が出ている。
「イージーマネー」の時代の終焉
史上初の世界同時量的引き締め局面に入った現在、低金利で資金調達が可能だった環境は過去のものとなり、いわゆる「イージーマネー」の時代が幕を閉じつつある。金融引き締めは減速し始めている経済にさらに重圧をかけることになるのはいうまでもない。FRBが引き締めモードに転じた影響はすでに米国の金融市場にあらわれている。今年第1四半期の米家計債務は前の四半期に比べて1.7%増の15兆8400億ドルに達し、過去最高となったが、住宅購入と借り換えを合わせた新規融資実行額は前四半期比17%減の8590億ドルと過去5年間で最大の下げ幅となった。借り入れコストが今年第1四半期に急速に上昇したからだ。
借り入れコストの上昇を引き起こしたのは、長期金利の指標である米国債10年物利回りの高騰だ。5月上旬に3%を超え、その後やや下落した。米国債市場の流動性が歴史的な水準にまで悪化していることが背景にある。流動性低下の主な要因はFRBの引き締めモードだが、米国政府がロシア中銀が保有する外貨準備(米国債)を凍結した措置が海外投資家の米国債購入をためらわせているとの指摘もある。
FRBは5月9日に発表した金融安定性報告で「市場全般で流動性をめぐる状況が悪化している」と警告を発したように、金融引き締め局面では米国債に限らず幅広い市場で流動性が低下し、下げ圧力が生じやすい。仏ソシエテ・ジェネラルが株式、米国債、原油の先物の売買動向をもとに算出した「流動性指標」によれば、すべての資産で流動性の枯渇の目安となるマイナス1を下回る水準に落ち込んでいる。リスク資産の売却はすでに始まっているが、流動性の懸念により今後さらにこの動きが加速する可能性が高いといわざるを得ない。
中国経済の失速と信用収縮
市場関係者の間でさらに「FRBの引き締め局面で中国経済が失速すると信用収縮がさらに深刻化する」との危惧が強まっている(5月23日付日本経済新聞)。債務を拡大させることで急成長してきた中国経済だったが、このところゼロコロナ政策も災いして悪化の一途をたどっている。「中国の今年の経済成長率は政府目標(5.5%前後)を大きく下回る」との見方がコンセンサスになりつつあり、「わずか2%にとどまる」との見通しも出ているほどだ。
このような苦境を回避するため、中国政府は5月25日、新型コロナの感染拡大で急減速している経済の立て直しを図る目的で省や市などの幹部ら10万人以上を動員した異例のビデオ・電話会議を開催した。会議を主催した李克強首相は「パンデミックが襲った2020年よりも経済は悪化している」と危機感を露わにし、「景気のてこ入れのために粉骨砕身せよ」と発破をかけたが、中国経済の不透明感を払拭することはできていない。
中国経済の屋台骨である不動産業界がゼロコロナ政策の直撃を最も強く受けているところが気になるところだ。4月の住宅販売額は前年比47%減と過去最大の落ち込みとなり、資金繰りはますます悪化するばかりだ。中国経済のハードランデイングはすでに起きているといっても過言ではない。
中国経済の失速自体が米国の金融市場全般に悪影響を及ぼすなかで、筆者は「特にバブル状態となっている米国のジャンク債(信用力の低い企業が発行する社債)市場が深刻な打撃を被るのではないか」と考えている。ゴールドマン・サックスは5月20日「米ドル建て債を発行する中国の不動産企業の3割以上が今年デフォルトに陥る」との見通しを示した。中国の不動産企業の米ドル債発行残高は500億ドル弱にすぎないが、デフォルトが頻発すれば、米国のジャンク債市場全体のセンチメントを悪化させる可能性が高い。
昨年12月下旬に4%強だった米国のジャンク債の利回りは5月中旬に8%前後に上昇し、今後10%にまで上昇すると予想されている(5月18日付ブルームバーグ)。ジャンク債のスプレッド(米国債10年物との利回りの差)が広がれば広がるほど株式市場が暴落するリスクが高まることは、市場関係者の間では周知の事実だ。株式市場が不調になれば米国の不動産市場も変調をきたすことになるだろう。
「米中同時バブル崩壊」というとんでもないリスクが浮上しているが、頭が痛いのは仮にこれが現実に起こったとしても、リーマンショックの時とは異なり、インフレ防止の足かせをはめられたFRBが金融緩和に転じることが難しいことだ。米中同時バブル崩壊は大恐慌並みの痛みをもたらしてしまうのではないだろうか。
(文=藤和彦/経済産業研究所コンサルティングフェロー)