タピオカブームの仕掛け人が、密かに仕掛け始めてる新たな“台湾ブーム”とは?

飲食の世界では近年「タピオカブーム」があった。甘さのあるお茶の中にでんぷんで出来たボールがたくさん入っていて、その食感を楽しむというものだ。若者が集まる飲食店街で小型の物件はことごとくタピオカドリンクの店になった。そして、たちまち行列ができた。
このタピオカブームは2018年から始まった。これは「台湾ブーム」が発端となったという。当時はインバウンドもさることながら日本から海外に渡航するアウトバウンドも活発で、「エイビーロード」(リクルートライフスタイル、2020年休刊)の「海外旅行調査2019」によると、台湾は渡航先ランキングで5年連続1位だったという。こうして、台湾フードに親しむ人が増えて、タピオカブームにつながっていった。
ブームに先駆けて「タピオカ」に着手
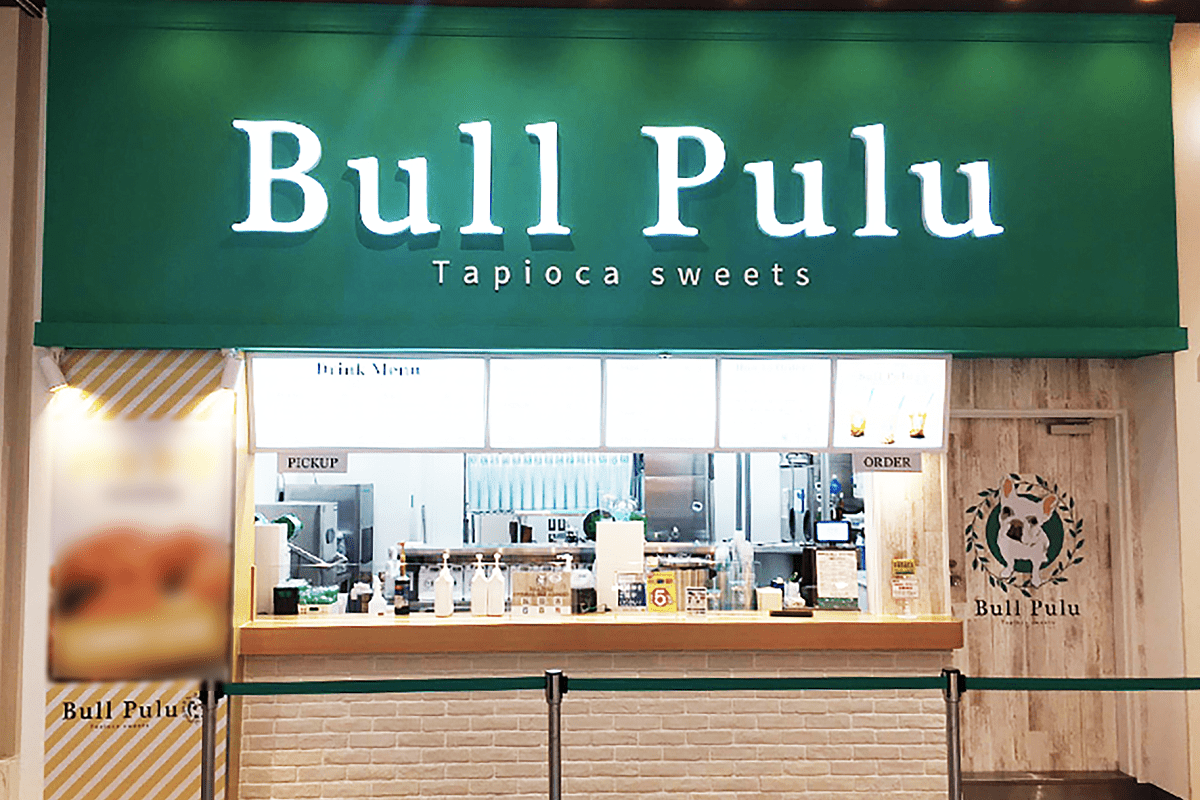
このブームを享受した企業として株式会社Bull Pulu(本社/東京都豊島区、代表取締役会長/加藤二朗)が挙げられる。ちなみに同社が展開するタピオカ専門店「Bull Pulu」は、現在全国に74店舗を展開している(うち26店舗が直営/2021年8月末現在)。
Bull Puluの1号店がオープンしたのは2010年のこと。ブーム到来の8年前である。台湾ブームも始まっていない。それは会長である加藤氏の前職での活動がきっかけとなった。
加藤氏は大手流通・小売業に勤務していて、台湾に関わる機会があった。現地でタピオカが大きなビジネスになっていることを目の当たりにして「これは日本で大きなビジネスになる」と感じ取った。加藤氏は一方で父が事業とする飲食業もみていた。そこで「自分たちでできるのでは」と考えてタピオカ事業を立ち上げた。

その後、知人から「FC(フランチャイズ)をやらせてほしい」という声が相次ぐようになった。しばらくして、日本では「台湾ブーム」が到来し、タピオカ人気を巻き起こした。加藤氏は、父の会社に本格的に関わる必要性を感じ会社に退社を申し出て、19年12月の退社がかない現在の会社に就いた。
当時のタピオカブームはすさまじいものがあった。FC募集を公開していなかったが、知人からの要望が相次いだ。19年の1年間で40店舗を出店した。コロナ禍になっても、すでに出店が決まっていたところがあり、厳しい経営状況でありながらも店は増え続けていった。居抜きで出店するというパターンもいくつかあった。
出店コストは、スケルトンからだと1200万~1300万円、居抜きであれば500万~600万円で出店可能。標準店は8坪、これで月商300万~400万を狙う。損益分岐点は200万円。これがタピオカブームの当時には1000万~1500万円を売っていた。
しかしながら、タピオカブームは2020年に入り鎮静化した。その要因について加藤氏は、まず「2019年の終わりごろにブームが過熱して物件の取り合いが始まり、これによって家賃相場が上がるようになった」、さらに「コロナ禍となり、マスクをつけるようになったことでタピオカドリンクの“飲み歩き”ができにくくなったことが、これまでのタピオカファンを遠ざけるようになったのではないか」と語る。
「台湾カステラ」とドリンク事業を育てる

同社がタピオカ事業と共に育てていたものが2つある。一つは「台湾カステラ」を持ち帰り品として拡販すること。もう一つは、同社の関連会社である株式会社ドリンクリンクの事業だ。
前者の台湾カステラとは、日本のカステラと比べるときめが細かく濃密でクリーミーな食味であることが特徴である。カステラをはじめとした和菓子や、ケーキなどの洋菓子とも異なり、スイーツの選択肢を広げる存在である。
Bull Puluの既存店では台湾カステラを焼成する機能を持つところもあるが、この商品の多くは東京・駒込の店舗や埼玉・和光の工場で焼成し、それを冷凍して各店舗に配送している。和光の工場では、この他、餃子の製造を行い、この年末からタピオカも製造してクオリティアップに磨きをかける。
後者の事業とは、ドリンクリンクが輸入しているタピオカ、シロップ、茶葉などの商品をB to Bで飲食業者に提供していること。例えば同社のシロップを仕入れた居酒屋では、それを使用して自社オリジナルのサワーを提供したり、かき氷に使用しているパターンもある。これらの商品は日本のメーカーにはない、本場“台湾”を感じさせ、また使い勝手のよいことが既存のユーザーから喜ばれている。

台湾食文化を基軸とした「直営部門」
加藤氏はコロナ禍にあって、「当社はこれからどのように進むべきか」ということを一生懸命考えたという。その結果「直営部門」と「フランチャイジー部門」の両輪で展開していこうと方針が定まってきた。
まず「直営部門」は、これまで同社のタピオカ事業が大きく躍進することになった「台湾食文化」を基軸として推進していく方針だ。そこで、創業の事業であるBull Puluは“台湾ポップカルチャー”をコンセプトとして、現状の商業施設を中心とした立地で展開する。本場イタリアのエスプレッソクオリティを核としたコーヒーショップチェーンの「セガフレード・ザ・ネッティ」と業務提携を行い、ここのメニューを提供していくなど、タピオカに加えて多様なメニュー構成を取る。

次に、「Bull Pulu カフェ」。これは台湾茶のカルチャーをコンセプトとして、駅ビル、百貨店に展開して、台湾茶が楽しめるほか、持ち帰りのスイーツを充実させる。
そして、フード業態の「Bull Pulu Tenshin」「灯」。台湾屋台フードや豆花(トウファ)をはじめとした台湾スイーツを提供する。さらに、「生餃子 小籠包 餃子」。これは、生餃子の他に小籠包、餃子の販売店である。さらにBull PuluやBull Pulu TenshinはFC本部としての事業を推進する。

客層を拡大する「フランチャイジー部門」
もう一つの「フランチャイジー部門」は、すでにフランチャイジーとしてさまざまな飲食店を展開していることを基盤として、これらを推進していく構えだ。
まず、加藤氏の父の代に基盤をつくった長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」が現状2店舗存在する。次に、日常外食にエンターテインメントとこだわりの要素を提案するB級グルメ研究所が本部のナポリタン専門店「パンチョ」が1店舗存在する。さらに、台湾ではスイーツや台湾フードの人気ブランド「騒豆花」(サオトウファ)が1店舗存在する。
そして、これから高級パン「みるく」を展開する。これは足立区北綾瀬の牛乳販売店が開発したブランドで商品にはプリンやソフトクリームもある。これが業態として加わることによって、同社のターゲットがこれまでの若い女性中心といった固定的なファンから老若男女へと大きく広がることが想定される。
コロナ禍以前の同社の年商は27億円であったが、コロナ禍で15億円となった。それを今期19億円に巻き返し、5年後40億円を計画している。同社がこれから成長していく場所として想定している場所の多くは商業施設である。これは加藤氏が過去大手流通・小売業を経験していたノウハウを背景としていて、過去から一貫して得意とする場所での成長を描いている。
同社を成長させてきたタピオカはコロナ禍で揺らいだが、一方で「台湾食文化」を基軸としてきたことを改めて見直して新しいスタートを切っている。
(文=千葉哲幸/フードサービスジャーナリスト)










