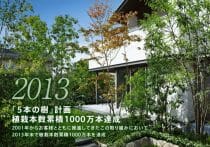マンション解体、国立市も建設を承認していた…着工後も住民が反対→市は対応せず

東京・国立市のほぼ完成済の新築マンション「グランドメゾン国立富士見通り」が、建物の構造上の問題や法令違反はないにもかかわらず解体されることが決定した問題。富士山の眺望など景観が損なわれるとして周辺住民から反対の声が強いことが理由だが、国立市は着工前に建設事業者の積水ハウスから提出された計画について、条例に定める各種基準に適合していることを確認し承認していたことがわかった。着工後も住民から反対の声が出ていたことを受け、市は協議の調整や仲介などの対応は行っていなかった。建設業界関係者からは「いったい何のために市の承認を得たのか」「市による承認の意味がない」「行政の不作為」との声も聞かれる。また、積水ハウスは引き渡しを目前に控えた今年5月に天空率に関する建築計画の変更を東京都に届け出ていたとも報じられており、「通常ではあり得ず不自然」(元ゼネコン社員)との疑問も聞かれるが、背景に何があるのか。業界関係者の見解を交えて追ってみたい。
同マンションは、国立駅の南口から南西に延びる「富士見通り」沿いの物件。一橋大学に近い閑静な住宅街に建ち、10階建てで1戸あたりの専有面積は約65~75平方メートル、分譲予定価格は7200万円~。部屋からは富士山を眺望できる点が魅力の一つだ。
国立市でマンションなどの建物を建設するには、建設事業者は着工前に東京都に建築確認申請を行い承認を得る必要がある。また、一般的には、建設途中でも自治体による中間検査を受けて中間検査合格証の交付を受け(3階建て以上の共同住宅の場合)、工事完了後は完了検査申請をし、検査済証の交付を受ける必要がある。これらに加えて国立市では、国立市都市景観形成条例の大規模行為の届出制度に基づき、着工前に市に対し届出を行う必要があるが、積水ハウスは行政手続き上は問題なかったとしており、これらの手続きは適正に行っていたとみられる。
今回問題となっているマンションについて、国立市はいう。
「市が行ったのは、自主条例として定めている国立市まちづくり条例の手続きの中で、計画が条例に定める各種基準に適合していることを確認したという旨の承認となっております。その後、建築確認として指定検査機関にて、法令に定める各種基準に適合していることを確認した後に着工に至ったと認識しております」
国立市「建物のボリューム感の低減などを指導してきた」
12日の国立市議会で永見理夫市長は「建てるときに住民の不安を踏まえて建物のボリューム感の低減などを(積水ハウスに)指導してきた」と発言しているが、建設中に自治体が事業者に指導などを行うことはあるのか。
「私の知る限り、法令で決まった検査以外で自治体から指導などを受けるという事例は聞いたことがありません」(建設会社社員)
市がいう「指導」とはどのようなものなのか。国立市に聞いた。
「国立市まちづくり条例に基づく指導を工事着工前に2回行っております」
国立市は良好な景観づくりに力を入れている自治体として知られている。「国立らしい景観を守り育て未来に引き継ぐ」などと定めた「国立市 景観づくり基本計画」を策定し、施策として「良好なまちなみ・景観の保全」「地域特性を活かしたまちなみの形成」を掲げている。1997年には国立市都市景観形成条例を制定し、建物の建設について景観への配慮を義務付けている。市は「周囲に比べ高さや大きさのある建築物の景観的工夫」として「大規模な建築物の建築を行う際には、関係者と連携・協働し、周辺の景観と調和するよう誘導します」としている。
今回のグランドメゾン国立については、3年前の2021年2月に計画が公表された後、住民から景観が損なわれるとの声があがった。そのため、21年6月、国立市まちづくり審議会で諮問にかけられ、審議会からの答申を踏まえて市は積水ハウスに対して建物のボリューム感を見直すよう「指導書」を提出。積水ハウスは11階建てから10階建てに変更し、23年1月に着工した。
「協議の調整や仲介などの対応は行っておりません」
積水ハウスは解体を判断した理由について11日に発表した文書で「現況は景観に著しい影響があると言わざるを得ず、本事業の中止を自主的に決定しました」としており、着工後も周辺住民から反対の声があがっていたことがうかがえる。こうした状況のなか、市は積水ハウスと住民の間の調整に乗り出すなど、何らかの対応を行ったのだろうか。
「工事着工後については、近隣住民から陳情は出されておりませんし、協議の調整や仲介などの対応は行っておりません」(国立市)
元ゼネコン社員はいう。
「国立市は景観を重視するとして厳しい条例を定めており、そのためきちんと手続きをして承認を得て着工し、ほぼ完成したにもかかわらず住民の反対で解体に追い込まれるとなれば、建設事業者としては何を担保にして建設してよいのかわからない。こんなことがまかり通れば、リスクが高すぎて、国立市にマンションを建てようと考える事業者は出てこなくなる。市としては『行政手続きは済んだので、あとは民間事業者と住民の間の問題なので関与しませんよ』というスタンスなのかもしれないが、このような事例が生じると住宅供給の面で将来的に住民の生活に支障が生じる懸念もあり、市として調整なり仲介なりに入ってもよかったのではないか。行政の不作為だという声もあり、なんのための市なのか、わざわざ条例に基づいて手続きをして承認を得たのは何のためだったのかと疑問を感じます」
不動産事業のコンサルティングを手掛けるオラガ総研代表取締役の牧野知弘氏も11日付け当サイト記事で次のように指摘していた。
「事業者が適切な行政手続きを踏んで建物を建設し、それに対し住民が反対して解体に至るという一連の事態について行政が対処しなかったという『行政の不作為』を問う声もあるでしょう。このような事態が起これば、業者としてはあまりにリスクが大きすぎて、もう国立市に新たにマンションを建設できなくなります。それが果たして街の発展にとって良いのか、という点は議論があるでしょう」
積水ハウス、不自然な動き
10日付「朝日新聞」記事によれば、積水ハウスは5月、天空率に関する建築計画の変更を東京都に届け出て認められていたという。
「これは非常に不自然だと感じます。完成した建物の天空率が着工前に届け出ていた内容と異なると、建物を取り壊さなければならなくなるので、変更する場合は着工前に届け出る必要があります。例えば、工事が進むなかで届け出の内容とズレていることが判明し、自治体の担当者に内々で相談しており、『数値が確定した段階で変更の届け出をしてくださいね』というかたちで握っていたという可能性は考えられなくはない。ただ、基本的には設計書どおりに建設するので、かなりイレギュラーです」(建設会社社員)
市議会で永見市長は「周辺地域は再び解体工事に直面することになり影響が必ずある」と懸念を示している。解体はリスクが大きな作業なのか。
「建物の建設は下から上に順繰り作業を進めていけばよいですが、解体は『ここを壊すと、どこにどういう影響が出るのか』を予測しにくい面があり、倒壊するリスクもゼロではないため、建設よりリスクは高いかもしれません。現場周辺に埃が飛散したり、道路に瓦礫が漏れ出て事故が起きる危険もあります」(建設会社社員)
(文=Business Journal編集部)