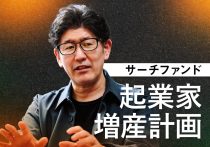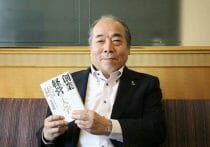本気で挑むなら、まず草野球を勝ち抜け──凡人のための逆算起業論

●この記事のポイント
・ファンド「ブーストキャピタル株式会社」の代表取締役である小澤隆生氏が語る「成功する起業家」の3つの力
・起業を見据えたとき、やっておいたほうがよいこと、経験しておくべきことは何か
・目標に対して最適なものを選んでいく、という逆算の方法
起業家に必要な能力、と聞くと何を思い浮かべるでしょうか? 「誰にも思いつかない奇抜なアイデア」「ずば抜けたビジネス感覚」など、人並み外れたフレーズを思い浮かべる人は多いはず。
しかし、楽天での球団創設や、決済サービス「PayPay」の立ち上げを牽引し、現在はファンド「ブーストキャピタル株式会社」の代表取締役である小澤隆生氏が語る「起業家に必要な要素」は、それらとはまったく逆をいくものです。
起業を妄想で終わらせず現実に変える、小澤氏の徹底したリアル思考とは——。
●目次
- 小澤氏が語る「成功する起業家」3つの力
- 「起業=天才の特権」じゃない!凡人こそやるべき“下準備”とは
- 大谷を目指す前に草野球で勝てるか?起業に必要な逆算思考
- 座学は成立しない!起業家に必要な学びの方法とは
- 買えなければつくる。ブーストキャピタルのファンド構想
小澤氏が語る「成功する起業家」3つの力

——小澤さんが考える、成功する起業家の特徴や必要な要素はなんでしょうか?
私は大きく、
見抜く力
失敗力
徹底力
この3つの力が重要であると考えています。
見抜く力は、起業のスタートにおいては、おもに市場選びに活かされます。どんなに優秀な人間でも、現状でビジネスの可能性やニーズがあまり大きくない市場を選んでしまうと成功しません。私は、ビジネスにおいて本当に大事なものを「センターピン」と呼んでいるのですが、そのセンターピンをどこに置くのか? を見極められる人が、本質を見抜く力がある人ですね。
2つ目に挙げた失敗力は、上手に失敗させる力、失敗から学ぶ力ともいえるかもしれません。実は、先ほど話した事業におけるセンターピンは、見抜く力があったとしても外れてしまうことが多いものなのです。しかも、一度や二度ではききません。センターピンが外れる可能性がある事業に対しては本来、資金や労力は最小限で仕掛けていくべきなのですが、最初からかなり大金を投資して「大失敗」にしてしまう人も多くいます。失敗力とは、最小限の金額、最小限の労力を使って、成功に向けた修正をかけていくための失敗を重ねられる能力、ということですね。
——一見、金額や労力を最小限にしたスタートは当たり前のことのようにも思えますが、多くの人が「大失敗」に至る理由はどこにあるのでしょうか?
多くの人にとって起業や新規事業は初めての試みであることが多いため、動き方がわからない上、これらに関するプロセスが確立されていないことも原因です。たとえば、すでにやり方が確立されている化学の実験であれば、最初は試験管からスタートして、徐々に規模を大きくしていきますよね。しかし、これがビジネスになると最初から生産工場の建設をしてしまう人が信じられない割合で存在するのです(笑)。
一方で私は、上手に失敗を重ねて成功が見えている状態であれば、大きく勝負に出るという行動はしてもいい、と考えています。
そして、3つ目の徹底力。私が最も重要だと考えている能力です。何があってもやり抜く力のことですね。この徹底力がなければ、成功するまでに何度も失敗を重ねて修正していくこともできません。見抜く力や失敗力が備わっていても、この徹底力がなければ成功はないともいえます。
「起業=天才の特権」じゃない!凡人こそやるべき“下準備”とは

——起業を見据えたとき、やっておいたほうがよいことや経験しておくべきことはありますか?
メンバーとして新規事業を含む起業活動のプロセスに関わったという経験は、できるのであればしておいたほうがよいですね。前段でもお話ししたように、起業活動に関してはプロセスを知らない人が多い上に、教えてくれる人もそう多くありません。もちろん、起業活動に同じパターンはありませんが、目の前で見た場合、それらに対する一定の理解ができあがります。
起業が“自分ごと”になることもメリットです。すでに大きなサービスをつくった起業家を、スポーツ選手でいうと大谷翔平選手のような存在のように捉えてしまうことはないですか? しかし、実はほとんどの場合、ビジネスには特別な才能が必要になることはありません。起業活動に関わることで、「コツコツ真面目に積み上げていくことでここまでできるのか」という、“自分にもできる感”を味わうことができるんですよね。
——しかし、起業活動に携わるには、機会に恵まれるかどうかも影響しますよね。
その場合は、自分がやろうと思っている事業や規模の会社がどうやって立ち上がったのか? をオープンソースで事例研究するのがよいですね。ビジネスにも、勉強やスポーツと同じく、「こういう方法を取れば、一定の確率でここまで成長できる」というフレームが存在するためです。逆にこの研究を怠ると、特定の一社だけを参考にしてモノマネしたり、場当たり的に右往左往したりすることになります。やろうと思えば何百社も研究できるはずなのですが、それをやらずに起業しようとする勉強不足な人が非常に多いです。
——起業を目指す人が勉強不足に陥ってしまう原因はどこにあるのでしょうか?
まず、事例研究がどれだけ重要なことなのか理解していないから、ですね。起業に関することは、受験や部活とは違い、強制力を持って「これをやれば勝てる」と教えられるような機会がほとんどないため、事例研究を「やらなければいけないこと」と認識できていないのです。また、起業のプロセスが多岐に渡りすぎているように見えて、一社一社の事例を研究していくことが有意義なものに感じられない、ということもあるかもしれません。
もうひとつの原因は、自分自身のアイデアに惚れ込みすぎることです。一刻も早く着手したいという気持ちが先行して、さまざまな情報を自分自身にとって都合よく解釈し、ネガティブな情報を排除していくのです。情報を排除するという行動が、結果的に勉強不足につながっていきます。
大谷を目指す前に草野球で勝てるか?起業に必要な逆算思考

——起業を目指す人の中には、そういった自分自身のアイデアに惚れ込んだり、非現実的な目標を掲げている人は少なくないのでしょうか?
いえ、まったくそんなことはないですね。少なくともブーストキャピタルに面談に来る人の多くは、数値的な目標をすでに持っていたり、自分の会社をつくって意思決定する立場にいたいと考えていたりする人がほとんどです。ごく稀に、「起業するからにはユニコーン起業に」など、漠然とした目標を掲げてくる人もいますが、私からすると「いやいや、ユニコーンって……なめんなよ」という気持ちになることもありますね(笑)。
もちろん、夢を大きく持つことを推奨する経営者もいますし、私もそういった大きな志を持つなとは思いません。しかし、その目標にリアリティがあるか? という部分を認識するメタ認知が足りないと、ただの妄想で終わってしまいます。たとえば、「大谷翔平選手のようになりたい」と思ったときに、地元の草野球チームですら勝てない状態で、ひらすらその目標だけ掲げ続けるのはリアリティがありません。まずは「草野球で勝つ」、それから「甲子園に出る」など、目標から逆算した段階的な成長戦略が必要です。
——小澤さんのこれまでの起業や事業も、このような戦略で行われていたように見えます。
基本的には目標に対して最適なものを選んでいく、という逆算の方法です。一番最初の起業に関していえば、「家業の借金を返す」という目的が先にありました。その金額を稼ぐためにどんな仕事が最適か? をまず調査して起業家を選択し、自分自身の年齢とビジネス的なケイパビリティを加味した結果、参入すべき市場はITだという結論に至った結果の起業です。
「自分が今こんな能力を持っているから」「こんなことをやりたいから」という地点からの積み上げではないですね。この考え方は、M&Aに関しても同じことがいえます。最終的な設計図を見たときに、すでに存在しているコンテンツを入れ込むことが最適な場合、一からつくるのではなくM&Aという手法をとる、というイメージです。
座学は成立しない!起業家に必要な学びの方法とは
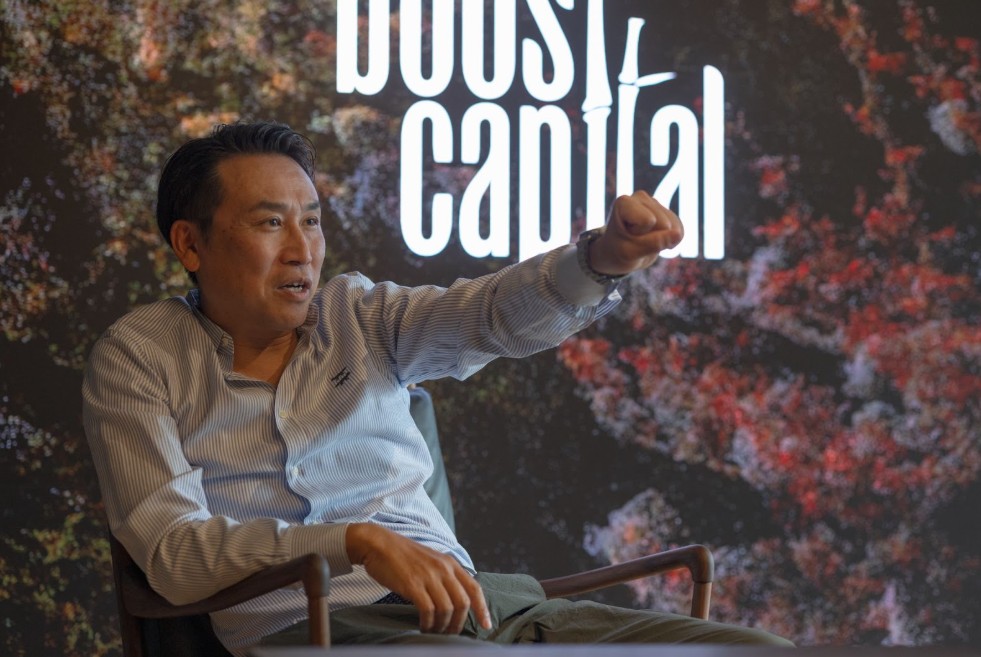
——ブーストキャピタルでは、人材募集でも、その仕事に必要な能力や経験、展望を明かさずに募集をかけていますよね。
そうですね。何をやるかは言わない状態で新規事業や新会社の人材募集をかける、という方法をとっています。一見、無茶苦茶な募集方法にも見えると思いますが、実はかなりの応募が来るのです。「なんでもいいからやってみたい」「何かで人生を切り拓いてみたい」という人はかなりの割合でいます。そういった人からの応募が多いですね。私は、やりたいことが明確にあるよりも、こういった「なんとなく何かやりたい」という人のほうがマジョリティだと考えています。
——ブーストキャピタルでは、起業家志望や人材募集で集まった方々に、ファンドとしてどのように関わっているのでしょうか?
我々はVCとして起業に関わるだけではなく、起業家育成プログラムなども行っているのですが、いわゆる座学で何かをレクチャーするということはなく、家庭教師的に伴走していくスタイルをとっています。
起業というものは、それをやる人物もやる内容もそれぞれ状況が異なります。すべてを「起業」と一括して扱うことは、いわばスポーツも将棋も勉強もすべて同じカテゴリに入れてしまっているのと同じです。とてもではないですが、座学での教育は成立しません。まずは市場選び、そしてどんな会社にするのか? またはどんな会社を買収するのか? という部分から一緒に進めています。
——市場選びの段階からすでに入っているのですね。
事業が成功するか否かに、市場選びが大きく影響するためです。それに、私自身の人生から「何をやるかを自身の強い意思で選ぶこと」に、そこまで重要性は感じていません。私は最初にIT分野で起業し、楽天時代にはプロ野球球団の立ち上げにも関わりましたが、それまでIT関係の仕事をやりたい、プロ野球に関わりたいと思ったことはありませんでした。しかし、それでも十分に人生が変わったし、十分どころか十二分に楽しかったんですよね。我々と関わって事業をやろうという方が同じように感じてくれるだろう、という自信は常に持っています。
買えなければつくる。ブーストキャピタルのファンド構想

——最後に、ブーストキャピタルの今後の展望について教えてください。
ブーストキャピタルは、つくる・育てる・買うの3つを行うファンドです。M&Aなどの買収が成立しない場合も多いため、つくる・育てるという選択肢も持っておくことでファンドとしての幅が広がると考えたことが起因しています。私やメンバーがこれまでに起業や譲渡、買収などの経験があることで、この3つの要素に寄与できる実績を持っていることも大きな強みですね。
今年は会社を「つくる」にフォーカスして数社、「買う」に関しても1〜2社できたらよいですね。この取り組みが、今後どうスケールしていくかが見えてくるには、10年ほどの時間がかかるかなと考えています。しかし、ファンド経営者に事業経営の経験者は少ないですし、私のこれまでの経験から起業に対する抵抗がないことは、ブーストキャピタルのファンドとしての大きなアドバンテージだと感じています。
*
小澤氏が語るのは、天才のサクセスストーリーではなく、常に地に足がついた起業に対する見解です。小澤氏の話から見えるのは、「起業や新規事業に必要なのは成功までの確実な道筋や劇的な展開ではなく、事業に合った“逆算の戦略”」ということ。
「何をやりたいか」だけにとらわれることなく、「目的地までどう歩いていくかを突き詰める視点を持てたとき、起業が現実的な選択肢になっていくのかもしれません。