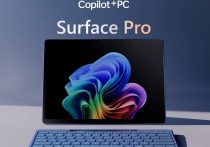OpenAI、アイブ氏の会社買収の裏にアップルからの拒絶?パーソナライゼーションめぐる焦り
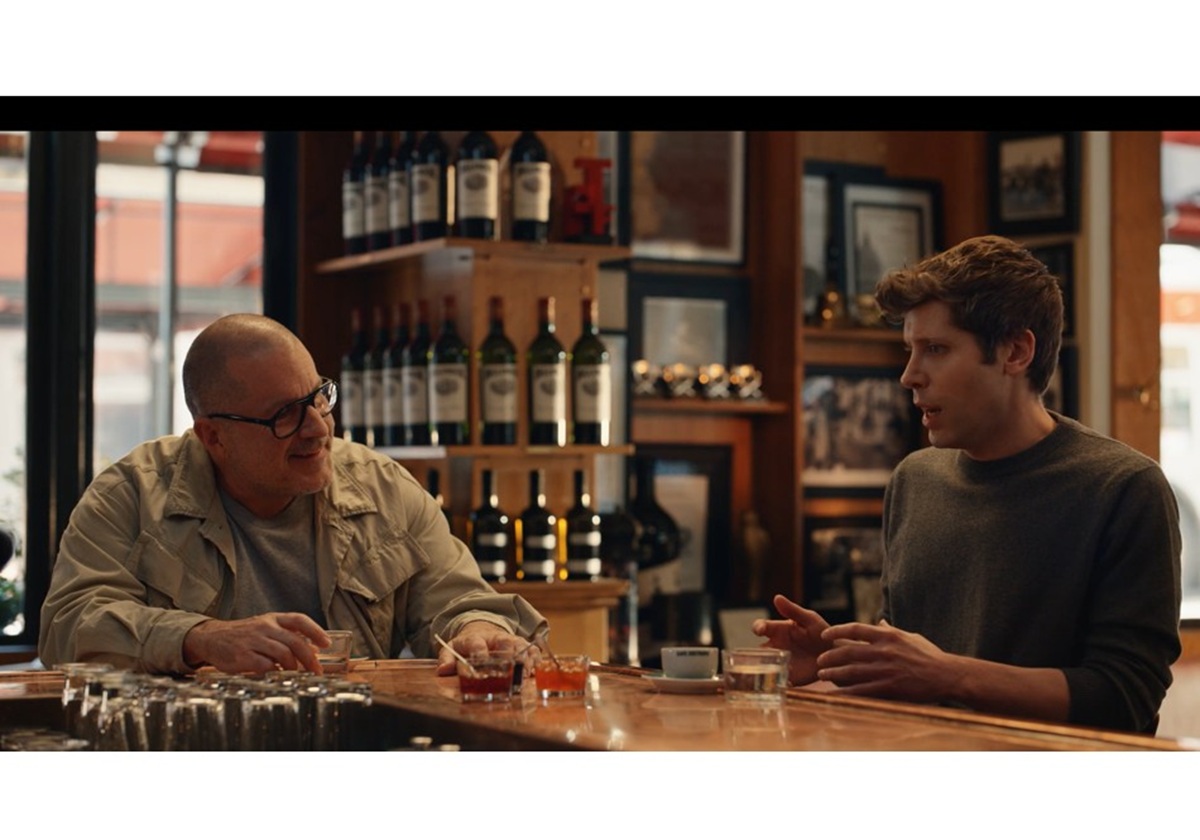
●この記事のポイント
・米OpenAIは、米アップル元幹部でスマートフォン「iPhone」のデザインをリードしたジョニー・アイブ氏が昨年に創業した米io Productsを買収
・スマホのように指で画面を操作する必要がない新AI端末を来年に発表するとの観測
・AI開発競争のテーマがパーソナライゼーションに移行。OpenAIはグーグルらに対し出遅れ
米OpenAIは今月21日、米アップル元幹部でスマートフォン「iPhone」のデザインをリードしたジョニー・アイブ氏が昨年に創業した米io Productsを買収すると発表。買収総額は65億ドル(約9300億円)とも報じられているが、ChatGPTをはじめとする生成AIを開発するOpenAIが、巨費を投じてAI端末のハードウェア企業を買収するとあって、その目的をめぐり世界で関心が寄せられている。OpenAIは新AI端末を来年(2026年)にも発表するとしており、スマホのように指で画面を操作する必要がないヘッドフォン型の端末を開発するという報道も出ている。だが、すでに米グーグルや米メタをはじめとする有力テック企業が、音声で操作するAI搭載型のメガネ型デバイスやヘッドセット、ARグラスなどの開発を進めており、競争が激しい領域となっている。そうしたなかで後発組となるOpenAIの次世代ハードが優位に立てるのか、懐疑的な見方もあるが、なぜ同社は参入するのか。そして、同社に勝機はあるのか。専門家の見解を交えて追ってみたい。
●目次
強力な競合他社に肩を並べることができるのかは未知数
世界的な生成AIブームの火付け役となったOpenAIが大きく成長して注目されるきっかけとなったのは、2019年から米マイクロソフトから累計約2兆円もの出資を受けたことであった。22年にはChatGPTをリリースし、マイクロソフトはChatGPTに使用される言語モデル「GPT-3」の独占ライセンスを取得。23年にはマイクロソフトはChatGPTの技術を活用したAIアシスタントツール「Microsoft Copilot」をリリースするに至った。そのマイクロソフトも今月、AI開発者向けのサービスでイーロン・マスク氏が率いるxAIとの提携を発表。すでにクラウドサービスのプラットフォーム「Azure」上では中国ディープシークのAIモデルを展開したり、米メタの「Llama 2」をAzureとWindowsでサポートするなど全方位戦略をとっており、独自のAIモデルも開発中とみられている。このほか、グーグル(「Gemini」)、アップル(「Apple Intelligence」)をはじめ多くの有力テック企業が生成AIモデル開発に力を入れるなか、OpenAIの優位性は薄れつつあるともいわれている。
そのOpenAIが、なぜハードウェア事業に本格参入するのか。
「生成AIの領域に限っていえば『GPTでなければできない』というものは、現在ではほとんどなく、ソフトウェア面だけでひたすら性能向上や機能拡張を追求していくだけでは、いつかは限界が来るので、これまでとは違ったアプローチが必要になってきています。また、今月には完全な営利企業化を断念すると発表したものの、ソフトバンクグループ(SBG)などから400億ドル(約6兆円)の出資を受けることで合意するなど、多額の投資が流入しており、成長に向けて資金を有効に使っていく必要にも迫られています。こうした状況のなかで繰り出した手の一つが、AI端末の開発だということでしょう。
ただ、グーグルはスマホ端末のGoogle Pixel、アップルはiPhoneを持っており、マイクロソフトとメタも各種ハードウェアを開発しており、AI開発を手掛ける大手テック企業はハードウェアの開発に関して豊富な実績を持っています。OpenAIが今から端末の開発を本格化させ、そうした強力な競合他社に肩を並べることができるのかは未知数といえます」(中堅AI企業幹部)
製品化までの間に競合他社が先を行ってしまう可能性も
エクサウィザーズ「AI新聞」編集長・湯川鶴章氏はいう。
「個人の考え方、趣味・嗜好、行動履歴といったものをすべて理解した上で、その個人に最適な答えを返すパーソナルAIエージェントが急速に普及してきており、そのパーソナライゼーションの部分の開発をめぐる競争がAI市場の勢力図を大きく左右するといわれていますが、膨大な量の個人ユーザーのデータを持つマイクロソフトやグーグルと異なり個人情報をあまり持っていなかったOpenAIは、これまでアップルと組みたいと考え接近していました。アップルのiPhoneのなかにデフォルトでGPTを組み込んでもらうことによって、アップルが持ってるユーザーの情報を使ってパーソナライゼーションを強化しようとしていたんですね。ですが、アップルはなかなか首を立てに振らずに、あくまでも外部アプリの一つとしてしか取り扱ってくれず、デバイスを使ったパーソナライゼーションが思うようにできない。そこで自分たちでデバイスをつくるしかないと考え、アイブ氏の会社を買収したのだと推察されます。
ですが、新端末の発表は1年以上も先の予定ですし、アイブ氏は天才的なデザイナーなので、ものすごい端末を開発する可能性はあるものの、製品化までの間に競合他社がどんどん先を行ってしまうという展開は考えられます。
また、AIの競争のカギがコストパフォーマンスになりつつあるなか、グーグルは非常に効率の良いデータセンターを自前で運用することで高い価格競争力を実現していますが、OpenAIがソフトバンクとのStargate Projectを通じて進めるデータセンターの建設は、完成が2~3年先になるので、そのあたりの年単位のタイムラグというのがOpenAIにとっては不利に働くかもしれません」
(文=BUSINESS JOURNAL編集部、協力=湯川鶴章/エクサウィザーズ・AI新聞編集長)