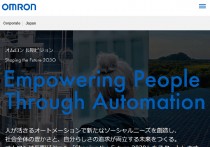「のれん」定期償却が不要になればスタートアップの活性化につながる?メリットとリスク

●この記事のポイント
・政府の規制改革推進会議、答申にM&Aで生じる「のれん」の費用処理について検討することを盛り込んだ
・スタートアップは「のれん」が高くなりがちで、買収のハードルとなりの成長を妨げるという指摘も
・のれんの定期償却が不要になれば、M&Aを実施しやすくなる
政府の規制改革推進会議は5月28日にとりまとめた答申に、M&A(合併・買収)で生じる「のれん」の費用処理について検討することを盛り込んだ。「のれん」とは、M&Aの相手企業が持つ数値化できないブランド力などの資産の対価として支払う代金であり、純資産額を上回って支払う代金を指す。日本の会計基準を採用している企業は、これを販管費として20年以内に定期償却する必要があり、その分、毎年の営業利益が低くなるという影響が生じる。そのため、日本企業が買収案件で海外企業と競うようなケースでは、日本企業は「のれん」の定期償却を見越して買収金額を提示しなければならず、競争で不利になることがある。また、スタートアップは純資産額が低いことが多いため「のれん」が高くなりがちで、買収のハードルとなり、スタートアップの成長を妨げるという指摘もある。もし「のれん」を定期償却する必要がなくなれば、スタートアップの活性化につながる可能性はあるのか。専門家に取材した。
●目次
メリットとデメリット
欧米企業が採用する国際会計基準(IFRS)などでは、「のれん」を定期償却する必要はなく、価値が減少したときのみ減損処理するかたちとなっている。「のれん」の非償却が認められると買収のハードルが下がる一方、買収先の急激な業績悪化に伴い多額の減損を計上しなければならなくなるリスクも生じる。
現在の「のれん」の償却に関する会計制度には、課題や問題があるといえるのか。数多くの企業再建を手掛けてきた企業再生コンサルタントで株式会社リヴァイタライゼーション代表の中沢光昭氏はいう。
「誰かにとってデメリットがあることは、誰かにとってはメリットがあったりするので、のれんの定期償却が絶対的に悪いということではないと思います。のれん償却費が費用となってA社の利益を押し下げられることはA社にとってデメリットだとしても、株主や債権者にとっては、A社が割高な価格で他社をM&Aをしてしまうというような事態を抑止するというメリットがあります」
制度の変更はスタートアップの成長を推進することにつながる可能性はあるのか。
「銀行や投資家から見ると、のれんの償却費の負担が重いといった、どんな理由があっても赤字は好ましくありませんし、見かけ上の利益が低くなっても同様です。のれんや減価償却費など実際の現金の移動が伴わない費用については、すぐに現金に影響を及ぼすわけではなく、ただの会計処理の問題だとはわかっていても、だからといって赤字や低利益が許されるということにはなりません。もし、のれんの定期償却が不要になれば、A社にとっては銀行融資を含めた資金調達の手段を維持しやすくなるので、M&Aをやりやすくなります。一方、M&Aへの障壁が低くなることで高値掴みをしやすくなるので、A社にとって本当の意味で良いことかどうかはわかりませんが、高値掴みをするということは高値で売る側がいるので、全体的な観点からはイーブンでもあります。
取引が増えるのでM&A仲介会社は業績が良くなり、納める税金も多くなるので税務署は喜ぶでしょうし、お金の流通量が増えれば増えるほど景気は良くなるとされるので、世の中の空気感にも良い影響はあるのかもしれません。税務処理がどうなるのかはわかりませんが、経済に関わるインフラを国際基準に合わせていくというメッセージを海外に発信できるのは日本にとってはよいことでしょう。
個人的には、減価償却費の期間を自由に設定できれば商取引は活性化されて景気に良い影響が出ると考えています。利益が多く出る年は大きく設備投資をして、それを税務上すべてその年の費用に計上できれば、設備投資などは活発化するはずです。利益が出る予定だった企業からの目先の税収は減るように見えますが、利益が出ている会社から設備投資の発注先にお金が流通するので、その発注先の従業員が納める所得税や消費税が増え、税収増となるはずです」
会計基準を海外のものに合わせていくという流れ
メガバンク関係者はいう。
「スタートアップの活性化を促す可能性はあると思います。一方で、買収先の業績が悪化した際に減損を計上するかどうかの判断が、企業に委ねられる部分が大きくなるため、突発的に一気に減損計上が発生するというリスクが高くなりますし、買収のハードルが低くなると精査が甘くなるということも考えられるので、株主・投資家にとっては新たなリスクも生じることになります。よって、トータルでみるとメリットとデメリットのどちらが大きくなるのかは、なんともいえませんが、会計基準を海外のものに合わせていくというのが基本的な流れなので、『のれん』の償却についても見直しの方向で進んでいくのだと考えられます」
(文=BUSINESS JOURNAL編集部、協力=中沢光昭/リヴァイタライゼーション代表)