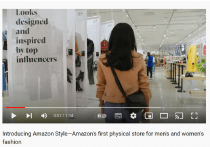日本市場はユニクロだらけになる…私が提唱する東京ショールーム戦略とは

過日、某経済紙に、フランス・パリで服を破棄した場合、ペナルティが課せられるという話が掲載されていた。
また、世界的な投資銀行での国際会議に招かれ、そこで「今、世界では毎年30%の過剰在庫が量産されている」という話を聞いた。一年で30%である。この大量の衣料品の残骸は、フィリピンやアフリカで、CO2をどんどん出しながら燃やされている。
この衝撃的スクープは、AmazonなどでDVD販売されている「The true cost」というドキュメンタリー映画に映し出されている。ファッション業界にいる方は必見、そうでない人も「環境破壊第二位」の汚名を着せられたファッション産業の実態を知るには、よい機会だと思う。ぜひ見てもらいたい。
余剰在庫は最重要課題
私が初めて経営コンサルタントの名刺を持ったとき、商社出身だった私の頭の中には「在庫=悪」の公式がガッチリとビルトインされていた。しかし、周りの私以外のコンサルタントたちは「在庫=売上」という常識が蔓延し、いつも私一人vs.その他全員で侃々諤々議論が始まっていた。
確かに、市場が伸びている時は「デマンド・プル(売れているから在庫が足りなくなる)」といって、在庫は怖くなかった。しかし、供給過多になり市場が縮小している時代にあっては、在庫は企業のクビをしめることになる。
1970年以降、激しく統廃合を繰り返してきた総合商社の業績悪化の主要因は、ほとんどがバランス在庫(売約定がついていない在庫)を増やしたからだ。なぜ、在庫を増やすのか。
在庫を持てば、「モノが欲しい」と言われた際に「はい、どうぞ」と、すぐに出荷できる。要は、スピードが速く、探さなくても商品をつくるための原料を確保できているから、付加価値が高いのである。特に、何がはやるかわからない状況、企業は商品生産のリードタイムをどんどん短くして、的中率を上げようと考える。だから、ベンダーが在庫を持っていると安心するわけだ。
しかし、どのようなものにも裏表がある。持っている在庫が売れ筋のものであれば、それは宝の山になるが、売れないものだったらどうなるか。結局、仕入れた分だけ償却して焼却する“ダブルショウキャク”で、企業に多大な損失を負わせることになる。ましてや、マーケティングが、広範囲のブロードキャスティングからナローキャスティング、そしてパーソナライズという具合に、どんどん狙いが狭くなっている潮流を考えれば、在庫がないことによる欠品以上に、売れ残った余剰在庫のダブルショウキャクによる損失のほうが大きくなってきて、今、日本ではなんと90%以上もの在庫が売られずに残っているのだ。
こうして、在庫は私がこの業界に入った20年前に予言したように、「宝の山」から「破裂したら即死する爆弾の山」へと変わってゆく。
売らない店…ショールーム化する店舗
円安の時代、あれだけ不調だといわれた百貨店が好調だという。聞けば、この円安によるインバウンド需要が爆速しているからだ。しかし、私はこの現象は一時的なものだと思う。為替だって、いつ円高に戻るかわからない。すべてが固定化されて動かなくなるなんてことはない。
そこで、企業は可能な限り、企業内部にある「無駄、無理、無茶」の撤廃をすすめ、在庫の極小化、最適化を図っている。それが在庫の一元化であり、店頭から陳列以外の在庫をなくす方向だ。確かに、個客にとって「その日のうちに持って帰る」ことは、さほど重要ではない。せいぜい、翌日か数日内に到着してくれれば十分ということもある。そうすれば、店舗はショールームと化し、着こなしやコーデをチェックすれば、ポケットに入っているスマホでポチるだけで翌日に新品が自宅に届く。こういう時代がやってくる。いわゆる「売らないお店」だ。
それでは、なぜ「在庫の一元化」は在庫の極小化に貢献するのだろうか。答えは簡単。店舗の評価を売上で見ているからだ。
店長やエリアマネージャと呼ばれる人たちは、売上をできるだけ多く上げれば出世もするしボーナスも出る。そうなると、何より最初にやるのは、「在庫の確保」なのである。思い切った言い方をすると(実際はそんなことはないが)、「売れ残っても大丈夫。アウトレットにまわせば、彼らがうまくやってくれるだろう。自分たちは売れる在庫をとにかくたくさん確保しなければならない」ということになる。
力のある店舗は実績が伴い、在庫の取り合いがあれば優良在庫は売れる店へと優先的に回され、ますます店舗の評価に明暗がつくのだ。このような力学が働く場で、それぞれのエリアなり店が独自に売る分だけの在庫を持ったらどうなるか。
例えば、日本で500店舗持つアパレル企業があるとしよう。その1店舗、1店舗が在庫を積み増して発注するわけだから、日本全土でみれば恐ろしいほどの余剰在庫が積み上がることになる。これを一元管理して、FIFO (先に売った店が優先的に引き当てできるルール)で、総在庫の管理がシンプルになり余剰在庫も最小化されるわけだ。
そうなると、次に心配なのは欠品による機会損失である。しかし、これは、LOUIS VUITTON(ルイ・ヴィトン)などのお店に行けばよくわかるが、店頭で接客用に見せる在庫(この在庫は売らない)はフルセット揃えておき、販売する在庫は倉庫に一元的に管理しておかれ、最初に販売した店から出荷されるルールにする。これが、「売らないお店」の基本コンセプトなのである。
“Tokyoショールーム戦略”
ここまで読んで、「なるほど、売れないお店によって、悪い在庫を極力最小化できるのか」と感心していないだろうか。それ以上に、そもそも、あれだけ売れて仕方なかった時代が過ぎ、日本のアパレルの超デフレ化がおき、韓国や中国から1000円、2000円という、私のように昭和の人間にとってはついて行けないほどの低価格で、特に“Z世代”と呼ばれるファッション購買セグメントのハートをがっちり掴んでいるのだ。
つまり、これからのファッション産業の大部分は、アジアのD2C(Direct to Consumer)企業(アジアは世界のアパレルの工場で、その工場が自分で商品を売り出した)にやられてしまうことになり、低価格化と外資企業の越境ECと呼ばれる国をまたいだEC販売で、市場は小さくなってゆく。加えて、人口減少、失業、所得の減少などファッションなどに使える金は若者には残されていない。そうなると、比較的安価で長く着られるユニクロのような服が一層強さを増し、日本市場はユニクロだらけになるというのが私の見立てである。
こうしたなか、「売れないお店」だけでいいのか、というのが、私が立てた第一命題である。一般的にリテール産業は、内需型産業といわれているが、今日本では、企業は必用な量の倍も服をつくり、それらの多くがダブルショウキャクによって企業の利益を悪化させているのだ。そして、こうした状況を避ける方法は、論理的に二つしかない。
それは、ファッション衣料製品からファッション雑貨などへ「売る商品」を替えるか、日本市場だけでなく海外市場に売るという「市場」を替えるかのいずれかである。
売る商品を替えるのは、たやすいことではない。なぜなら、アパレルの多くは製造業だからだ。やはり、ここは韓国や中国が日本市場に入ってきているように、我々のデザインした服を世界に売ってゆくことが残された道である。これが、私が提唱する「売らない店」ならぬ、「売らない国」なのだ。
そして、そのブランドの中核にいるのが「Tokyo」だ。アジアの人と話をすれば、「Tokyo」という言葉が持つブランド力を感じることが多い。あのユニクロも銀座店舗には「ユニクロTokyo」があり、Tokyo baseというアパレルは純国産の服をアジアで販売して成功している。立派な上場企業は、すべてのブランドに「Tokyo」という名前を冠にしている。
「Tokyo」が醸し出すイメージは、こんなものだろう。無駄がないミニマリズム。素材感、原材料が持つ色や風合いを大事にし、人が見ないところでも丁寧な仕事をしている。デザインでいえば、モダン・コンテンポラリーといって、近代的で近未来を映し出すスタイリッシュなラインなどだ。
私には、はっきりと「Tokyo」が持つイメージが見える。この「Tokyo」をファッション化し、「Tokyo」の青山、代官山、大手町などをファッションシティとしてイメージ想起させる。上記の「売らないお店」のショールーム化なら、「Tokyo」をショールームシティーとするわけだ。そして、成長著しいインドネシア、インドなど、爆発的に人口が増えている国に販路を拡大する。商社や政府などが共同で、そのルートをつくりアパレルが海外で成功できるような手助けをする。私にやれといわれればやってもよい。これが、“Tokyoショールーム戦略”の全体像である。
(文=河合拓/事業再生コンサルタント)