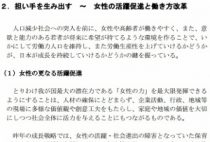安倍首相、姑息な温暖化ガス削減目標 だまし討ちで脱原発論封じ、対応が大幅遅れ
米国も似たようなものだ。国内で進むシェールガス革命によって、温暖化ガスの排出削減で石炭より圧倒的に有利なシェールガスの本格利用にメドがついたことを生かそうとした。40%削減するというEUと比べれば削減幅は決して大きくないが、40年かけて目標を達成するというEUに対して、基準年を05年、達成年を25年とわずか20年の間に26~28%の削減を行う短期決戦型の目標を打ち出したのである。対日戦略に限れば、EUと足並みを揃えて圧力をかけてきたのが明らかだった。
このように国際的な駆け引きが早くから本格化していたのに、日本の対応は遅れていた。首相官邸筋が、この春の統一地方選挙の前に原発の存続議論が社会的な注目を集める事態を嫌い、本格的な議論のスタートをぎりぎりまで遅らせたからである。水面下の議論でさえ、本格化したのは4月に入ってからだ。低い目標では国際的に孤立すると恐れた環境省や外務省の動きを逆手にとって、経済産業省が原発依存度の引き上げと再生可能エネルギーの普及拡大を軸に、温暖化ガスの排出が多い石炭火力発電の比率を下げることによって、ある程度削減幅を積み増す努力を開始した。
そんな状況下の4月下旬、安倍首相が6月にドイツで開かれる主要7カ国(G7)首脳会議(サミット)への参加を意識し始めた。経産省幹部に対し、諸外国から批判を招かないよう欧米に遜色ない目標をつくれと指示したという。
ナンセンスな議論
浮上してきたのは、安倍政権らしいレトリックに頼るという手法だ。それまでの方針通り05年を基準年にしたのでは、日本は欧米と比べて見劣りする。しかし、13年を基準年に計算すれば、温暖化ガスの削減幅は、日本の26%に対し、米国が18~21%、EUが24%になる。欧米を上回る削減努力の演出にうってつけというわけだ。こうして安倍政権は、13年と05年の両方を基準にした2つの削減目標を国連に登録する戦略にたどり着いたとされる。
関係者が検討に費やした物理的なエネルギーは多としたいが、こうした政治的、官僚的な目標づくりが良策だったとは思えない。必要だったのは、世界全体の温暖化ガスの排出削減に効果的な目標づくりを促す戦略だったはずだ。そこを出発点と考えれば、基準年を設けて削減幅を競う駆け引きに参加するのはナンセンスとしか思えない。
経産省と環境省の合同会合の資料によると、日本の温暖化ガスの排出割合は2.8%(10年実績)であり、世界で8位にすぎない。1位の中国(22.2%)、2位の米国(13.8%)、3位のEU(10.2%)、4位のインド(5.8%)、5位のロシア(5.1%)、6位のインドネシア(3.9%)、7位のブラジル(3.3%)がそれぞれ見せかけの削減を競うようでは、地球温暖化は予防できないと断じてよいだろう。これからの削減幅を比率で競うよりも、排出の絶対水準を抑える目標を掲げるほうが重要であり、日本の国益にも適うのは明らかだ。