不動産、来月にも大暴落の可能性…中国人が一斉売却の懸念、すでに局地的バブル終了
 「Thinkstock」より
「Thinkstock」より
今年の6月に拙著『2025年東京不動産大暴落』(イースト新書)を上梓したせいで、いろいろなメディアから不動産価格の「暴落」について取材を受けたり、コメントを出したりしている。
しかし、実際のところ大暴落はいつ始まるのか? 答えを言ってしまえば、それは来月かもしれないし3年後かもしれない。しかし、必ずやいつかやってくる。ここでは簡単に説明してみたい。
 『2025年東京不動産大暴落』(榊淳司/イースト新書)
『2025年東京不動産大暴落』(榊淳司/イースト新書)まず、大暴落が起こるエリアは2013年以来の異次元金融緩和で局地バブルが発生したエリアである。マネタリーベースにして約4倍に膨らんだお金が、限られたエリアの不動産に注ぎ込まれたことによって生じた不動産価格の高騰を、私は局地バブルと呼んでいる。それが発生したのは、首都圏では山手線の内側とその周縁、城南、武蔵小杉、みなとみらいエリアが中心だ。地方では京都市の御所周辺と下鴨エリアで顕著にバブル現象が見られたが、すでに終息の気配を見せている。
私が考えているバブルの定義も示しておく。まず、不動産というものはただ存在するだけでは意味がない。利用されてこそ価値がある。日本の多くの山林が無価値化したのは、それを利用する用途がなくなったからだ。住宅なら自分が住むか、誰かに貸すことで価値が生まれる。
「元が取れる」価格水準
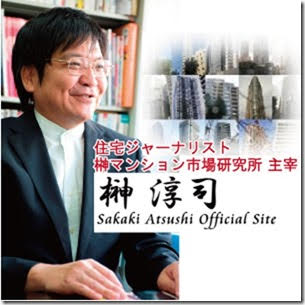
誰かに不動産を貸すと想定した場合、健全な利回りは5から8%だと私は考えている。たとえば1億円のマンションを購入して賃貸に回した場合、13年から20年で元が取れる、というレベルだ。
なぜ5から8%かというと、リスクとリターンのバランスだ。1億円でマンションを購入し、それを保有するということはそれなりのリスクを背負うことでもある。考えられるリスクを挙げてみよう。
(1)値下がりリスク
(2)災害リスク
(3)事件リスク
(4)欠陥リスク
(5)管理リスク
まず、1億円で購入しても5年後には資産価値が7000万円に下がっているかもしれない。地震や洪水、津波に遭うかもしれない。その部屋で誰かが殺されたり、自殺や孤独死もあり得る。そのマンションの杭が基礎となる地盤に刺さっていないこともあり得る。管理組合が困った人物に支配されて、修繕積立金を横領される可能性もゼロではない。そうでなくても、建物は日々老朽化していく。
そういう諸々のリスクを背負っているのだから短くて13年、長くても20年で「元が取れる」価格水準が健全である、と私は考える。だから利回りが5から8%。ただし、この水準が適用できるのは入居率が90%以上を望める都心エリアのみ。郊外や地方に行くと10%から20%の利回りでないとリスクに見合わない不動産も多い。
ところが、現在の市場はその水準を逸脱している。たとえば、東京都港区かつ山手線の内側で新築マンションを購入すると、利回りは3%そこそこ。物件によっては2%程度のケースも散見される。つまり、健全な利回りである5から8%と、現状の3%の差がバブル分なのだ。
仮に価格が1億円で年間の実収が300万円(利回り3%)のマンションが、年間5%の利回りの物件になるには6000万円に値下がりしなければならない。その差の4000万円分がバブルということ。したがって、現在の局地バブルエリアは4割程度の値下がりリスクを背負っていることになる。この4割の値下がりが短期間に発生すると「大暴落」ということになる。
需要と供給の法則、金融情勢
では、いよいよ本題に入る。その値下がり局面(あるいは暴落)はいつ起こるのか?
冒頭に申し上げたように、それは来月始まっても不思議はない。その理由を順番に説明しよう。
まず、モノの価格を市場が決める「需要と供給の法則」は不動産にもあてはまる。現状、たとえば都心エリアでは中古マンションの売り出し物件が大量に発生している。しかし、売買が成立する成約数はさほどでもない。この側面だけ見れば、供給過剰である。特に江東区の湾岸エリアではこの傾向が強い。しかし、成約金額の顕著な下落は起こっていない。
なぜか?
ひとつには、売り手側がまだ焦っていないことだと推測する。今の市場の妙な均衡は当面続くと考えている人が多いからだ。あるいは「2020年の東京オリンピックまで不動産価格は上がり続ける」という、何の根拠もない都市伝説を信じている人も多い。だから、いまだに下落局面がやってきていない。
しかし、供給過剰の現状は下落、あるいは暴落への下準備をしっかりと整えているという現実を見逃してはいけない。あとは売り手が焦りだせば一気に動き出す可能性がある。
次に、金融情勢。これも暴落へのカギを握っている。
まず、現状ではマネーと不動産のバランスが不自然に崩れている。異次元金融緩和によってこの国にはマネーが大量に供給されたが、みんなが欲しがる不動産は限られていた。だからこの局地バブルが発生したと推測する。
16年の夏頃に金融庁が目立たないように規制を始め、今は不動産融資がやや引き締め気味と観測されている。しかし、銀行も日銀から突き返された資金の運用先に困っている。不動産担保融資の残高は依然として高水準。銀行が低利でお金を貸している限り、一定の買い手は存在し続けている。だから、いまだにバブルが崩れていないとも理解できる。しかし、世界的に見ても金融引締めの潮流ができつつある。日本の異次元金融緩和もいずれ終わらざるを得ない。黒田日銀総裁の任期は18年4月に迫っている。
いったん金融引締めが始まり、金利が上昇しだすと都心の不動産市場を直撃する。今までは低利の融資が引っ張れたからこそ3%や4%などという低利回り(高額)な物件でも取引が成立したが、融資金利が上昇すればそういう価格では買い手が現れなくなる。つまり、金利の上昇は不動産価格への強烈な下落圧力になる。
18年4月以降、日銀の新総裁がどのような金融政策を打ち出すのかが不動産市場にとってはかなり重要だ。金融引締め(金利上昇)なら、一気に先安観が広がる。あるいは暴落的な下落が始まるかもしれない。
外国人の動向
外国人の動向も気がかりだ。15年、都心や湾岸エリアではタワーマンションが飛ぶように売れた。特に湾岸エリアでは中国人を中心とした外国人のプレゼンスが目立った。なかには外国人比率が2割を大幅に超えたマンションもあったと推定される。そういったマンションが16年から続々と竣工してきた。いろいろな事件が起こっている。
ある大手財閥系のデベロッパーでは、新築販売時に中国人に売ったマンションを積極的に買い戻しているという。管理費を払わないなどのトラブルが多いのが原因だ。
一方、購入した中国人側からしても、「こんなはずではなかった」と落胆していることが容易に想像できる。まず、思ったほど値上がりしていない。中国や香港などでは、マンションが短期間で5~10割値上りする物件も珍しくない。それが東京の湾岸エリアではせいぜい2割程度。手数料を差し引けば1割の値上がり益を手にできるかどうかという水準だ。しかも、管理費や固定資産税などの維持費が年間に購入価格の1%程度は発生している。民泊で運用しようにも、管理規約で禁止されれば完全に違法だ。「だったら今のうちに売ってしまえ」という動きも一部では見られる。
彼らは時に一斉に動く習性がある。東日本大震災の直後、「東京に放射能が降りかかる」という噂を信じた中国人たちが東京から一斉にいなくなった。あのとき、上海までの片道航空券は30万円だったとか。しかし、彼らはそれを買ってまでも帰国を急いだ。中国人は日本人に比べてかなり「損切り」については思い切りがよさそうだ。
3つの下落タイミング
まとめよう。不動産市場の下落には3つのタイミングが考えられる。
(1)売り手が何かで焦りだした時
(2)金利の上昇側面
(3)中国人たちの一斉売却
このうち(1)の「焦り」は、ちょっとしたきっかけで起こる。たとえば株式市場で下落が続いた場合。あるいは北朝鮮との地政学リスクがなんらかのかたちで発火した時。中国経済のクラッシュが再燃した時などである。
政治の不安定化も当然、ここに入ってくる。安倍政権の基盤が崩れたりすると、売り手に焦りを生む原因になる。同様に、米国のトランプ政権の弱体化もいいことではない。世界のどこかで、リーマン・ブラザーズのような大企業が倒産しても、それは売り手の焦りにつながる。
ひとつ言えるのは、局地バブルエリアでの不動産価格高騰はすでに終わっているということだ。あとは、いつ下落に転じるのかというのが最大の関心事。そのときは刻々と迫っている。
(文=榊淳司/榊マンション市場研究所主宰、住宅ジャーナリスト)











