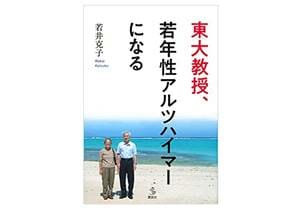
人の死にざまは「ピンピンコロリが理想」とは言うが、実際には年を重ねる過程でさまざまな病気に悩まされ、それは本人だけでなく家族にも重くのしかかることがある。
どんな病気も嫌なものだが、かかりたくない病気の最たるものの一つが「認知症」だ。実際、日本認知症予防学会と食から認知機能について考える会が2020年に行った「食と認知機能」に関する意識調査(※)によると「かかりたくない病気」として全回答者の約48%が「認知症」と答え、最も多かったという。
「運転、どうするんだっけ?」
これまでできたことができなくなっている、大事なことが思い出せない、簡単な作業をこなすことができない。自分が自分でなくなっていくかのような恐怖のなかで、自分は認知症なのかと自問し、そんなはずがないと打ち消しても疑念は消えない。当事者の苦しみは想像を絶するが、そんな時家族はどのように寄り添えばいいのだろうか。
『東大教授、若年性アルツハイマーになる』(若井克子著、講談社刊)は、50代で若年性アルツハイマーを発症した夫と、彼と共に歩み続けた妻の記録だ。
東京大学教授として国内外を飛び回る忙しい日々を過ごしていた若井晋さんの異変は、ちょっとした物忘れからはじまった。これまでなら問題なく書けていた漢字が思い出せなくなった。
「近ごろはみんな、パソコンを使って文章を書くから、漢字が書けない人間はごまんといる」
自分に言い聞かせるようにそう言ってはいたが、かつては脳外科を専門とする医師だった晋さんには何らかの心当たりがあったのだろう。晋さんのノートには人知れず漢字の練習をした痕跡があったという。妻の克子さんは、書斎にこもった晋さんが自分の脳のMRI画像を熱心にながめている姿も目撃している。
妻・克子さんからみても、晋さんの行動に違和感を持つことが増えていった。暗証番号を忘れたのかATMでお金をおろすことができなくなり、ネクタイを結べなくなった。職場である大学でも、構内で迷ってしまう、まとまった文章が書けなくなるなど、仕事に支障をきたすようになっていたという。
特に克子さんの印象に残っているのは、晋さんのお母さんの引っ越しで車を出す時のこと。もともと運転は得意だった晋さんだったが、その日はハンドルを握ったまま「運転、どうするんだっけ?」と言ったまま発車させることができなかった。アルツハイマーというワードがちらつくなか、克子さんは病院で検査を受けるべきだということをいかに晋さんに伝えるか、思い悩むようになる。
認知症関係で受診を勧める家族の声に素直に耳を傾ける人は少ないという。自分が認知症などとは誰だって認めたくないし、まして晋さんは脳の専門家である。いかに傷つけずに病院の受診を勧めるかを考えた末、克子さんは「晋さんが克子さんの前でとった行動」をリスト化したメモを手渡すことにしたという。
◇
検査を受けることにした晋さんだったが、克子さんが医師に告げられたのは、晋さんの脳の言語の分野が委縮しているという事実。その後、晋さんは若年性アルツハイマー病と診断された。ここから、晋さん克子さん夫婦の、認知症との日々が始まる。その毎日は病気との「闘い」という色合いは薄く、どちらかというと「共生」という方が近い。
抗わず、無理せず、隠さず、二人は認知症と向き合いながら豊かな人生を模索していく。晋さんは病気を公表し、病気についての講演を行うなど、社会とのかかわりを持ち続けた。そして、その傍らにはいつも克子さんの姿があった。
私がアルツハイマーになったということが、自分にとって最初は「なんでだ」と思っていました。けれども私は私であることがやっとわかった。そこまでに至るまでに相当格闘したわけですけど。(中略)「こういう病気はどうしようもない、何もできない」、多くの人がそういうことでこの病気を考えていると思います。私がそのことに対して皆さんに「そうではないんだよ」と言えることができれば一番いいのではないかと思います。(p.129より)
晋さんはこんな言葉で、同じ病気にかかった人にメッセージを送っている。誰もがかかりうる一方で、症状や周囲の人間としての関わり方などがあまり知られていない認知症。本書でつづられているこの病気を抱える人と、それを支える人の日常は、いつか読んだ人の人生を助けてくれるかもしれない。(新刊JP編集部)
※「食と認知機能」についての意識調査(https://dm-net.co.jp/calendar/2021/030833.php)
※本記事は、「新刊JP」より提供されたものです。





















