がん検診が死亡率高める?過剰な診断・医療が、無駄に犠牲者を増やす危険な現実
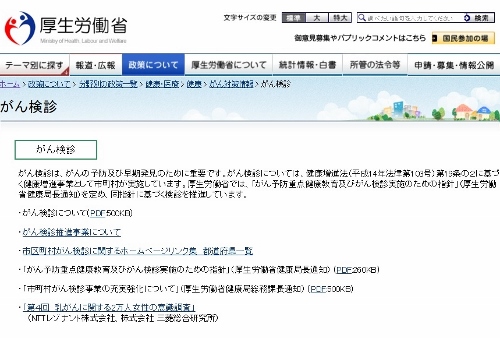 「厚生労働省 HP」より
「厚生労働省 HP」より現在、5つのがんに対する集団検診が国によって推進されています。胃、大腸、肺、乳房、それに子宮の各がんです。しかし、どのがん検診も死亡率を下げる効果がないか、むしろ死亡率を高めてしまうものであることは、本連載で述べてきたとおりです。
検診でがんが見つかれば必ず治療が行われていますから、これは検査だけの問題でなく、治療の方法にも疑義があることを意味します。
では早期発見・早期治療ができるはずのがん検診で、なぜ死亡率が下がらないのでしょうか。
「がん=死」というイメージが人々の脳裏に焼きついています。日本では、昭和27年に公開された黒澤明監督作品『生きる』がひとつのきっかけだったように思います。映画の中で、がんを患った主人公を名優・志村喬が演じていましたが、「がんは必ず死ぬ病気」であることが強調されていました。しかし、本当にそうなのでしょうか。
その昔、がん細胞のかたまりを動物に移植すると、たちまち大きな腫瘍に成長して動物が死んでしまうという研究報告が世界中でなされました。がん=死であることが専門家の共通認識となり、やがて世界中の人々の知るところとなったのです。
しかし動物にがんを移植しようとしても、普通は拒否反応が起きるため、うまくいきません。もし移植したがんが動物の体内でどんどん大きくなったとすれば、よほどたちの悪いものを選んで実験を行ったと考えられます。動物実験の結果だけから、がんの性質を論ずることはできないのです。
何も治療せずに、病気を放置した場合にたどる経過を「自然史」といいます。『現代病理学体系-癌の自然史(藤田哲也著)』によれば、ヒトの胃がんや大腸がんは、1個のがん細胞がレントゲン検査や内視鏡検査で発見できるほどの大きさ(直径1センチメートル以上)に成長するまでに、理論上25年くらいかかるのだそうです。しかし現実には個人差も大きく、また、がんが発見されるとほぼ例外なく手術などの治療が行われるため、本当の自然史は誰にもわかっていませんでした。
放置と最新治療、5年生存率は同じ?
ところが最近、意外な事実が次々と明るみに出されるようになりました。
たとえば、CTによる肺がん検診が行われ、小さな変化まで見つかるようになりましたが、ある研究によれば、直径が3センチメートル以下の腫瘍では、サイズとその後の運命、つまり死に至るかどうかとは無関係であることがわかりました。
乳がんと診断される人の22%くらいは、放置しても自然に消滅してしまう可能性が高いことは、本連載ですでに紹介したとおりです。
また、海外で行われた調査によると、死亡した人の解剖を行ったところ、たまたま肺がんが見つかった153人のうち、43人は生前に肺がんの診断は受けておらず、症状もいっさいなかったそうです。
さらに国内で行われた調査によれば、精密検査で胃がんと診断されながら、なんらかの理由で治療をいっさい受けなかった38人の日本人を追跡したところ、5年後に生存していた人が63~68%もいたというのです。胃がんと診断された時点での「進行度」は不明ですが、平均して2期(正式表記はローマ数字/がんが胃壁に留まる)くらいだったとすれば、最新治療を受けた場合の5年生存率とほぼ同じだったことになります。
がんは放置すると必ず大きくなり、たちまち死に至るとの神話は、すでに崩れ去っています。がんの悪性度には大きな個体差があり、人畜無害なものから極悪なものまでさまざまなのです。無害ながんを検診でたくさん見つけて治療すれば、5年生存率は高く見えるに決まっています。
がん検診の専門家は、レントゲン検査をCTや内視鏡に替えて「検診の精度が高まった」と自慢しています。しかし、その努力は過剰な診断(over-diagnosis)を助長し、過剰医療の犠牲者を増やしているだけです。
がん検診の旗振り役が「日本対がん協会」のようですが、いったい誰が、何を根拠に、どんなことをしているのか、国民にわかる言葉で説明してほしいものです。「ピンクリボン」という名の運動を支援している厚生労働省、東京都、日本医師会、朝日新聞社などは、利益相反の有無も含めて自らの責任を明確にする必要があるでしょう。
がん検診を推進する組織のホームページは、どれも「受けるのが当然」との前提でつくられていて、筆者には誇大広告か詐欺商法にしか見えません。
(文=岡田正彦/新潟大学名誉教授)
参考文献:Gut 2000;47:618-21.





















