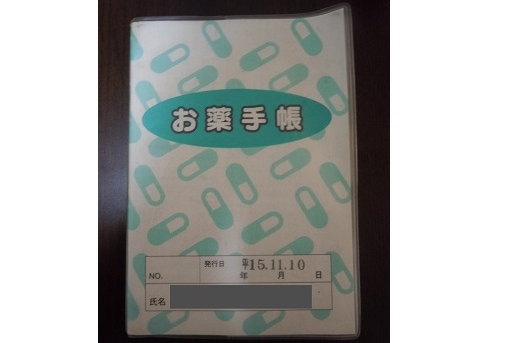 おくすり手帳(「Wikipedia」より/Shigeru-a24)
おくすり手帳(「Wikipedia」より/Shigeru-a24)つい最近までは、調剤薬局に行く際に「おくすり手帳」を持参しない患者さんが多かった。しかし、この4月からはほとんどの患者さんが持参するようになった。
いったい何が起こったのか。そもそもおくすり手帳とは何か。 そして、その代金はどうやって決められているのか。今回はこうした疑問について解説してみたい。
そもそも、おくすり手帳というのは、病院などで処方された薬の情報を記録し、その服用履歴を管理するためにつくられた。こうすることで、薬の飲み合わせのチェックなどができ、投薬がスムーズに行われるというメリットがあった。そのため、国はこれを診療報酬制度に組み入れて実施してきたのだが、その制度自体は2年に1度の診療報酬の改定ごとに目まぐるしく変わってきた。
直近3回の改定を振り返ると、2012年の改定がもっとも大きかった。これは、11年の東日本大震災が影響したからである。震災では、地震と津波の被害でカルテや調剤履歴を喪失した病院や薬局が続出したが、おくすり手帳を持っていた患者さんは、避難先でもスムーズに診療や投薬ができた。
そこで厚労省はこの教訓から、それまで希望者だけだったおくすり手帳をすべての患者に適用することに変更し、その診療報酬を「薬剤服用歴管理指導料」に一本化したのである。その点数は41点、すなわち410円(1点=10円)である。ただし、これを得るには薬局は次の5項目をすべて行うこととされた。
1.薬剤情報提供文書による薬の説明
2.薬剤服用歴の記録と指導
3.残薬の確認
4.後発医薬品(ジェネリック)に関する情報提供
5.おくすり手帳への薬剤情報の記載
おくすり手帳を渡す際に、これらを行えば410円になる。1日に患者さんが100人なら4万1000円、1000人なら41万円である。もちろん、患者が支払うのは410円ではなく、保険適応の3割負担(70歳未満)なら130円である。ただし、おくすり手帳がない場合(上記5項目を満たさない場合)は、34点=340円とされた。3割負担なら110円である。
410円-340円=70円。この差額の70円が実質的なおくすり手帳の値段というわけだ。3割負担の患者さん側から見ると差額は20円(130円-110円=20円)となる。
つまり、このときからおくすり手帳を持参しないほうが、患者さんは医療費を20円節約できることになった。そのため、テレビや雑誌では「おくすり手帳を利用せず、窓口での負担金を節約しよう」という特集が多く組まれた。
点数稼ぎする薬局も
しかし、こうなると薬局の収入は減る。そこで厚労省は次の14年の改定では、おくすり手帳を必ずしも必要としない患者に対する薬剤服用歴管理指導料の評価を見直すとした。つまり、手帳を持参しなかった患者については41点を算定できず、34点しか取れない。
その結果、何が起こったか。とりあえずシールだけを渡して、管理指導料を取ってしまうという薬局が現れた。また、薬局によってはぺらぺらの「超薄型おくすり手帳」をつくり、これを乱発することで点数稼ぎするところも現れた。
当然だが、これには患者さんから不満が続出した。「薬の説明もないまま、知らないうちに薬袋にシールだけ入っていた」「ジェネリック医薬品についての説明がなかった」などだ。
こうして今年の4月の改定では、管理指導料をおくすり手帳を持参した場合は38点=380円に引き下げ、おくすり手帳がない場合は50点=500円に引き上げたのである。
この差額は120円。おくすり手帳の有無によって、3割負担であれば40円の差が生じることになった。つまり、今度はおくすり手帳を持っていったほうが、40円トクできることになってしまったのである。
手帳を持参しないデメリット大
ただし、手帳を持っていっても安くならない場合もある。たとえば、かかりつけの病院に通い、薬局もいつも決まった薬局を使っているとしても、たまになにかの都合で別の薬局に行くケースがある。こうすると値段は高くなる。
管理指導料は、初めての薬局と、一度調剤をしてもらって半年以内に再度利用した場合とでは、点数が異なる。初めての薬局は50点=500円(3割負担で150円)だが、半年以内に再度利用したときは38点=380円(3割負担で110円)になる。つまり、度薬局を決めたら、そこに通うほうがトクなのである。
また、利用する薬局が「大型門前薬局」であれば、歴管理指導料は50点=500円という規定もある。大型門前薬局に該当するかどうかは、薬局に確認したほうがいい。
現在、おくすり手帳は電子化が進んでいる。調剤薬局チェーンのなかには、独自で専用アプリを開発し、スマホで管理できるサービスを展開しているとこともある。これまでは、電子版おくすり手帳に記録した場合は診療報酬には加算されなかった。しかし、この4月からは、電子版も条件を満たせば紙と同じに扱われることになった。
以上、非常にややこしい話だが、手帳を持参しないために、他の薬局でもらっている薬や合わなかった薬の名前がわからないとどうなるか。手帳代というわずかな金額を節約して、複数の病院から飲み合わせの悪い薬が処方されたり、副作用が出た薬を再度飲むことになり、かえって莫大な医療費がかかると共に、健康を損なう苦痛を味わうのはいかがなものだろうか。
それだけに、今後はぜひ活用してほしい。
(文=富家孝/医師、ラ・クイリマ代表取締役)





















