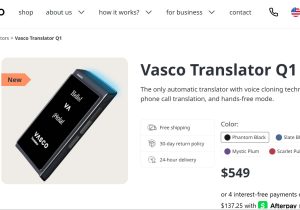精神科医が語る大正天皇の“ご病状”…生誕直後に髄膜炎、そして発話障害、認知機能障害

現在に続く都市文化の幕が開いた「大正という時代」
明治と昭和という、ふたつの巨大な時代のはざまに位置している「大正時代」(1912~1926年)。15年間という短い時代であったこともあってか、一般にはそれほど注目されていないようにも思われる。もしかすると、この時代の君主である大正天皇が生来病弱で、明治天皇や昭和天皇と比べるとインパクトの少ない存在であったことも関係しているのかもしれない。
振り返ってみると、「明治」は武家社会から近代国家創設への変革期であり、一方で「昭和」は戦争の惨禍と奇跡的な経済復興の時代であった。それでは、大正とはどういう時代であったのだろうか。実は大正という時代は、今日にも通じるさまざまな社会的・文化的なテーマがはっきりと呈示された時期であったし、そうしたテーマが現れるべくして現れた、光と闇が交錯した時代であった。
この時期は、明治以来続いていた、維新の実力者による藩閥政治体制が揺らいでおり、代わって政党勢力が進出してきており、いわゆる大正デモクラシーの機運が高まっていた。「平民宰相」と呼ばれた原敬が政党内閣を組織したのは、1918(大正7)年であったが、原は1921(大正10)年に暗殺されてしまい、時代に暗い影を投げかけた。一方でこの時期、普通選挙運動が活発となり、平塚らいてうや市川房枝ら「新しい女性」による婦人参政権運動も目立つようになった。
1921(大正10)年11月25日には、皇太子裕仁親王が、大正天皇の病状悪化によって摂政宮となった。1923(大正12)年には関東大震災が起こり、東京に甚大な被害がもたらされた。この震災直後の混乱期に、アナーキストの活動家であった大杉栄と伊藤野枝の夫婦が憲兵隊に拘束され、殺害されるという事件が起きている。1925(大正14)年には加藤高明内閣下で普通選挙法が成立したが、一方で社会主義者・共産主義者の弾圧のために治安維持法が制定された。
日本が第一次世界大戦に参戦したのも、大正時代のことである。日本は連合国の一員として連合国の側につき、中国にあったドイツの拠点を襲撃し、革命が起こったロシアに対してシベリア出兵を行った。第一次世界大戦の結果、敗戦国のドイツやオーストリアでは君主制が廃止され、ロシアなきあと、世界初の社会主義国となるソビエト連邦が成立した。
こうした大正時代をもっとも大きく特徴づけるのは、その文化的な側面ではなかろうか。
近代都市の発達や経済の拡大にともない、現在にも通じる大衆文化が開花し、「大正モダニズム」と呼ばれる華やかな時代が到来した。女性の就労も増えて、大都市部に「モガ」(モダンガール)と呼ばれる女性たちが登場したのもこの時代である。電灯や電車が一般的となり、洋食屋やカフェ、さらには扇風機や蓄音機も登場し、今日の都市文化の幕が開かれた。無声映画の隆盛もこの時代である。
この時期は文学分野でも多くの作家が活躍し、芥川龍之介、有島武郎、志賀直哉らの文学者が多くの作品を発表した。芥川と有島は人気作家であったが、自ら命を絶っている。1920(大正9)年に創刊された雑誌「新青年」は今日の目でみれば大衆文芸雑誌であるが、江戸川乱歩らが活躍し、現在の「サブカルチャー」の原点ともいえる内容を含むものであった。
こうした時代の君主、大正天皇はどのような人物であったのか。以下に、医学的な見地から解き明かしてみたい。
本書の記載においては、古川隆之『大正天皇』(吉川弘文館、2007年)、原武史『大正天皇』(2015年、朝日文庫)、『大正天皇実録 補訂版』全6巻(ゆまに書房)などの資料を参考にした。

生母は歌人・柳原白蓮のおば、柳原愛子…生誕直後に髄膜炎をわずらい、後遺症に苦しむ
大正天皇は1879年(明治12年)に生誕したが、明治天皇の子のうち、唯一成人した男子(三男)であった。生母は権典侍、柳原愛子(やなぎわら・なるこ)で、諱は嘉仁(よしひと)。愛子は公卿であった柳原光愛の次女で、歌人として活躍した柳原白蓮は姪にあたる。
大正天皇は生来病弱で、何度か大病に罹患している。生誕した直後には髄膜炎を患い、嘔吐や痙攣を繰り返すなど一時は危険な状態に陥った。幼児期は中山忠能邸で暮らし、明治天皇の生母である中山慶子を中心に養育が行われた。親王の健康状態はなかなか安定しなかったが、3歳になりようやく歩けるようになったと伝えられている。
このように大正天皇には発育の遅れがみられたが、これは乳児期に罹患した髄膜炎の後遺症と考えられる。1885(明治18)年、嘉仁親王は中山邸から青山御所内の新御殿に移った。小学校入学の年齢になっても病気がちであったため、青山御所内に御学問所を作り、個人授業を受けることとなったのだ。しかし規則に縛られることを嫌う性格から、授業そのものを投げ出してしまうこともあったという。
その後、1887(明治20)年に学習院初等科に入学したが、やはり病気がちで学校を休むことが多かった。1889(明治22)年2月、青山御所から赤坂離宮内の東宮御所に移り、同年11月3日に皇太子となった。これ以後、軍事教育の比率が増したが、これを好まなかったという。
1893(明治26)年、学習院初等科を卒業し中等科へ進学した。しかし病弱で学習面での遅れが目立つため、中等科1年修了時に学習院を退学している。その後も体調は安定せず、腸チフス、結核などに罹患している。勉強については、国学、漢学、フランス語などが個人教授されたが、なかなか身につかなかった。その後、伊藤博文の提案により、明治天皇の信任が厚かった有栖川宮威仁親王が皇太子養育の全権を与えられ、勉強よりも健康第一の養育が行われるようになった。
32歳で即位、47歳で崩御…即位直後からちぐはぐな動きや不用意な発言
1912年7月29日、明治天皇が崩御し、皇太子嘉仁は7月30日に即位し、大正と改元した。8月1日に朝見式が行われたが、大正天皇は勅語朗読中に言葉に詰まり、スムーズに話すことが困難であったという。
大正天皇の統治能力には不安がもたれていたが、実際、即位後も重臣との間でちぐはぐな動きや不用意な発言がしばしばみられた。体調も安定せず、1913(大正2)年には肺炎となったため、葉山や日光で静養している。
1918(大正7)年末には風邪を引いたがこれをこじらせ、翌1919(大正8)年1月末から3月まで葉山で静養した。そして、同年11月に兵庫県・大阪府で行われた陸軍特別大演習への参加が、最後の地方の公式行幸となった。この時には、左足の不全麻痺、歩行障害が確認されている。1919(大正8)年には、山県有朋の依頼により、東京帝国大学教授三浦謹之助が天皇の診察を行ったが、診断はついていない。この頃、原敬も日記のなかで、天皇の病状への憂慮を表明している。
1920(大正9)年3月、大正天皇の「体調悪化」が宮内省から公表された。その後は必要最低限の面会以外は静養に専念し、行事への参加は皇太子などが代行した。1921(大正10)年7月に塩原へ静養に行った際には、侍従に抱えられてやっと歩き、風呂や階段を怖がったり前年の出来事や身近な人物を忘れるなど記憶喪失に陥ることもみられた。この時期には言語障害が次第に進行し、面会した者には、「ご趣旨不明の点あれとも」「御言葉の明瞭を欠くことある」などの発言がみられている。大正天皇の侍医であった西川義方は、天皇の疾患をアルツハイマー病と考えていたようである。
天皇は山県有朋が気付いた1918(大正7)年冬、天皇39歳の頃に発症し、病状がはっきりしてきたのは、原が気付いた1919(大正8)年後半、40歳の頃と思われる。しかし、本稿末に示す神経心理学者・杉下守弘の論文では、実際はもっと早期から病気は始まったという記述も指摘されている。大正天皇実録によれば、1914(大正3)年に軽い発語障害がみられ、その後、姿勢の前屈が出現した。そして、大正1915(大正4)年11月より階段昇降の障害がみられている。
1921(大正10)年9月に皇太子が欧州から帰国すると、同年10月4日には大正天皇の病状が深刻で公務を行うことができなくなっている旨発表がなされ、11月25日に皇室会議と枢密院で摂政設置が決議され、正式に皇太子が摂政に就任した。ただし大正天皇本人はこれに抵抗し、自らの病状の悪化を正確に認識していなかったという。同年11月の侍医頭池辺棟三郎らによる御容態書には、「御発語の御障碍あらせらるる為、御意志の御表現甚だ困難に拝し奉るは洵に恐懼に堪えざる所なり」と記載されている。
その後の大正天皇は、夏は主に日光、他の季節は沼津や葉山に長期滞在し療養に専念した。日課として散歩を行ったり、具合のいい日は侍従や女官たちとビリヤードや雑談をして過ごしたが、病状の悪化は続いた。
1926(大正15)年の年初からひいた風邪が長引き、5月ごろからは歩行が不可能になった。10月末から38度を超える高熱が続いた。12月8日に呼吸困難に陥り、12月14日には食事が流動食に切り替えられた。病状は一時小康状態となったが、12月24日から肺炎が悪化し、翌日12月25日午前1時に崩御した。47歳という短い生涯であった。

梨本伊都子曰く「明治天皇と違って大正天皇は大変親しみやすいお気軽なお方」
皇太子時代に富士山麓で狩猟中にひとりはぐれた際、通りかかった青年に道を尋ね立ち寄った家でお茶漬けを勧められたり、陸軍の演習に参加した際に突然旧友宅を訪問したりと、大正天皇は気さくな人柄であったという。梨本伊都子は『三代の天皇と私』(1985年、講談社)で、「明治天皇と違って大正天皇は大変親しみやすいお気軽なお方でした」と評している。一方で側で仕えていた侍従長などからは、軽率で社会性がないという批判もあがっていた。各地を行幸した際には、急な予定の変更がひんぱんで、随行した職員たちは警備などに関してたいへん難儀したという。
趣味は洋風で、洋服、ワインを好んだ。娯楽はビリヤードや将棋を楽しんだほか、ヨット「初加勢」によるクルージングや乗馬も楽しんだ。初加勢が、ヨーロッパの王族が使用するような豪華な大型ヨットであったという。また、自転車もよく利用した。当時の自転車は高級品で、庶民には手の出ないものだった。
1920(大正9)年3月に三浦謹之助・東京大学教授、池辺棟三郎侍医頭は、「大正天皇は即位後の多忙により神経過敏となったうえ、2年前から内分泌臓器のいくつかが不調となり、幼児期の髄膜炎の影響から心身の緊張を要する儀式の際に体が傾くなど平衡を失うようになったため、政務を見る以外には儀式に出ず静養することが必要である」との診断書を提出した。しかし診断は確定していなかった。
近年、杉下守弘は、大正天皇の罹患した疾患は、脳の変性疾患である「原発性進行性失語症」、あるいは「大脳皮質基底核症候群」であった可能性を指摘している。いずれの疾患も原因不明の脳委縮により、失語症、認知機能の障害、歩行障害などの身体症状を伴う稀な進行性の疾患である。
杉下の具体的な指摘は以下の通りである。
大正三年(1914)、発話障害(恐らく、失語症、しかし構音障害の可能性もある。)で始まり、その後、前屈姿勢が生じた。大正四年(1915)、階段の昇降に脇からの手助けが必要となった。四年後(大正七年、1918)の11月には発話障害は増悪し、軽度の記憶障害が認められた。五年後(大正八年、1919)には歩行障害が生じた。その後、これらの症状の増悪とともに、大正十年(1921)末には御判断及び御思考なども障害され認知症となられた。大正天皇の御病気は、初発症状が「失語症」なら「原発性進行性失語症」と推定される。「原発性進行性失語症」は言語優位半球(通常は左大脳半球)の前頭葉、側頭葉および頭頂葉のうちの少なくとも1つに脳萎縮がおこり、はじめに顕著な失語症を生ずる。その後、脳萎縮が広がるにつれ、失語症は徐々に増悪し、さらに記憶、判断、思考なども障害され、認知症となる。
初症時の発話障害が失語症ではなく、構音障害の場合は「大脳皮質基底核症候群」が考えられる。「大脳皮質基底核症候群」は、一側優位の大脳半球皮質と皮質下神経核(特に黒質と淡蒼球)などの萎縮でおこるといわれる症状で、中年期以降に徐徐に始まり、ゆっくり進行する運動及び認知機能障害である。
(杉下守弘:「大正天皇(1879-1926)の御病気に関する文献的考察」『認知神経科学』第14巻第1号、2012年、 51-67)
(文=岩波 明/精神科医)