コカ・コーラ飲用時、ペプシでは反応しない脳の部位が反応…ラベル事前提示の条件下で
 「Gettyimages」より
「Gettyimages」より
読者の方は1980年代に一時期、日本でも行われた「ペプシチャレンジ」というキャンペーンをご存じでしょうか? これは一般消費者を対象に、ペプシコーラとコカ・コーラをブラインドで飲み比べてもらい、より多くの人がペプシコーラを好んだというCMです。
一方、両方のコーラのラベルを隠さなかったコカ・コーラ社による味覚調査では、より多くの人がコカ・コーラを好んだ結果になりました。これも知識が経験に影響を与えた事例ですが、これを神経科学の観点から研究した2004年のマクルーアをはじめとするヒューストンのベイラー医科大学神経科学チームらの論文を紹介しましょう。
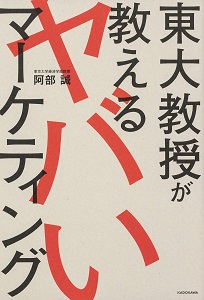 『東大教授が教えるヤバいマーケティング』(阿部誠/KADOKAWA)
『東大教授が教えるヤバいマーケティング』(阿部誠/KADOKAWA)彼らはfMRI(機能的磁気共鳴画像)を用いて、コカ・コーラとペプシコーラを飲んだとき、脳のどの部位が活性化するかを、ブランドを見せた場合と隠した場合とで比較しました。実験は、被験者がfMRIの大騒音の中で仰向けになり、口に咥えたチューブから液体を流し込まれるという、通常コーラを飲む状況とは大きく異なった環境で行われました。ブランド名が伏せられた場合は、どちらのコーラでも口に入ったとき、感覚(味覚)と快楽(糖分)を感じる脳の前頭前野腹内側部(VMPFC)が活動しました。
一方、ブランド名を明かした場合は、コカ・コーラだけ、脳の前頭前野背外側部(DLPFC)が反応したのですが、ペプシコーラでは反応しませんでした。DLPFCは、短期記憶や連想などの高度な認知機能をつかさどる部位です。これはペプシコーラにはないコカ・コーラへの特別な文化的感情やブランドイメージが、高次の脳機能を活性化させたと考えられます。
この実験により、VMPFCは感覚を、DLPFCは感情を、と別々の要因に影響を与えて、対象への選好が形成されると彼らは結論づけました。大がかりな実験のため、サンプル数が67と少ないのと、コーラを摂取している環境が非日常的であるという問題はありますが、脳内メカニズムを視覚化したことは、大きな進歩でしょう。
テイストテストにおけるバイアス
ところで、テイストテストでの環境が通常、食べ物や飲料を摂取する状況と違うことは、テスト結果にどのようなバイアスをもたらすのでしょうか?
官能評価と日常場面でのずれを理解することは、被験者ではなく顧客に美味しいといわれる商品を企画するためにも、企業の製品開発に重要な意味を持ちます。
ある研究では、被験者を、甘味、酸味、苦味など、個別の属性を評価してもらったあとに好き嫌いを聞いた分析条件、単に好き嫌いだけを聞いた直観条件、テイストテストであることを明かさずに飲んでもらったあとに好き嫌いを聞いた日常条件という、3つのグループに分けて、飲料に対する総合評価を比較しました。すべての被験者には、単純な計算問題を解かせてから飲料を飲んでもらったのですが、日常条件では何も告げずに、作業のお礼として飲料が提供されたあとに、その好き嫌いを聞きました。
結果は、日常条件の評価は分析条件の評価より有意に高くなりました。つまり、評価をまったく期待されなかった自然体の被験者は、細かい評価を要求されたテイストテストの被験者と比べて、飲料をより美味しいと感じたのです。
また、いずれもテイストテストを行うと告げられた直観条件と分析条件を比較すると、どちらの評価のほうが高いかは飲料によって違いました。このような結果になった理由としては、分析条件の被験者が、日常飲むときに重視する飲料の特性ではなく、評価を要求された個別属性に対して特段の注意を払ったことが挙げられます。
そして、これら個別属性の中で、より重視されるものがポジティブな属性であれば直観条件の評価より高くなり、より重視されるものがネガティブな属性であれば直観条件の評価より低くなってしまいます。普段飲むときには気にもかけない渋味やエグミなどの属性が評価項目にあったり、ノドで感じるような属性が評価項目から欠けていたりすれば、これらの影響を受けて総合評価が変わってしまうのです。
さらに、日常・直観・分析条件の間では、被験者の飲み方にも、大きな違いがありました。一口当たりの平均量も全体量も、直観・分析条件は日常条件に比べて少なかったため、評価に必要な分量だけを飲むという傾向がみられました。口につけた回数は、分析条件が直観条件や日常条件より多かったため、属性別評価のためテイスティングを慎重に行っていたことがうかがえます。
これら飲み方の違いも直接的、間接的に味覚の判断に影響を与えるでしょう。たとえば炭酸系の飲料は、一度にある程度の量を飲まないと、ノドで爽快感を感じられませんし、少量では舌に十分な酸味や刺激を与えられません。
私は大のビール好きで、飲みに行ったときは最初から最後までずっとビールです。アメリカに住んでいたときは、法律で禁止されていないので、自分でビールをつくったこともあります(サミエルアダムスのような味だと友人からは好評でした)。国産4社の違う銘柄を置いている居酒屋などでは、いろいろなブランドを混ぜて注文して当てっこをします。合宿など、旅館でビールを飲むときには、必ず1本1本違うビール、発泡酒、新ジャンルを混ぜて買ってきて、みんなでブラインドテイスティングをします。
それでも相変わらず正解を外してしまうことに、最近は慣れてくるとともに、納得しはじめています。やっぱり自分もラベルを飲んでいるんだなあと……。
(文=阿部誠/東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授)

















