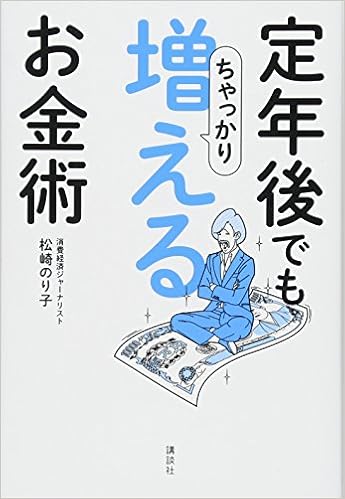コロナ時代の家選びはどう変わる?在宅勤務で「都心にマイホーム」の常識が一変か

夏休みを前に都道府県境をまたぐ移動が全面解禁になり、道路も混雑、観光地にも人出が戻ってきた。まるで、新型コロナ以前の日常を取り戻しつつある気にすらなる。
しかし、それは錯覚だ。第2波襲来におびえ、リモートワークや時差通勤・間引き出社を続ける企業も多い。特に、首都圏在住・在勤者は気が抜けない。なんといっても、感染リスクがもっとも高いのが「首都東京」だからだ。
東京都の人口は5月1日現在で1400万人(推計)を突破した。うち、対前年同月比で人口増加が多い市区町村は、世田谷区、品川区、江東区、練馬区、中央区の順。4月の入学や就職で転入が増えたという理由もあるだろうが、これらの区では、さらに「密」化が進んでいる。
コロナ禍の終息は当分見えない。それは、じわじわと我々の暮らしを変貌させている。これまでの「東京に住むのがベストチョイス」「マイホームを買うなら都心に近いほうが価値が落ちない」という常識は、今後も通用するのだろうか。新型コロナは住まい選びを変えるのか。マイホームは、この先も東京周辺に買うべきなのか。それを考えてみたい。
東京には人口が増え続けるだけの理由がある。人が住まいに求める要素が揃っているからだ。
「住まいを選ぶ基準として重視されるのは、まず利便性。職・住・遊の面で、都心もしくは都心に近い場所であればあるほど、仕事にも遊ぶにも便利だからです。その次に考える要素は、医・食・学。高度な医療が受けられるか、食のこだわりを満足させられるか、教育環境のレベルはどうか。これらの条件が揃っているエリアなら、不動産の資産価値も高いといえます」
そう語るのは、不動産市況分析のプロであり、LIFULL HOME’S総合研究所副所長の中山登志朗氏。「これらの条件にこだわって買うのが、これまでの正解だった」というが、新型コロナの蔓延で変化が起きつつある。
職・住・遊が充実した場所は“密”になりやすい
「職・住・遊、そして医・食・学に加え、もう2つの要素があるのですが、それは快適の『快』と安心の『安』。先の6つに比べると、もう少し個人的、メンタルな要素といっていいかもしれません。どんなに利便性が高いエリアでも、そこに住むことを自分が快適と感じられるか。それは、安心も同じです。安心といえば、これまでは防犯や防災面を指すものでしたが、新型コロナで防疫の意味を帯びるようになりました」(中山氏)
これまで重視されてきた住まいの条件はあくまで日常時のものであり、感染症のような非日常性のリスクが起きると、前の6つの要素の意味が逆転しかねないという。
「職・住・遊の利便性が高い場所は人が密集して住んでいますから、逆にリスクは高まってしまいます。タワマンなんて必ずエレベータを使うし、密閉された空間に何人も乗ってくるわけですから、もし感染者が1人いたらクラスターにもなりかねない。これまでは子どもにお受験させて有名校に通わせたいと思ってきたけれど、電車通学は不安だから近所の学校に通わせたいとか、大病院が近くにあると集団感染が発生したら怖いとか。
対コロナを軸に据えると、これまで重視されてきた利便性や経済合理性より、ここに住んで、果たして快適に安心して生活できるかという心理のほうが強くなってくる。(ウイルスを)人にうつさない、人からうつされないことを重要視すれば、住まいの条件も大きく変わる可能性があるでしょう」(同)
加えて、多くのビジネスパーソンが感じていることだろうが、この先、在宅勤務や時差出勤がメインになれば、優先順位は「会社まで近い」ことより「在宅で仕事できる十分なスペースがある」ことが先にくるだろう。
教育面もそうだ。これまでは高水準の教育を子どもに受けさせるためには大都市周辺に住む必要があったが、もしオンライン学習が本格導入されれば、日本全国どこへでも質の高い授業が提供されるようになる。北海道在住でも沖縄在住でも大都市の有名校にお受験し、そのままオンライン在学できる時代が来るかもしれない。
コロナ禍で「住みたい街」は変わるのか?
LIFULL HOME’Sでは、年に1回「住みたい街ランキング」を発表している。これはイメージによる「住んでみたい街」ではなく、実際に自社サイトの検索・問い合わせ数から算出した“実際に探されている街・駅”のランキングだ。
2020年2月に発表されたランキングは19年のデータによるもので、コロナの影響はまだなかったため、東京オリンピック・パラリンピック会場で話題だった勝どきエリアがトップになっている。
中山氏によると、近年は都心マンションの価格が高騰しすぎて、戸塚や八王子、船橋が上位にきていたこともあったが、消費税増税対策の優遇策もあり、都心回帰の動きが見えていたところだという。しかし、コロナ禍でまたランキングにも変動が起きそうだ。
「19年のデータではランキングを落とした八王子ですが、18年では3位です。なぜかといえば、駅周辺が再開発されて徒歩圏に新築マンションが分譲されているんですね。距離的には三鷹駅のほうが都心に近いけど、そこからバスに乗り換えて15分……という物件より、かえってアクセスがいい。トータルの通勤時間も、それほど変わらないかもしれない。それなら十分、八王子で家を買う経済合理性があるというわけです」(同)
さらに、言わずもがなのリモートワーク推奨で、購入条件はさらに一変しそうだ。もし、週に1回しか会社に来なくてよろしい、あとは全部オンラインでとなれば、都心まで片道2時間だろうが、極端に言うなら新幹線通勤だろうが、自分が快適だと思えるエリアで暮らすことができる。
都心でマイホームを買うならマンションなど集合住宅が第一の選択肢になるが、郊外なら一戸建ても夢ではないし、書斎が確保できるだけの広めの家が買える可能性も高まる。今後は、ワークスペースを設置するリフォームや収納の一部をデスクスペースに変更できる物件なども、どんどん増えてくるのではないだろうか。
また、余暇の過ごし方も変わる。これまでは都会の商業施設に出かけていたのが、我が家の庭でバーベキューを楽しんだり、家庭菜園やDIYに打ち込んだり。職・住・遊が、まったく別の色合いを帯びてくるのだ。
さらに、地方には、子育て層が移住すれば家のリフォーム代を助成してくれる自治体もある。数千万円の住宅ローンを組んで、毎月それを返すために35年あくせく働く……というライフモデルは、ひょっとすると前時代のものになるかもしれない。
「これまでは職住近接というのが、経済的に合理性があると思われてきました。でも、ネットが普及すれば物理的に会社の近くに住む必要はなくなる。離れていても、そのぶん住宅コストや生活コストが安く済むなら、経済合理性はそちらのほうが高いとも言えます」(同)
来年発表される「住みたい街ランキング」は、いったいどう変わるだろうか。
災害時の避難所にも発生する“密”リスク
さらに、新型コロナはもうひとつの「密」リスクをあぶりだした。自然災害が起きたときの避難所問題だ。このところ有感地震が相次いでおり、首都直下型地震の発生も予断を許さない。
台風シーズンになれば大規模水害の恐れもあるが、ただでさえ混み合う東京23区の避難所がコロナ対策のために受け入れ人数を絞り込めば、行き場のない避難難民があちこちで発生するだろう。東京一極集中は、災害に対してももろいのだ。
つまり、生活拠点を都心から離れた場所に置き、できるだけリモートワークに切り替えて出勤日を減らすのは、防災面でもメリットが大きい。企業や業種によって事情は異なるだろうが、どうしても出勤が必要な人とリモートでも勤務が可能な人とがうまく分散すれば、「密」の割合が薄まっていくことは間違いない。
「人気のエリアは、1にも2にも便利だから。便利なところは人口密度も高いんです。それが大都市圏の特徴で、その利便性を高めるために商業施設ができ、劇場や映画館などのエンタメ施設ができ、さらに人が集まってくる。しかし、人を集中させてきたことが一番のリスクに変わったのが、このコロナ時代なのです」(同)
コロナ時代に家を買うなら重視すべき要素は何か、これまでの常識を捨てて考えてみるべきだろう。
(文=松崎のり子/消費経済ジャーナリスト)
『定年後でもちゃっかり増えるお金術』 まだ間に合う!! どうすればいいか、具体的に知りたい人へ。貧乏老後にならないために、人生後半からはストレスはためずにお金は貯める。定年前から始めたい定年後だから始められる賢い貯蓄術のヒント。