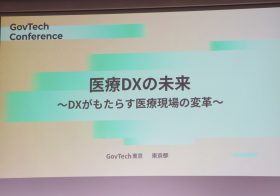【江川紹子の考察】木村花さんを追いつめたネット中傷問題と、侮辱罪厳罰化…懲役刑も視野

インターネット上の誹謗中傷への対策を強化するため、刑法の「侮辱罪」の厳罰化を検討している法制審議会(法務大臣の諮問機関)の部会は、法定刑に懲役刑を追加する法改正の要綱案をとりまとめ、近く法相に答申する。
ネットの誹謗中傷ーー発信者特定に壁
「誹謗中傷」を刑事事件として扱う場合、内容によって、適用できる罪名は異なる。そのうち名誉毀損罪は、「不倫をしている」「会社の金を横領した」といった、社会的評価を下げる事実を公然と流した場合に適用される。罰則は、最高刑が懲役3年だ。
これに対し侮辱罪は、具体的な事実を示していなくても、「バカ」「死ね」といった悪口や罵倒、容姿をあざけるなどの文言が公然と発せられれば適用され得る。ただし法定刑は拘留(刑務作業の義務を課さない、30日未満の身柄拘束)または科料(1万円未満の財産刑)と、刑法のなかで最も軽い。
侮辱罪改正の議論は、昨年5月、フジテレビ系列で放送のリアリティ番組『テラスハウス』に出演していた女子プロレスラーの木村花さんが、SNSで多くの誹謗中傷を受けた後に自殺した件がきっかけとなった。
木村さんのツイッターアカウントには、多くの誹謗中傷コメントが寄せられたが、そのうち「顔面偏差値低いし、性格悪いし、生きてる価値あるのかね」「お前のいちばん悪い所は未だに世の中に汚物を垂れ流しているところや」「ねえねえ。いつ死ぬの?」「死ねやくそが」「きもい」などと投稿した2人の男性が侮辱罪に問われ、科料9000円の略式命令を受けた。
注目されたのは、(1)多くの人が誹謗中傷をしていたのに、刑事責任を問われたのはたった2人だった (2)取り返しのつかない結果に比べ、誹謗中傷に対する法定刑が軽い――という2点だ。
(1)については、1年と短い公訴時効と、情報開示に消極的なSNS運営会社の対応などが壁になった。
5月23日付け日経新聞電子版によると、木村さんが死亡して3日後の時点で、誹謗中傷の投稿は約300件あった。警察は、このうち1アカウント当たり3回以上の書き込みをした7アカウントを悪質な事案として捜査対象にした。
しかし、米ツイッター社は侮辱罪での捜査照会に対しては、「(テロや殺害などの)緊急事案に該当しない」として応じず、発信者の特定に行き詰まった。結局、特定できたのは、木村さんの自殺を知って投稿を後悔し、木村さんの母親に謝罪のメールを送って名乗り出た20代の男性と、木村さんの遺族の代理人が米国の情報開示制度を利用して割り出した30代男性の2人だけだった。残り5アカウントは消去されてしまい、警察は復元もできず、独自に容疑者を特定することはできなかった。しかも30代男性の場合、略式起訴したのは時効のわずか2日前。ギリギリ間に合った。
公訴時効の長さは、罪の重さと連動する。法改正によって罰金刑や懲役刑を導入すれば、時効は3年に延びる。ネットでの誹謗中傷は容疑者の特定にかかる時間を考えれば、公訴時効1年はあまりに短すぎた。
侮辱罪の規定は、明治40年に刑法が制定されて以来、そのまま現在に至る。ネット時代の今は、誰でも容易に発信できる。そのうえ、リツイート機能などを利用することで、誹謗中傷コメントも手軽かつ広範囲に拡散してしまい、そのうえ記録は長く残る。1人に攻撃が集中して“炎上”する、ネット上のリンチもしばしば起きる。
専門家いわく「表現の自由に悪影響を及ぼすのではないか、という懸念は杞憂ではないか」
たとえば、自身が受けた性暴力被害を公表し、裁判を起こしたジャーナリストの伊藤詩織さんに対するネットリンチはすさまじかった。評論家の荻上チキさんらのチームが分析したところ、ツイッターでは伊藤さんに関する投稿を21万6294件収集し、そのうち計15.1%にあたる推計3万件超が、名誉毀損や誹謗など「セカンドレイプ」に相当するツイートだった、という。しかも、誹謗中傷はツイッターだけでなく、Yahoo!コメント欄など複数のメディアで展開される。伊藤さんは日本にいられなくなった。
ラジオすらなく、中傷の手段が張り紙やチラシなどに限られていた明治時代とでは、被害者が受けるダメージは比べものにならない。しかも、匿名での投稿など、身元特定はより困難になっている。
それを考えれば、今回の改正は時代の要請であり、むしろ遅すぎた、といえるだろう。
ただ「侮辱」は、口の悪い「批判」との境界線が曖昧で、処罰の客観的な基準を設けにくい。同じことを言われても、ひどく傷つく人もいれば、罵声には耐性のある人もいる。1人や2人からの誹謗は聞き流せても、集中砲火を浴びれば大きなダメージを受ける。
表現の自由にもかかわることだけに、曖昧さを残したまま、懲役刑まで導入するということに一抹の不安も残る。これについて、専門家はどう考えるのか。
刑法学者で法制審の委員でもある井田良・中央大学大学院教授は、懸念については「杞憂でしょう」と一笑に付す。
「懲役刑を入れるのは、『お金で済む問題ではない』という強いメッセージという意味合いがあります。ただ、(最高刑が)『懲役1年』では、実刑判決は考えられませんが」
同じ言葉でも人によって受け止め方が異なる、という問題はどうか。井田教授は、侮辱罪は被害者の心を傷つけることへのペナルティではないことに留意すべきだ、と指摘する。
「侮辱罪が保護しているのは、(誹謗された個人の)名誉感情ではありません。名誉毀損と同じく外部的名誉、つまり社会でその個人が得ている評価のことです。言われた本人が傷ついているかどうかといった個人の受け止め方より、一般的に考えて、(言われた言葉によって)その人の社会的評価が傷つくかどうか、が大事です」
たとえば、ある個人がいつ、どこで、誰にセクハラを行った、と具体的な「事実」をばらまけば名誉毀損だが、「あいつはセクハラ親父だ」と抽象的な悪口にとどまれば侮辱。どちらも、社会的評価を下げる発信という点では変わりはない。「セクハラ親父」呼ばわりされて傷つく名誉感情ではなく、この社会的評価を下げる、という点が被害として扱われる。ただし具体性に富む「事実」を伴う名誉毀損のほうが、より社会的評価を傷つける、という違いはあり、そのために刑罰もより重くなっている。
「したがって、まだ言葉がわからず、名誉感情を傷つけられているわけではない赤ちゃんが相手でも、(誹謗中傷すれば)侮辱罪が成立することはあり得る」
なるほど。では、批判との境界が曖昧な点はどうだろう。
「これだけ多くの誹謗中傷が飛び交うなかでも、侮辱罪が立件されるのは年に20件程度です。多くのものは大目に見られ、『誰が見てもひどい』というものしか対象になりません」
だから、表現の自由に悪影響を及ぼすのではないか、という懸念は「杞憂」というわけだ。
誹謗中傷コメント削除の迅速化、発信者特定手続きの簡素化、そして低額な賠償金額の是正を
憲法学が専門で表現の自由に詳しい曽我部真裕・京都大教授も、「(誹謗中傷の)程度や拡散の範囲、発言者の意図などを総合的に見て、一般人にとって受忍限度を超えているかを、裁判所が総合的に判断します」と述べる。
ただ、名誉毀損罪には表現の自由に配慮した免責規定がある。
・公共の利害に関する
・発信の目的は専ら公益を図るため
・内容が真実である
との要件がそろえば免責され、特に政治家や選挙の候補者については、社会的評価を下げる言論でも、内容が真実なら「罰しない」と明記されている。
しかし侮辱罪には、そうした規定は設けられていない。厳罰化によって、訴えが増え、その結果、政治家など公人への批判に対する捜査の介入や表現の自由の萎縮を招かないだろうか。
日本の裁判所は、表現の自由にかかわることでも、刑罰法規の文言を形式的に当てはめて、有罪判決を導きがちだ。官舎に反戦ビラをポスティングした件では、一審が住民の被害が極めて軽微で「刑事罰を科すほどではない」として無罪だったが、控訴審が逆転有罪とし、最高裁が上告が棄却されたため有罪が確定した。専門家からは批判が起きたが、裁判所の有罪判断は変わらなかった。
侮辱的表現との対決姿勢を鮮明にする政治家もいる。山本一太・群馬県知事は、自身のツイッターに「大バカ」「詐欺師」などと繰り返し投稿した者を裁判手続きで特定したと発表。「悪質な書き込みには断固として立ち向かっていく」と宣言した。相手が謝罪したため、山本知事はペナルティまでは求めていないが、今後、自身への否定的表現に対し、積極的に捜査や処罰を求める政治家が出てこないとも限らない。
もちろん、政治家に対しては何を言ってもいい、ということにはならないし、批判するときの言葉は極力選びたい。しかし、期待を裏切られた、公約を反故にされた、と有権者が感じたときに、政治家を「嘘つき」呼ばわりすることはあり得る。
「公共の利害に関する」発言であり、相手が政治家や候補者などの場合には、免責するなり、一般人とは異なる基準で判断することを明確にしておくことも考えたほうがいいかもしれない。
曽我部教授は、「(誹謗中傷を)刑事事件に持ち込むハードルはかなり高く、濫用されるおそれはあまり考えにくい」としながらも、次のように指摘する。
「懸念があるからには、改正の国会審議の中で、(大臣など政府の)答弁で表現の自由への配慮をきちんと確認すること、さらに附帯決議で乱用防止に釘を刺しておいたらいいのではないか」
侮辱罪厳罰化は、時代の要請とはいえ、ネット上の誹謗中傷対策という点では、効果を過剰に期待するのも禁物だ。罪に問われる、あからさまな侮辱表現を避けながら、個人の人格を貶めたり名誉感情を傷つけたり、あるいは特定の民族や集団へのヘイトスピーチを展開することは、いくらでも可能だからだ。
たゆまぬ啓蒙活動と合わせ、SNS運営会社などが明らかな誹謗中傷コメントを迅速に削除して被害の拡大を防ぐことを求め、さらには発信者特定の手続きを利用しやすくするなど、国内外への働きかけはさらに強めていかなければならない。また、被害者が民事裁判を起こして勝訴しても、賠償金の金額が低く、弁護士費用などの経費すら回収できない、という事態も改善する必要もあるだろう。
表現の自由を守りつつ、誹謗中傷による被害を少しでも減らし、起きた被害は速やかに回復して、言論空間をよりよいものにしていく努力は、さらに続けなければならない。
(文=江川紹子/ジャーナリスト)