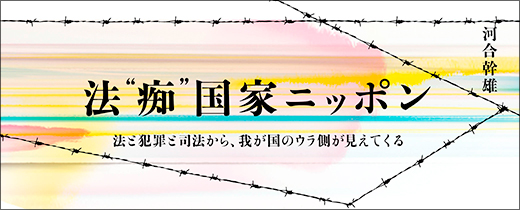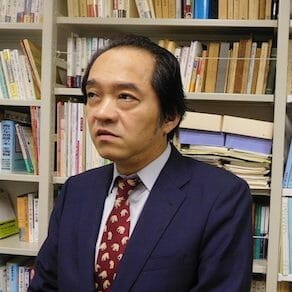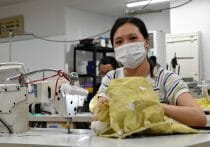「日本は難民を拒否する冷たい国」なのか?…法社会学者が考えるウィシュマさん事件の意味
名古屋出入国在留管理局にて収容中のスリランカ人女性(当時33歳)、ウィシュマ・サンダマリさんが2021年3月に死亡した。ウィシュマさんの死は、おりしも政府が第204回通常国会に提出した「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」(入管法改正案)審議のさなかに報じられ、人々の注目を集めることとなった。
政府の提出した入管法改正案は「退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとするため、在留特別許可の申請手続の創設、収容に代わる監理措置の創設、難民認定手続中の送還停止に関する規定の見直し、本邦からの退去を命ずる命令制度の創設等の措置を講ずるほか、難民に準じて保護すべき者に関する規定の整備その他所要の措置を講ずる必要がある」ことを改正の理由に掲げるものであった。
しかし、ウィシュマさんの死をめぐって繰り広げられた与野党協議の決裂や入国管理行政に対する世論の反発もあって、この第204回通常国会での採決は見送られ、さらにそこから1年たち、岸田政権発足後初の通常国会となる第208回通常国会でも再提出はされない見通しとなっている。
一方で2021年8月には、ウィシュマさんの死亡前の様子を映した施設内の監視カメラ映像の一部が遺族に開示され、政府は死亡の経緯に関する最終報告を公表している。しかし野党側は、「報告書は不十分」として映像の開示を要求し続け、2021年12月の衆院法務委員会の与野党筆頭間協議でようやく合意。遺族に追加の映像が公開され、衆参両院の法務委員会の議員らにも一部映像が開示されたものの、全容解明はいまだ道半ばだ。
ウィシュマさんの死は痛ましいものであり、故人の冥福を祈るとともに、二度と同じような事案が起きないよう、真相の究明と問題の把握、改善策の実行といった対応が求められることは論をまたない。また、ウィシュマさんの死が日本の入国管理行政に一石を投じたのもまた事実であろう。
しかし、ウィシュマさんの死を奇貨として入国管理行政を糾弾し、「人権意識に優れた欧米諸国では日本と比べものにならないほど難民を受け入れている。日本もそうあるべきだ」といった“出羽守”的な議論には、慎重な意見もある。もとより、入国管理行政は突き詰めて考えれば、「誰を国民として扱い、また扱わないか」「外国人をどう扱うか」という国家観そのものの問いに行き着くとともに、「人権を擁護するために、何が求められるか」という人権論とも結びつく。
法社会学者で桐蔭横浜大学法学部教授の河合幹雄氏は、「日本の入国管理行政を論じるには、まずその歴史・社会情勢、そして表裏一体の関係にある諸外国の入国管理行政と歴史・社会情勢を理解しなければならない。それらを理解すれば、入国管理行政の背景にある国家観や人権観も見えてくる」と語る。
その発言の意味とは? 日本の入国管理行政はどのような歴史・社会情勢に立脚しているのか? それは世界的にイレギュラーなのか? 日本、そして世界の入国管理行政の背景にある国家観・人権観とは?
本連載ではウィシュマさんの死という結果を招いた日本の入国管理行政・社会情勢と現在に連なる歴史的経緯について論じた前編に引き続き、難民の取り扱いに関する日本および欧米諸国の異同を後編として取り上げ、国家と人権について紐解いていく。
【前編「“外国人の人権は全て守られるべき”なのか?…法社会学者が問うウィシュマさん事件の意味」】はこちら

日本の入国管理行政と「難民」…「難民認定申請から6カ月経てば就労が許可される」の乱用という問題
――前編では自国民と外国人の間に存在する不平等や移民労働者の背景、日本における留学生のアルバイト解禁、日系ブラジル人の受け入れ、顔認証技術に後押しされる形で始まった外国人技能実習制度について解説していただき、労働者としての外国人に対する日本の入国管理行政の実像がクリアになりました。ところで、入国管理行政のなかで、難民についてはどのような制度になっているのでしょうか?
河合幹雄 本来の趣旨からいうと、難民はこれまでに説明した留学生や移民労働者、技能実習生といった問題とはまったく別物です。こちらはまさしく人権の問題であり、どんな人であっても、命の危険にさらされている人を助けようという話です。
日本で難民が問題となったのは1975年、ベトナム戦争終結と旧南ベトナム政権崩壊を背景とする「ボート・ピープル」の到来がきっかけです。彼ら彼女らはベトナム・ラオス・カンボジアのいわゆるインドシナ3国の出身者であり、インドシナ難民と呼ばれます。日本でいう難民とは、人種や宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、政治的意見などを理由に迫害を受けるおそれのある人で、インドシナ難民のほかにミャンマーからの難民などを受け入れています。そのほか、狭義の難民の定義には当てはまらないものの、戦争や国内紛争などによって難民と同様に国に帰ることができない人にも人道的配慮による在留特別許可がなされることがあります。
難民問題が外国人労働者の問題と関連してくるのは、2018年1月に廃止されるまで、「難民認定申請から6か月経てば、就労が許可される」という制度の運用方針が存在したためです。また、難民制度はどんな人であっても、命の危険にさらされている人を助けようという趣旨ですから、難民認定申請中は送還停止効が発生し、何回目の申請であっても送還が一律に停止されます。この制度が一部で悪用され、就労目的で何回も難民認定申請を繰り返すというケースもありました。法務省もこうしたケースを問題視し、現在では個別の事情に応じて難民認定申請中の就労許可・不許可を判断しているほか、2019年には「難民認定申請をすれば日本で就労できるというものではありません」といったお知らせを出すなどしています。
政府の提出した入管法改正案も、3回目以降の難民認定申請については申請中であっても送還を可能とするといった内容が盛り込まれていました。ウィシュマさんの死をめぐって繰り広げられた与野党協議の決裂や、入国管理行政に対する世論の反発によって、入管法改正案が第204回国会で成立することはなかったわけですが、入管法改正案もそうした難民認定制度の穴をつくようなケースに対処するための改正という側面があり、この改正案とウィシュマさんの死を絡めて「日本は人権意識に優れた欧米諸国と違って難民に冷たい」といった結論を導くのはいささか乱暴な議論ではという印象を受けます。

「人権意識が高い欧米諸国は、広く難民を受け入れている」は本当なのか?
河合幹雄 難民の取り扱いに関する日本および欧米諸国の異同について、さらに掘り下げていきましょう。確かに、欧米諸国が日本と比べて難民認定率が高いこと自体は事実で、その差は国によっては数百倍にも及びます。しかし、この事実だけでもって、日本と欧米諸国の難民問題を語るのは表層的にすぎます。
まず、いうまでもないことですが、地理的条件が違います。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)のデータによると、世界全体で見た難民認定申請者の出身国ランキング上位は、ベネズエラやシリア、アフガニスタンです。これらと地続きないしは近接している欧米諸国と、四方を海に囲まれた極東の日本という地理的要因を考える必要があります。
さらに、当然の話ですが難民認定率とは、難民認定申請者数に占める難民認定者数の割合です。つまり、先ほどお話ししたような送還逃れのための難民認定申請者が多ければ多いほど、難民認定率は下がるものだということです。日本における難民認定申請者の出身国は多岐にわたりますが、主なところはトルコ、ミャンマー、ネパール、カンボジア、そしてウィシュマさんの出身国であるスリランカとなっており、これら5カ国で半数以上を占めています。ちなみに、世界全体で見た難民認定申請者の出身国ランキング上位5カ国からの申請者は、100人にも満たないのが現状です。もちろん出身国だけで難民認定の可否が判断されるようなことがあってはなりませんが、こうした事実は議論の前提として理解しておくべきでしょう。
また日本の難民認定申請者数は、申請中の在留・就労に関する制度運用と密接に関連しています。2005年に約400人であった難民認定申請者数は、難民認定申請から6カ月経てば就労が許可されるという制度の運用が開始された2010年に約1200人、制度最終年の2017年に約2万人弱、濫用‧誤用的な難民認定申請には在留や就労を認めないとして制度運用の見直しが行われた2018年に約1万人と、運用方針の変更に連動して増減しています。
加えて、特に欧米諸国においては難民認定の間口は広いものの、その後の扱いは厳しいといった傾向もあります。単純労働や季節労働に従事することの多い移民労働者と異なり、人種や宗教、政治的意見を理由として迫害され、難民認定者のなかには手に職を持った技術職や専門職の人も一定数存在します。しかし、それでもなお、着の身着のままで逃げて来ざるを得なかった難民認定者が異国の地で自立した生活を営んでいくにはさまざまな困難があります。数々の困難に行く手を阻まれ、犯罪に手を染めてしまう人もなかにはいるでしょう。
そうした人に対して、欧米諸国の多くは抜本的な自立支援策を講じることなく、簡単に収容措置を行い、社会から切り離すといった対応をとっています。もとより難民認定者のその後の自立支援については日本でも問題になっているところですが、欧米諸国においては難民認定者数が多いだけに、そうした問題がいっそう顕在化しています。さらにいえば、前編で言及した、移民労働者の子どもが言語障壁や苦しい家庭環境のために現地社会に適応できず、不満を募らせた結果、まだ見ぬ母国への憧憬と生まれ育った現地社会への怨嗟を屈折させ、自身が生まれ育った現地社会やヨーロッパ諸国を対象とする「ホームグローンテロリスト」となってしまう問題は、難民認定者の子どもについても共通する話です。
だから難民はなるべく受け入れるべきではない、などというつもりは毛頭ありませんが、今までお話しした事情を踏まえれば、日本の難民政策は立ち遅れている一方、欧米諸国の難民政策は成功しているとはとても結論づけられません。むしろ欧米諸国の難民政策は大失敗しているといってもいいくらいです。
まとめると、移民労働者にせよ難民にせよ、外国人を社会に受け入れるには相応の社会的コストが発生するのです。移民労働者についてはそのコストに見合うベネフィットを社会が享受できるか。難民についてはコストに相対するものが人権であるだけに、コストベネフィットの関係で判断する問題ではありませんが、どのようにコストを減らし、残ったコストを負担するか。そうした議論が必要ですし、欧米諸国の真似をすればうまくいくものでもないということです。
ウィシュマさんが「スリランカに送り返されるべき対象だ」とされたこと自体は妥当ではないか
――欧米諸国は人権意識が根づいていて難民を手厚く遇している一方、日本はそうした国と比べると、人権意識への配慮において遠く及ばない――といった単純な話ではないということですね。
ところで報道によれば、ウィシュマさんも難民認定申請を行っていたとのことですが、ウィシュマさんの事件と難民問題との関係についても解説していただけますか。
河合幹雄 公式発表である「令和3年3月6日の名古屋出入国在留管理局被収容者死亡事案に関する調査報告書」を読む限り、まずウィシュマさんは千葉の日本語学校への留学を理由として来日したのち、同じくスリランカ人の男性と恋仲になり、静岡に居を移しています。その後、学校から所在不明として除籍されたものの、難民申請を行っています。ここで先述の送還停止効が発生したことで、就労はできないものの、一応の在留が認められました。その後、難民にあたらないとして在留期間の更新が認められなかったため、彼女は難民申請を取り下げます。
ちなみに、難民申請の理由について同報告書では「スリランカ本国において、恋人がスリランカの地下組織の関係者とトラブルになった。同組織の集団が家に来て、恋人の居場所を教えなければ殺害すると脅迫され、暴力を受けた。危険を感じ、恋人が先に来日し、私がその3か月後に来日した。帰国したら恋人と一緒に殺される」となっていますが、そもそもウィシュマさんと恋人が出会ったのは日本であるとウィシュマさんと恋人の両方ともが認めているようですし、あまり真実味は感じられません。
話を戻します。ウィシュマさんは難民申請を取り下げた後、所在不明となり不法残留状態となります。そこで恋人から家を追い出されたとして警察に出向いたところ、不法残留者として逮捕され、名古屋出入国在留管理局に収容されました。当初はスリランカへの帰国を希望していたようですが、支援者からのアドバイス等を受けるなかで在留希望へと転じたようです。その後、仮放免申請を行うものの、一度難民申請取り下げ後に所在不明となっていたこともあり、不許可となっています。その後、体調不良等を理由に再び仮放免申請を行い、申請中にウィシュマさんを診察した医師が「仮放免をすればよくなる」と言及したことから、体調回復の上で仮放免する方針を立てた矢先、救急搬送され、搬送先の病院で亡くなったということのようです。
以上をまとめれば、ウィシュマさんを「スリランカに送り返されるべき対象だ」としたこと自体については、入国管理行政上の問題は見いだせず、ただ、それがために、ウィシュマさんが十分な医療を受けることができなかった点については大いに問題があった――と考えるべきである、ということでしょう。調査報告書にも実際、収容中の医療的対応のあり方や収容継続の適切性、DVに関する事実関係確認の手続きなどについて至らない点があったことが言及されています。ゆえに、ウィシュマさんをただ入管行政に翻弄された“無垢で不幸な被害者”だとして済ませるような印象操作は慎むべきではないかと思います。
もちろん、調査報告書がすべての真実を正しく表しているわけではないかもしれない……と疑ってかかる必要はあるでしょう。それはそれとしてウィシュマさん事件は、多くの複雑な要素が不幸に絡み合った結果生じてしまった、そもそも非常に対処が難しい事例であった――ということは、きちんと理解しておく必要があると思います。
日本の入国管理行政が、諸外国と比較して大きくイレギュラーなわけではない
河合幹雄 ここまで前後編にわたって、日本のみならず欧米諸国の歴史・社会情勢とも関連づけながら、入国管理行政、さらにはその背景にある国家観や人権観について考えてきました。巷のイメージと違って、日本が世界的に大きくイレギュラーなわけではなく、どの問題をとっても非常に多面的で単純な話でないことがおわかりいただけたと思います。
繰り返しになりますが、ウィシュマさんの死自体は当然回避されるべきものであったし、その意味で入管側に一定の責任があることは間違いありません。しかしだからこそ、故人の冥福を祈るとともに、真相の究明と問題の把握、改善策の実行といった対応が求められます。そのためにこそ、背後にある歴史や社会情勢といったものについてしっかりとした認識を持ち、それを踏まえて議論していくことが大切ではないかと思いますね。
(構成=青木 隼)