京都が「ディープテックの聖地」になる…「行政×スタートアップ」の化学反応

●この記事のポイント
・国内最大規模の国際スタートアップカンファレンス「IVS」が、3年連続で京都において開催される。さまざまな都市で開催してきたIVSだが、京都はスタートアップ支援の体制が他自治体と異なると評価する。
・京都府でスタートアップ支援を担当する中原氏は、スタートアップを支援することが社会課題解決につながると実感すると語る。
国内最大規模の国際スタートアップカンファレンス「IVS」が、今年も京都で開催されます。京都府が実行委員会メンバーとして深く関わるIVSは、単なる一大イベントにとどまらず、古都が描く未来のスタートアップエコシステム形成の起爆剤となっている。
この度、IVSを京都で開催するにあたりスタートアップエコシステム拡大のための重要な役割を担う、京都府商工労働観光部産業振興課参事の中原真里氏にインタビューを実施。なぜ京都府が実行委員会という形でIVSを運営しているのか、学生や研究機関が集積する「ディープテック」という京都の強みをどう生かし、ベンチャーキャピタル(VC)やビジネス型人材を呼び込もうとしているのか、その戦略と熱い想いを深掘りした。行政がスタートアップ支援を通じて「社会を変える」という、その新しい発想の源流に迫る。
目次
なぜ京都府はスタートアップ支援に注力するのか
――――スタートアップやベンチャーに関心を持ったのはいつ頃からですか。
中原氏 実は、就職してから1年間だけ東京の大学院に来ていたことがあり、それは、どういうふうにしたら官民連携が進むのか研究するためでした。その大学院時代、大企業の方々がスタートアップと連携して新産業を起こす取り組みをしているとか、自分自身が起業しているという方にたくさんお会いして、新しい世界に触れました。
行政の人間は、自分が何者であるかを多く語る立場ではありません。異動で誰がその役職に就いても、行政の連続性こそが大切だからです。しかし、起業家の方は個人として自分は何をしているのかを語るので、とても刺激をもらいました。また、そういうことに憧れもありますし、そういう方々のチャレンジにすごく共感することもあります。
今の自分はそういうポジションにつけないにしても、起業家の方々を応援することで社会が変わるのではないかと感じています。
――行政がスタートアップ支援することで社会が変わるというのは、新しい発想ですね。
中原氏 入庁して福祉や市町村財政などの業務に携わってきましたが、これまでの枠組みの中では、自治体の経営努力で解決できることも限界に近づいてきていると感じるようになりました。社会のあり方が多様化して必要な社会サービスが増えていく一方で、人口減少等の社会構造の変化を背景に、行政だけでは最善な形が描けない、という分野も出てきているように感じています。。そんな中で、“社会に対して何かしたい”という強い思いのあるスタートアップの方々と連携することで社会課題解決の早道があるんじゃないかと考えるようになりました。
今はスタートアップの方々を支援する先に社会課題解決につながるということを強く感じながら、IVSを支援させていただいています。
――2023年と24年にIVSに携わるに至ったきっかけを教えてください。
中原氏 出会いは2021年に遡ります。私が20年に商工労働観光部に着任して1年ほどスタートアップ支援をしていたときは、京都にスタートアップの数がまだ300~400社ほどでしたし、飛び抜けて成長しているようなところはまだないような状況でした。スタートアップの方々も経験豊富な方に話を聞きたいと言っていましたが、それこそ資金調達する際は、連続企業家や投資家みたいな方々が京都にはいなくて、どうしても首都圏に多いという課題感がありました。
でも、京都のスタートアップにとって環境を良くするには、ネットワークを作ってあげないといけないというところで、お世話になっているアドバイザーの方たちからスタートアップや投資家のコミュニティがあるという話を聞き、IVSの方々をご紹介いただきました。そして、島川さんや現在の運営メンバーとお話させていただいたというのが始まりです。
京都開催の話は出てきましたが、まだコロナ禍だったので、結局通常の形では開催できませんでした。IVSにずっと参画されている起業家や投資家の方々をIVS側で組んでいただき、オンラインで京都のスタートアップがいろいろ相談できる場を設けたのが2022年の3月でした。
――2023年の京都から招待制をやめて大規模開催になりましたね。
中原氏 はい、コロナ明けに世界的にもスタートアップの盛り上がりがみられる中で、IVS側も日本が他国に後れを取らないよう、国際標準の本格的な国際カンファレンスにしようという方針になっていました。また、すでに起業した人ばかりでなく、これから起業する層を増やしていこうということやグローバル企業とのネットワーク構築などもテーマとなり、招待制をやめることになりました。学生が多く海外での認知度が高いという都市ブランドのある京都であれば、そういう方々も呼び込みやすいということで開催地に選ばれました。
京都で大規模に開催したいというオファーをいただき、国際カンファレンスという形なら京都としても力を入れて支援する意義があるということで合意しました。
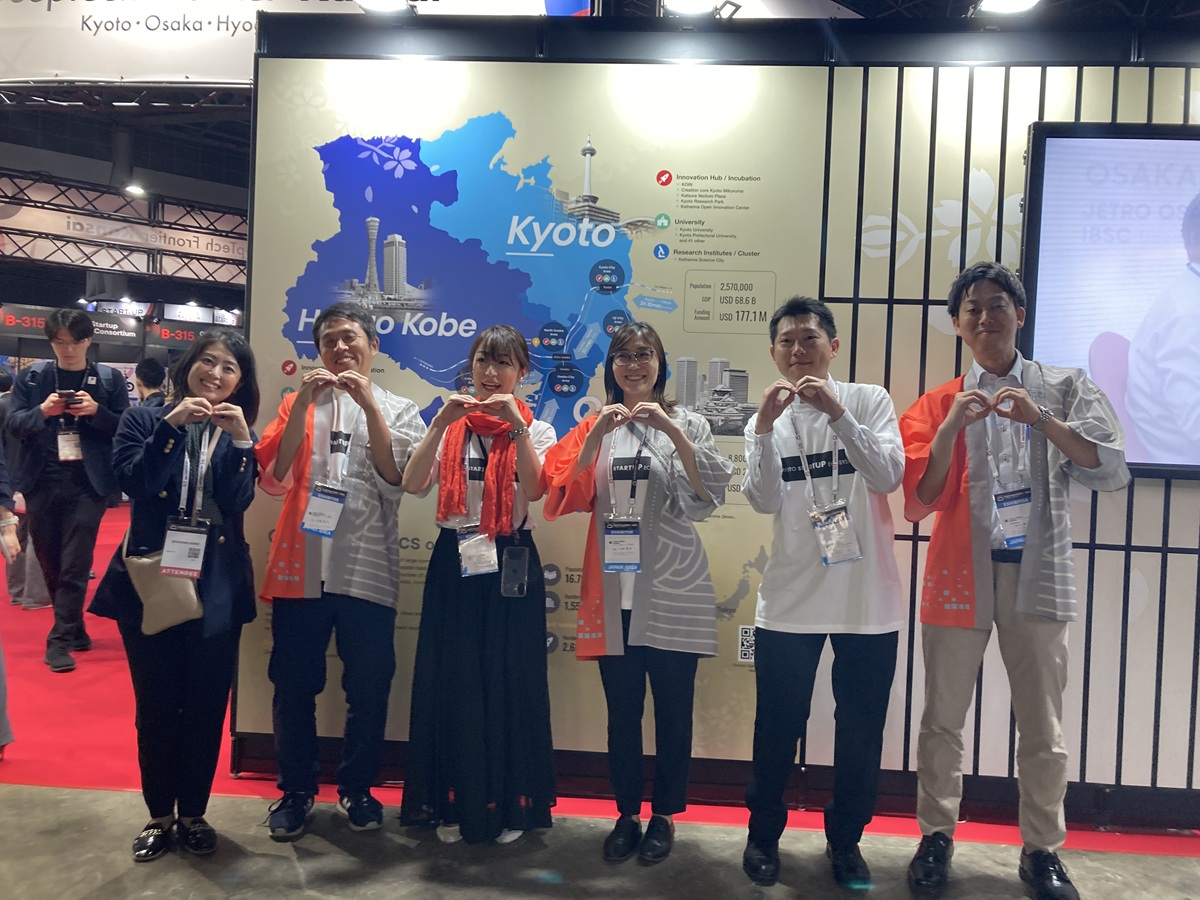
観光だけでなく“スタートアップ都市”としての情報発信
――IVSを京都で開催して得られた成果や手応えについてお話しください。
中原氏 成果は3つほどあったと思います。1つは、京都とスタートアップという言葉が結びついて、大きく発信されたということです。スタートアップ支援の取り組みはしてきましたが、観光地としての圧倒的な世界的ブランディングの前では、京都をビジネスの地と認識いただくことは一筋縄ではいきません。京都でスタートアップという形で情報発信ができたのは非常に大きくて、行政だけではできなかったと思います。
2つ目は、IVSが京都のスタートアップ関係者やビジネス界隈の方々が一堂に会する機会になり、一気に距離が近くなったことです。京都のスタートアップエコシステムで関わる方々はもちろん顔なじみだったり、事業会社の方々とも接点はあったのですが、一つの事業に一緒に取り組むことで、お互いの強みや今力を入れていること等があらためてわかる機会となりました。事業会社のスタートアップ連携の窓口になっている担当者とも対話をさせていただく機会が増え京都の産業界とスタートアップ関係者の関係性が強くなったと感じています。
3つ目は、実際に京都のスタートアップ・エコシステムの可能性を直に感じていただけたことで、首都圏のVC(ベンチャーキャピタル)がブランチを4社ほど立てていただけたことです。IVSの求心力で府内外からたくさんのスタートアップや投資家の方々、さらには学生にもにお集まりいただけたからこそ、このような動きが生まれたのかなと思っています。
――カンファレンスもスタートアップ支援の1つですが、京都府としては今後、どのように支援していきますか。
中原氏 京都の強みは、やはりディープテックだと思います。大学や研究機関の集積を核に、そこから生まれた研究シーズから事業を生み出していくというものです。実際、この分野の企業が大きく成長してきていますし、全体に占める割合も高いというのが京都の特徴です。京都府としてはディープテックスタートアップの創出・成長環境のさらなる充実に向けて、これまで以上に力を入れていきたいです。
それに関して今の課題は、大学やシーズはたくさんあっても、ビジネスサイドの方々が首都圏に集まっているといるので、事業化して成長させるところが弱いということです。例えば、こういうニーズを抱えている人がいるから、その方にはこのシーズが使えそうだということを見出して事業化するビジネス人材が足りていないわけです。そういう人材をうまく京都に呼び込むことがまず必要かなとも思っています。例えば、ベンチャークリエイト型のVCであるとかインキュベーターの知見を京都に呼び込むとか。そして、最終的には京都で生まれて京都に定着できるような環境を整えていければいいですね。
ただ、海外から見れば日本市場はそれほど大きくないし、新しいものを取り入れるのに慎重な国民性もある。ビジネス環境として日本で事業化を進めるメリットを感じてもらえないのではないかと思ったりもしますが、京都ぐらいの規模だからこそ特区制度などを使った規制緩和や、社会受容性向上のための住民理解の促進なども含め、どうすれば新たな技術やサービスがいち早く導入できるのかを考えたりもします。この分野なら京都は世界でどこよりも社会実装が早くできそうだというモデルが1つでも出せればいいですね。そうすれば、さらに世界からも注目される都市になれるので、今年から検討を始めて、向こう何年間でこのモデルを出していく構想を持っています。
――スタートアップを盛り上げるために、国内で他自治体との連携はありますか。
中原氏 2020年から国は、「世界と伍するスタートアップ拠点都市」を全国で数か所選定し、集中的に支援して育てていくとしています。京都は大阪・兵庫とともに「京阪神」として選ばれています。それまでも情報連携はありましたが、選定されてからはもう1つの主体として京阪神でスタートアップ支援には取り組んでいます。ディープテック系の成長環境を整えていくということも大阪や兵庫と合意して進めています。大学のコンソーシアムも今は関西圏で構築して、関西のシーズとしてどういうふうに事業化するかを考え実践しています。
特にグローバルプロモーションについては関西一丸で取り組みましょうっていうのがあります。京都から海外に打って出られる段階にあるスタートアップは、600社の中でも限られていますが、それが京阪神で集まれば、それなりのボリュームになります。そうすると海外の投資家の関心を惹きつけやすくなると考えています。
京都独自のスタートアップエコシステム
中原氏の言葉からは、京都府が「IVS」を単なるイベントとしてではなく、京都の産業構造そのものを変革し、未来を創造するための戦略的な一手として捉えていることが明確に伝わってくる。大学や研究機関が持つシーズを核とした「ディープテック」という圧倒的な強みを軸に、IVSが呼び込んだVCや、今後さらに呼び込もうとしているビジネス人材が融合することで、京都は「知」と「事業化」が高速で循環する、独自のスタートアップエコシステムを築こうとしている。
「完成された街」ではなく、常に変化し、関わる一人ひとりの手によって未来がつくられるように、行政が旗振り役となりながらも、多様なプレイヤーを巻き込み、有機的に成長するエコシステムを目指している。
「起業家の方々を応援することで社会が変わる」という中原氏の信念は、まさに行政が果たすべき新たな役割を示唆しているのではないか。IVSを起爆剤とし、京都が「ディープテックの聖地」として世界にその存在感を示す日は、そう遠くないかもしれない。古都が放つ、新たなイノベーションの光に期待が高まる。
(文=横山渉/ジャーナリスト)











